まず知っておきたい「馬」と神社仏閣の基礎知識

「徳島で“馬”を感じる旅って、何から始めればいい?」――答えは意外と簡単です。神馬像に会い、旧馬場筋を歩き、滝の音に耳を澄ませながら絵馬に願いを書く。それだけで、古代から続く祈りの時間へ自然に入っていけます。本記事は、一宮神社の重文本殿と馬像、助任の馬場筋、深瀬八幡の午尾の滝、北島の競馬天井絵、三好の大杉まで、阿波の“馬”を軸に見どころを体系的に紹介。モデルコースやマナー、写真のコツも整理しました。地図アプリを片手に、過去と現在が交差する“馬の徳島”を歩いてみませんか。
絵馬のはじまりと意味
神社で目にする木札の「絵馬」は、もともと“本物の馬”を神に捧げた古い祈りの形がもとになっています。雨を望むときや国家的な祈願の場で神馬を奉納する習わしがあり、やがて経済的・飼育面の負担から、土製・木製の馬、さらに「馬を描いた板」へと変化しました。これが絵馬の原型です。平安期にはすでに図像としての絵馬が広がり、神々への願いを視覚化して伝えるツールとして定着しました。祈雨の際には黒馬、長雨を止めたいときは白馬(のちに赤馬を用いる地域も)という色分けの伝承も各地に残ります。現代の私たちが旅先で絵馬に願いを書くのは、古代からの祈りを手のひらサイズに受け継ぐ行為といえます。願いは「誰が・いつまでに・どうなりたいか」を肯定文で具体的に書くと、後から読み返したときにも自分の指針になります。
神馬・狛馬ってなに?
「神馬(しんめ)」は神の使い、あるいは神が乗る馬を意味します。古記録には祭礼で実馬を曳く例が多く見られ、特定の神社では神馬舎で白馬を飼い、年中行事に登場させることもありました。時代が下ると実馬に代わって木や石の馬像が境内に置かれ、参道や拝殿前で悪を祓い、参拝者を守護する存在として親しまれます。各地で俗に「狛馬」と呼ばれる対の馬像が据えられ、阿波の一宮神社(徳島市)でも拝殿前に堂々たる馬像が確認できます(現地写真や参拝記録に広く掲載)。筋肉の張りや鬣の流れなど写実的な造形が多く、地域の信仰の厚さを可視化するランドマークになっています。参拝時は台座や囲いに手を触れたり、乗ったりしないのがマナーです。
十二支の「午(うま)」の縁起
十二支の午は、暦上で陽気が極まり勢いが強まるサイクルを表します。日本では古くから馬が“前へ進む力”“仕事を運ぶ”象徴とされ、武家社会では軍馬、近世以降は物流・交通の主役として生活を支えました。この歴史背景から、午年や馬図の授与品には「勝運」「飛躍」「道中安全」などの意味づけが重ねられています。とはいえ、干支はもともと時間・方位の記号体系であり、吉凶を直線的に断じるものではありません。大切なのは、暦の知恵を“行動のスイッチ”にすること。午のイメージにあやかり、計画を前倒しで実行する、迷ったら一歩踏み出すなど、旅や日常の意思決定に役立てるのが実践的です。神社巡りで馬の像や馬図に出会ったら、背筋を伸ばして深呼吸。前進のモードに切り替わります。
祈願と馬の関係(雨乞い・五穀豊穣・交通安全)
雨乞いに黒馬、止雨に白馬(あるいは赤馬)という色の使い分けは、天候と馬を結びつける象徴的な知恵でした。馬は雲を呼び風を切る存在として畏敬され、稲作社会では水の巡りを司る神へのメッセンジャーと見なされたのです。稲の生育と直結するため、五穀豊穣の祈りにも馬が登場します。近世になると街道が整備され、馬は物流の要へ。そこから「道中安全」「仕事運」「商売繁盛」の願意が馬図の絵馬や護符に重なっていきました。今日では実馬の奉納は稀ですが、馬像への一礼や馬図の絵馬に願いを託すかたちで文化は続いています。旅の安全祈願なら、出発日・目的地・守りたいことを具体的に書くのがおすすめです。帰宅後にお礼参りをすると、祈りの循環が整います。
参拝マナーと絵馬の書き方Q&A
鳥居の前で軽く一礼し、参道の中央を避けて歩きます。手水舎では柄杓一杯の水で「左手→右手→左手に水を受けて口をすすぐ→柄杓の柄を洗う」の順で清め、手ぬぐいで軽く拭きます。拝殿では賽銭→鈴→二拝二拍手一拝が基本。願いは心中で丁寧に伝え、終わったら深く一礼。絵馬は表面に願いを肯定文で、裏面の指定があれば指示に従います。個人情報は最小限に留め、掛所では他の絵馬に触れないように。写真撮影は人の顔や個人名が写り込みやすい場所なので、プライバシーに配慮しましょう。境内での飲食・通話・ドローン飛行は禁止が基本。迷ったら社務所に確認すれば安心です。こうしたベーシックな所作を守るだけで、初めてでも清々しい参拝体験になります。
徳島市エリアの「馬」ゆかりスポット案内
一宮神社(馬の像で知られる社)
徳島市一宮町の一宮神社は、阿波を代表する古社で、本殿は寛永7年(1630)建立の国指定重要文化財。千鳥破風や唐破風を備えた華麗な意匠が今も輝き、社殿の装飾や木鼻の細工は必見です。さらに拝殿前には堂々たる一対の馬像が据えられ、地域の馬信仰の厚みを物語ります(現地写真・参拝記録で広く確認される事実)。像は写実的で、前脚の踏み込みや筋肉の張りに力が宿り、参拝者を迎える守護の存在となっています。まずは手水で身を清め、馬像に一礼してから拝殿へ進むと、参拝の気持ちが自然と整います。授与所の対応時間は季節で変わることがあるため、訪問前に最新情報を確認すると安心。文化財の社殿と馬像のコントラストが、この社の“顔”です。
下助任の八幡社と“助任馬場”の歴史
徳島の城下北辺を歩くと、下助任町に小社の八幡社が鎮座しています。かつてこの一帯には神事競馬が行われた「助任馬場」があり、町を東西に貫く直線道路が“馬場筋”と呼ばれていました。明治初期まで祭礼で紅白に分かれて競馬を行ったと伝わり、地名や通りの線形に当時の記憶が残ります。今も地図を開けば、城下の筋違い道路のなかにスッと伸びる直線が見つかり、馬が駆け抜けた往時を想像できます。現地を歩く際は、生活道路として車の往来があるので端に寄って安全第一で。社頭の案内板や地域の郷土誌を手掛かりに、城下の都市設計と祭礼文化が重なり合う面白さを感じてみてください。近年は地域イベントで歴史紹介が行われることもあります。
津田八幡の授与品と絵馬チェック
徳島市の津田八幡神社は、八幡信仰らしく勝運・厄除の願いで参拝者が集う社。境内の大楠が印象的で、清々しい木漏れ日の下で手を合わせると気持ちが整います。授与所では御朱印やお守りの頒布が行われ、時期により意匠が更新されることも。馬そのものの神事が伝わるわけではありませんが、八幡と武士・馬の関係の深さから、馬図の絵馬に「勝負運」「仕事運」「道中安全」を託す人が多いスポットです。参拝の作法は基本形で大丈夫。撮影の際は拝殿や授与所の業務を妨げない位置から、他の方の祈りの時間に配慮しましょう。地元の情報発信は頻繁に更新されるため、授与品の詳細や御朱印の書置き有無は直近の案内をチェックすると確実です。
城下町に残る馬関連の痕跡を歩く
徳島城下は、吉野川の支流である助任川・寺島川を巧みに取り込んで外堀とし、武家地・町人地を配した整然たる都市でした。城北側の助任エリアには、八幡社へ向かう直線道路=馬場筋の記憶が残り、道幅や交差の仕方に馬の通行を想定した設計思想がにじみます。現地散策では、交差点の見通しや道の直進性、周辺の神社配置に注目してみましょう。往時の競馬や流鏑馬を直接再現する行事は見られなくなりましたが、地名・図面・古写真に“馬のまち”の痕跡が点在しています。古地図アプリや市の歴史資料を片手に現在の地形と重ね合わせると、街そのものが巨大な博物館のように感じられます。歩きやすい靴で、交通安全を守りながら静かに楽しむのがコツです。
徳島市内ぐるっと散策ルート
効率よく“馬”の手触りをたどるなら、徳島駅を起点に半日で回る小さな周回が便利です。例として、午前に一宮神社(重文本殿と神馬像)を参拝し、市街へ戻って下助任の八幡社界隈を歴史散策、さらに津田八幡で勝運と道中安全を祈願、最後は徳島中央公園(徳島城跡)で城下の地理を体感しながら締める流れ。公共交通+徒歩の組み合わせで無理がありません。昼食は移動の合間に地元の食を楽しみつつ、神社の境内では飲食や大声の会話を避け、静けさを尊びましょう。絵馬は各社の指定に合わせて掛け、個人名は略号にするなど配慮を。歴史の要点を押さえながら短時間で回れる、満足度の高い市内コースです。
阿南・加茂谷:午尾(ごお)の滝と深瀬八幡
午尾の滝と社域の自然美
阿南市の加茂谷に鎮座する深瀬八幡神社の社域には、「午尾(ごお)の滝」と呼ばれる瀑布があります。水量によって流れが細く“馬の尾”のように見えることから名が付いたと伝わり、渓谷の緑に赤い社殿が映える景観は四季折々に表情を変えます。落差は約30メートルとされ、雨後には水煙が立ち上るドラマチックな光景に。ここで注意したいのは、信仰の置き方です。深瀬八幡神社は八幡系の神を主祭神としますが、境内の午尾の滝は御神体とされ、水の神・水速女命(みずはのめ)を祀ると伝わっています。つまり、社の中心に八幡、滝の霊域に水の神という二重の信仰が息づくのです。参拝ではまず拝殿で礼を尽くし、それから滝へ向かうと心の流れが整います。
参拝と滝めぐりの安全ガイド
山あいの社域は天候の急変があり得ます。足元は滑りにくい靴、両手が空く軽装が基本。滝へは整備された道を利用し、柵やロープを越えない、濡れた岩に乗らない、増水時は近づかないことが鉄則です。写真撮影は展望所から行い、三脚を使う場合は通行の妨げにならない場所に。虫刺され・日差し対策の準備も有効です。社務所が開いている時間帯であれば、道順や危険箇所の簡単な質問にも応じてもらえることがあります。滝は自然そのものなので“無理をしない判断”が最優先。参拝者同士で道を譲り合い、静かな環境を壊さないよう会話は控えめに。水場の撮影では、他の方の祈りや個人情報(絵馬など)が映り込まないよう配慮するのも大切です。
アクセス&駐車のポイント
公共交通で向かう場合は、徳島駅からJRで阿南駅へ。阿南駅から加茂谷方面の路線バスを利用し、最寄りの停留所から徒歩圏で社域へ至ります(運行本数は季節により変動するため最新の時刻を確認)。車なら国道55号から内陸へ入り、谷筋の道を進むルートが一般的。カーブが続く区間があるため、スピードは控えめに。境内周辺の駐車は誘導表示やマナーに従い、参拝者の動線をふさがないように停めましょう。雨天の翌日は路面が滑りやすく、落葉期は枯れ葉で足を取られることも。帰りのバス時間をあらかじめ押さえて行動計画に余裕を持たせると、慌てずに参拝・見学ができます。スマホの電波が弱い場所もあるため、地図は事前に保存しておくと安心です。
近くの立ち寄りスポット
加茂谷周辺は清流、棚田、里山の暮らしが色濃く残る地域です。地元の直売所では柑橘や山の幸が並び、季節の手づくり菓子や加工品に出会えることも。帰路に海辺へ出れば、紀伊水道の風と光で気分転換ができます。カフェや食堂は営業時間が短い場合があるため、事前確認と現金の用意を。写真好きなら、河岸段丘の俯瞰スポットや、石積みの棚田が美しい集落を合わせて回るのもおすすめです。地域の行事や田植え・収穫時期には、農作業の妨げにならない距離感を守り、私有地には立ち入らないのが鉄則。滝と社の静けさを楽しんだら、里の時間に合わせて「ゆっくり味わう」ことが旅の満足度を高めてくれます。
四季で変わる見どころ
春は新芽の柔らかな緑が滝の白と重なり、桜や山躑躅が彩りを添えます。初夏は苔が瑞々しく、長時間露光で“絹糸の滝”を表現する写真に最適。盛夏は水量が増して轟音が響き、日中の強い光でも水煙が立つ迫力の画が撮れます。秋は紅葉の赤と社殿の朱が呼応し、夕刻の斜光が差し込む時間帯が美しい。冬は落葉で視界が開け、澄んだ空気の中で滝の造形をくっきり楽しめます。いずれの季節も、増水時は展望所から安全第一で鑑賞すること。濡れた落葉や凍結の朝は特に足元注意です。気象アプリで雨量・気温をチェックし、無理と感じたら撤退する判断を。自然への敬意を払いながら、季節の変化を“ゆっくり観る”ことが名瀑を楽しむ最短ルートです。
阿波の「駈馬」と奉納文化をたどる
阿波市・浦庄に伝わる駈馬の記録
阿波国では、祭礼の余興ではなく“奉納”としての競馬=駈馬(かけうま)が各地で行われてきました。阿波市の浦庄地域にも、農閑期の神事として馬が社頭の馬場を駆け抜けた記録が残ります。氏子が紅白に分かれて競う形式や、宵宮に若者が手綱を取り観衆が見守る様子など、地域資料や古老の聞き書きに当時の空気感が活写されています。明治後期から昭和にかけて道路交通が自動車中心になると、馬の飼育環境や安全面の事情から途絶した例が多いものの、地名・古写真・神社の所蔵品を通じて文化の断片は各所に残存。現地に立つと、直線の参道や緩やかな勾配に“馬を走らせるための設計”が潜んでいることに気づきます。地域の聞き取りや資料展示に触れるのも、旅の学びを深める一歩です。
北島町・水神社の天井絵と競馬用具
板野郡北島町の水神社では、大正期ごろまで宵祭りに奉納競馬が行われていました。その痕跡として、拝殿の格天井に描かれていた競馬図など多数の天井絵と、鞍・鐙などの競馬用具が町の有形文化財として保存されています。天井絵は総計208枚の大部で、作者には地元の絵師・多田藍香(阿波の踊り歌で知られる多田小餘綾の父)と考えられる作品も含まれると伝わります。奉納競馬のスピード感、観衆の熱気、馬と若者の誇らしげな表情が克明に描かれ、単なる芸術作品を超えて“地域の記憶媒体”の役割を果たしています。社殿改築に伴って取り外された絵は現在保管・公開の体制が整えられつつあり、事前連絡で見学の可否が変わる場合も。見学時は撮影や接近に関する指示に必ず従いましょう。
三好・馬岡新田の伝承と大杉
三好市の馬岡新田神社は、その名に“馬”を冠する山里の鎮守。明治27年に現社名へ改称された経緯が伝わり、地域の発展とともに氏子の心の拠り所であり続けてきました。境内には幹周約6.1メートル、高さ約50メートルとされる見事な大杉がそびえ、長い年月を生きた樹木の気配が訪れる人を圧倒します。吉野川の流れと谷筋の暮らしに支えられたこの地では、農耕や運搬に馬が欠かせない時代が長く続き、社名や地名の由来にも馬への敬意が色濃く刻まれています。参拝時は根元の保護柵を越えない、樹皮に触れないなど最低限のマナーを守り、鳥や昆虫が棲む“生きた社叢”として静かに対話するのが良いでしょう。山間部ゆえに天候・路面状況の変化に注意し、余裕ある計画が安心です。
徳島に広がる馬の神事の系譜
阿波の馬文化を俯瞰すると、城下の助任八幡で行われた神事競馬、北島町の水神社での奉納競馬、海辺の地区に残る競馬図の天井絵など、各地の事例が連なって見えてきます。京都・大和平野で培われた祈雨・止雨の馬信仰が、日本列島を東西に横断する街道とともに伝播し、地域の祭礼に合わせて独自のスタイルへ変化した、と考えると理解しやすいでしょう。実馬の奉納や競馬が姿を消しても、馬像・絵馬・祭具・地名・口承といった“文化の痕跡”は層を成して残り続けます。徳島で馬をテーマに歩く旅は、こうした断片を拾い集めて一本の線にする作業。各社の由緒や地域資料を尊重しつつ、“断定を避け、伝わる事実として丁寧に紹介する”姿勢が、未来へ文化を手渡す第一歩になります。
写真撮影のコツと守りたいマナー
馬文化の痕跡は「直線の道」「馬場の名」「競馬図の絵」「馬像や石碑」に宿ります。広角レンズで通りの抜け感と空の余白を活かし、道の消失点に社殿や鳥居を置くとスッと時代の奥行きが出ます。天井絵や文化財はフラッシュを避け、許可なく接写しないこと。絵馬掛所は個人名や願いが映り込みやすいので、角度を変えたり、書かれた文字が判読できない距離を保つのが基本です。神事や祭礼では、係や宮司の指示がすべてに優先。音の出る連写や動画の長回しは控え、参拝の導線や視界をふさがない場所から撮影します。SNSに投稿する際は位置情報の扱いに注意し、私有地や保存脆弱な場所の拡散を避ける配慮も大切。写真は“文化を守り、魅力を伝える手段”であることを忘れずに。
午年・馬好きに効く!徳島開運旅プラン
徳島市内・半日で“馬”を感じるコース
所要3~4時間の半日コース。徳島駅からスタートし、まずは一宮神社で重文本殿と神馬像を拝観。境内では参拝を最優先に、建物の細部は人通りの少ない時間に。続いてバスまたはタクシーで下助任エリアへ移動し、八幡社周辺の“馬場筋”の面影を歩いて確かめます。史跡の案内板や古地図を参照すると理解が深まります。最後に津田八幡神社で勝運・道中安全を祈願し、徳島中央公園(城跡)で城下の地理を俯瞰して締め。絵馬は「いつまでに、何を達成するか」を具体化し、書いたら掛所へ丁寧に奉納。歩行距離はややあるので、履き慣れた靴と飲み物を忘れずに。公共交通の待ち時間は、地元の喫茶で小休止を。短時間でも“馬”の要点をぎゅっと味わえます。
午尾の滝でリフレッシュ日帰りプラン
自然と信仰をたっぷり浴びたいなら、午尾の滝を核にした日帰り。徳島駅→JRで阿南駅→路線バスで加茂谷へ。深瀬八幡神社に参拝し、滝は展望所から安全第一で観賞。増水・強風・雷の兆しがあれば滝壺方面へは近づかず、引き返す判断を。滝の霊域には水速女命を祀ると伝わるため、静けさを保ち、声量は抑え目に。帰路は里山の直売所や海辺の展望スポットに立ち寄り、夕景の海で一日の余韻を。公共交通の本数が少ない時間帯があるので、復路の時刻表を先に押さえるのが成功の秘訣です。写真は広角と望遠の両方が活躍。霧がかかる日や薄曇りの午後は、コントラストが落ちて滝の白が柔らかく浮き上がります。
西阿波・三好まで足をのばす1日周遊
車で機動力を高め、西阿波の山里へ。徳島市内から吉野川沿いを遡り、馬岡新田神社で大杉に手を合わせます。根元の保護柵や参道の石段は保存上の配慮が必要なので、ルールを守って拝観を。時間に余裕があれば、祖谷方面へ足を延ばして渓谷の絶景と古民家の風情に触れましょう。山間部は天候変化が激しいため、服装は重ね着で調整し、帰路のガソリンとライトの点検も忘れずに。道幅の狭い区間では対向車に配慮し、カーブミラーの前で一時停止するなど慎重な運転を。山里の鎮守と清流、木橋や石垣の景色が相まって、“時間が少しゆっくり流れる一日”が過ごせます。撮影は住民の生活を妨げないよう配慮し、私有地に踏み込まないのが最低限のマナーです。
御朱印&授与品で「馬」を集めるヒント
馬図や馬紋の授与品は、社ごとにモチーフや意匠が異なります。まずは授与所の掲示や公式発信で頒布状況を確認し、無理のない範囲で巡拝計画に組み込みましょう。絵馬は“旅のテーマを一枚にまとめるカード”と考えると楽しく、徳島では一宮神社の馬像を眺めてから「仕事運・飛躍」を、助任エリアでは「道中安全・学業成就」を、津田八幡では「勝運・厄除」を……と社の個性に合わせて書き分けるのもおすすめです。御朱印帳は一冊にまとめても、地域ごとに使い分けてもOK。混雑時は書置きをいただき、静かな時間に貼り付けるときれいに整います。授与品は“授かる”ものなので、丁寧な言葉遣いとお礼の一言を忘れずに。
ご当地グルメ&カフェでひと息
散策の合間は、徳島ラーメンやすだち料理、阿波尾鶏など地元の味でエネルギー補給を。神社の境内では飲食を控え、周辺の指定エリアや店舗で楽しみましょう。水分とミネラル補給はこまめに行い、夏場は塩タブレットが役立ちます。カフェでは旅のノートを開いて、今日の学びや気づきをメモ。写真のバックアップやバッテリーの補充もこの時間に。地元の人に「周辺で馬にまつわる場所はありますか?」と尋ねると、思わぬ小社や道の名が出てくることもあります。食は旅のハイライト。無理に詰め込まず、一食を丁寧に味わうことで体力回復と心の整理が同時に進み、次の一歩が軽くなります。
旅に役立つ早見表
| スポット | 特徴 | 所在 | メモ |
|---|---|---|---|
| 一宮神社 | 本殿は寛永7年(1630)建立・国指定重要文化財。拝殿前の神馬像は現地写真で広く確認 | 徳島市一宮町 | 参拝は社殿優先、像には触れない |
| 助任エリアの八幡社 | 神事競馬の記録が伝わる。直線道路“馬場筋”に痕跡 | 徳島市下助任町 | 生活道路のため安全最優先 |
| 深瀬八幡・午尾の滝 | 境内の名瀑。落差は約30m。滝は御神体とされ水速女命を祀ると伝わる | 阿南市加茂谷 | 増水時は展望所から安全鑑賞 |
| 北島町・水神社 | 競馬図を含む格天井絵208枚と競馬用具を町の文化財として保存 | 北島町鯛浜 | 見学は公開情報・指示に従う |
| 馬岡新田神社 | 明治27年改称の伝承。幹周約6.1m・高さ約50mの大杉 | 三好市 | 山間部は天候・路面に注意 |
まとめ
徳島を“馬(うま)・午”の視点で歩くと、重文本殿と神馬像の一宮、馬場筋の記憶が残る助任、滝を御神体とする深瀬八幡、競馬図を守り継ぐ北島、山里に威容を誇る大杉の馬岡新田――点のように見える場所が一本の線でつながります。絵馬は実馬奉納の代替から生まれ、雨乞い・豊穣・道中安全といった祈りを今に伝える媒体。だからこそ、願いは肯定形で具体的に。現地では“断定を避け、伝わる事実として丁寧に”という姿勢を持ち、文化財・自然・地域の暮らしに敬意を払って楽しみましょう。安全第一、静けさ最優先。そうすれば、阿波に息づく馬の記憶は、旅のあなたの中で確かな実感となって残ります。


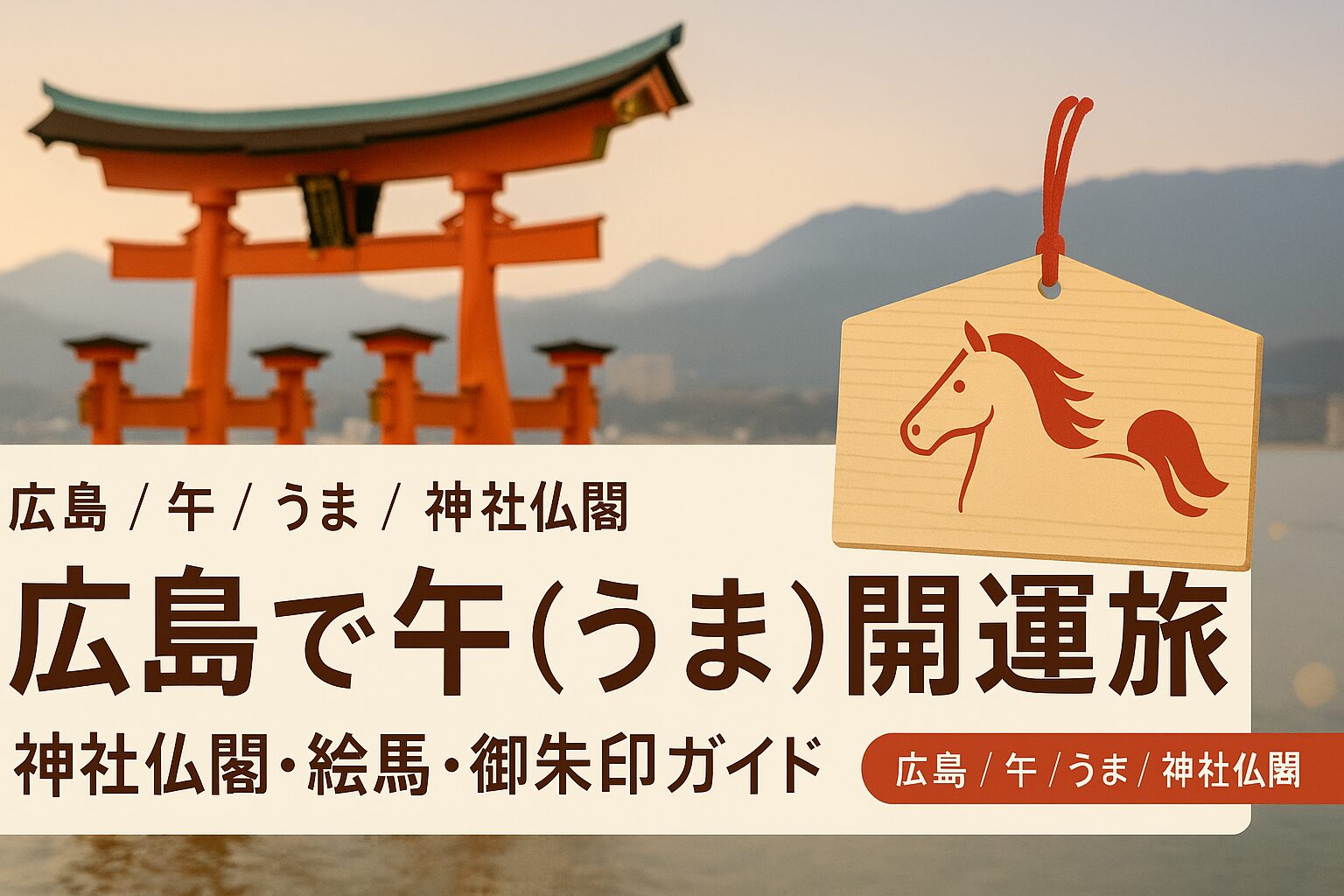

コメント