神社に馬がいる理由と基礎知識

「石川で“午(うま)”をめぐる旅」——それは、絵馬のルーツに触れ、神輿と神馬が形づくる春の行列を見送り、平安の馬頭観音と静かに向き合う体験です。金沢の御馬神社(みうま/みんま)から羽咋の豊財院、能登の氣多大社まで、由緒・回り方・マナーを一冊分の密度でまとめました。年により運営が変わる行事は必ず公式の最新情報で確認し、地域の暮らしに敬意を払って歩く——その姿勢さえあれば、初めてでも満ち足りた一日になります。
絵馬のはじまりと「馬」の関係
神社で願いを書いて奉納する「絵馬」は、実は“本物の馬”の代わりです。古くは雨乞い・止雨・五穀豊穣などの重要な祈りの場面で、白馬・黒馬などの神馬を献上しました。しかし生きた馬を何頭も用意するのは現実的に難しく、やがて木や土で作った馬像(「土馬」「木馬」)が奉納され、それが板に馬を描いた「絵馬」へと簡略化されていきました。現在は受験や安産、交通安全、病気平癒など、個人の願いを一枚に込めて掛けるのが一般的です。絵馬掛所は社殿近くにあることが多く、奉納前には必ず参拝を済ませるのが基本。奉納の向き(表を外側に)や掛ける位置が示されている場合は案内に従いましょう。由来を知ると、板一枚にも「馬を神さまに捧げる」という古い記憶が宿っていると感じられ、筆が自然と丁寧になります。
神馬と馬の像の意味
神馬(しんめ)は「神さまの御用馬」を指し、神輿とともに行列に加わる場合があります。境内に実際の馬を飼う社もあれば、象徴として馬の石像・銅像・木像を安置する社もあります。像は“神の乗り物が常駐する”しるしで、神がここに降り来ることを示す標識の役割も果たします。色は白馬が尊ばれますが決まりではありません。行事や祭礼で馬が参加する年もあれば、事情により不参加の年もあります。像の前で手を合わせる作法は一般の参拝と同様で、賽銭→二拝二拍手一拝が基本。写真に収めるときは周囲の参拝者の動きに気を配り、正中(参道の中心線)をふさがないよう立ち位置を選びます。馬は音や光に敏感なので、実馬がいる場面ではフラッシュ・連写音・無断接近をしないことが大切です。
「午(うま)年」と相性が良い参拝の考え方(守り本尊・勢至菩薩)
干支には仏教側の“守り本尊”という考えがあり、午年の守り本尊は勢至菩薩(せいしぼさつ)と伝えられています。勢至は「大いなる智慧の到来」を意味し、迷いを照らし出して進むべき道を示す存在として信仰されてきました。午年生まれの人はもちろん、進学・就職・独立など人生の分岐点にある人が、決断力や前進する力を願う対象として手を合わせるのにふさわしい菩薩です。神社で“馬”にちなむ社を巡り、寺院で勢至菩薩に知恵と気力の充足を願う——そんな神仏の合わせ方は、日本の暮らしに根づいた祈りの流儀に合っています。参拝はまず感謝を伝え、次に願意を簡潔に述べるのが基本。守り本尊のお札やお守りは、玄関や仕事机など“日々目に入る場所”に丁寧に安置すると心構えが整います。
写真撮影・参拝マナーの基本
神社仏閣は観光地である前に祈りの場です。鳥居の手前で一礼し、手水舎で手と口を清め、拝殿では賽銭→鈴→二拝二拍手一拝の順に。写真は「まず参拝、次に撮影」を守るとトラブルになりません。社によっては拝殿内・御垣内・宝物の撮影が禁止、商用利用や自撮り棒の使用不可など細則があります。掲示や公式案内の指示に従い、人物が写るときはプライバシーに配慮します。三脚は安全と動線確保の観点から制限されることが多く、混雑時は使用を避けるのが無難です。参道中央(正中)は神さまの通り道とされるため、立ち止まっての撮影は避け、端に寄る配慮を。お寺では大きな声の読経・木魚の使用が制限されることもあります。いずれの場でも、係の方の指示を最優先に、地域の生活を妨げない静かな行動を心がけましょう。
旅の持ち物チェックリスト(石川版)
石川は日本海側特有の変わりやすい天候が特徴です。まずレインジャケットや折りたたみ傘、防水の歩きやすい靴を基本装備にしましょう。春秋は薄手ダウンやフリースを重ね着に、冬は手袋・ニット帽・カイロが心強い味方です。参拝では小銭(5円・10円など)、朱印帳、黒の油性ペン(絵馬用)、ハンドタオル、ウェットティッシュ、モバイルバッテリーが実用的。境内で音が鳴らないよう、スマホはマナーモードに設定してから入ります。写真好きならレンズクロス、予備バッテリー、レインカバーも用意を。長時間歩く日は、両手が空く小さめのデイパックが便利です。季節の目安として、夏は日よけ帽子・日焼け止め・虫よけ、梅雨は滑りにくい靴底、冬は防滑タイプの靴を。飲食のゴミは必ず持ち帰り、境内では水分補給以外の飲食を控えるのが礼儀です。
金沢の「御馬(みうま/みんま)」を歩く:地名に残る“馬”の信仰
金沢・久安の御馬神社(読み:みうま)—由緒・御祭神・アクセス
金沢市久安に鎮まる御馬神社は、『延喜式神名帳』に記される「御馬神社」の比定社とされる古い伝承を持つ小社です。主祭神は保食神(うけもちのかみ)で、天照大神・応神天皇を配祀します。地域の稲荷信仰と結びついた歴史があり、社頭では素朴ながら端正な雰囲気が漂います。所在地は金沢市久安1-178。兼務の社務は波自加彌神社が担っており、授与・祭事の案内も同社経由で示されることがあります。住宅街の中にあり、車なら近くのコインパーキング利用が現実的。公共交通は金沢駅周辺からのバスと徒歩の組み合わせで到達できます。境内は地域の方の祈りの場であることを意識し、朝夕の静かな時間帯は特に行儀よく。拝殿前の石段や狭い通路での長時間の三脚設置は避け、手短に撮影を済ませると気持ちよく参拝できます。
金沢・間明町の御馬神社(読み:みんま)—由緒・御祭神・アクセス
金沢市間明町の御馬神社は、「みんま」と読みます。こちらも『延喜式神名帳』所載の御馬神社の比定社とされ、主祭神は保食神、高皇産霊命(たかみむすびのみこと)、菅原道真公を配祀します。昭和期の区画整理に合わせて社殿や鳥居、手水舎、神馬像などが整えられ、生活圏に密着した氏神として親しまれています。所在地は金沢市間明町1-85。春日神社が兼務し、行事の告知や問い合わせ先も春日神社の社務所となるのが通例です。最寄りの「間明」バス停から徒歩圏で、車でも訪ねやすい立地。通学路に面するため、平日昼間は車の出入りや子どもの動線に特に配慮しましょう。参道は狭めなので、正面からの記念撮影は短時間で。地域の方が掃除をされていることも多く、挨拶を交わしつつ、邪魔にならない距離感を大切に歩くと良い雰囲気で回れます。
2社の違いと共通点(歴史・地域との関わり)
二つの御馬神社は読みが「みうま」「みんま」と異なるものの、どちらも“御馬”の社号を持ち、『延喜式神名帳』の御馬神社の比定社とされる点が共通です。久安の社は稲荷とのつながりが強く、食と産業を守る性格が色濃い一方、間明は学問や創造の象徴である菅原道真を配祀し、地域の子どもたちの成長や学業成就の祈りが集まるのが特徴。両社とも近代に合祀や社殿整備を重ね、町の変化の中で祈りの場を守ってきました。研究上は「どちらを式内社に比定するか」に複数説が並立しますが、信仰は“地域の現在”に根づいて続いています。参拝の実感としては、久安は静謐で端正、間明は暮らしに溶け込む温かさが印象的。どちらも小ぶりな境内なので、歩く足音や会話の音量に配慮し、境内の案内板に従って丁寧に過ごすことが大切です。
| 項目 | 御馬神社(久安・みうま) | 御馬神社(間明・みんま) |
|---|---|---|
| 住所 | 金沢市久安1-178 | 金沢市間明町1-85 |
| 主な祭神 | 保食神・天照大神・応神天皇 | 保食神・高皇産霊命・菅原道真 |
| 位置づけ | 『延喜式神名帳』御馬神社の比定社とされる | 同左 |
| 管理 | 波自加彌神社が兼務 | 春日神社が兼務 |
| 雰囲気 | 静謐・端正 | 生活圏に溶け込む温かさ |
御朱印や授与品のポイント
小規模な氏神では、常時の授与体制が取られていないこともあります。御朱印や授与品が必要な場合は、久安は波自加彌神社、間明は春日神社の社務所に事前確認をしてから訪ねると確実です。無人のときは、扉や鈴をむやみに触れず、拝礼のみで静かに立ち去るのが礼儀。御朱印は“参拝の記録”であり、収集そのものが目的にならないよう、まず本殿で手を合わせてからお願いしましょう。授与品は身につける位置が示されているもの(交通安全=車内・バッグ内など)は案内に従います。写真撮影では、氏子の方や近隣の生活の邪魔にならないことを第一に。絵馬は願いを一つに絞り、主語を自分にして、読みやすい文字で。叶ったら「お礼参り」を忘れない——この一往復が、地域の神さまとの関係をやわらかく育てます。
周辺で立ち寄りたいスポットと移動術
久安と間明は車で10分ほどの距離感で、市バスもこまめに走っています。午前に久安、昼食をはさんで午後に間明という回り方が効率的。合間に地元のパン屋や喫茶でひと休みすると、境内の余韻がほどよく整います。雨天は足元が滑りやすい場所があるので、防水シューズと替えの靴下を用意すると快適。バスを利用する場合は最新の時刻表を確認し、帰路の便を先に決めてから行動するのがコツです。写真目的なら、久安は朝のやわらかな光、間明は夕方の斜光が石の陰影を美しく見せます。混雑を避けたい人は、休日の昼前後を外すだけでも印象が変わります。周辺の大型神社や金沢中心部の観光地と組み合わせると、半日から一日で“祈りも観光も”バランスよく楽しめます。
仏教で「うま」に縁ある尊格を知る
午年の守り本尊は勢至菩薩
勢至菩薩は阿弥陀如来の右脇侍として観音菩薩とともに阿弥陀三尊を形成し、智慧の光で衆生の進む道を照らす菩薩と説かれます。干支守護の民間信仰では午年の守り本尊とされ、受験や就職、方針転換など“前へ進む決断”の場面で心の支えになります。参拝の仕方に難しい決まりはなく、まずは合掌して日常の感謝を述べ、落ち着いた呼吸で願いを静かに言葉にします。寺院によっては勢至像や御札、梵字(種子)をあしらった護符の授与があり、身近な場所に祀ると心が整います。写経やお念仏と合わせた祈りも古くから行われてきました。神社で“馬”にちなむ社にご縁を結び、寺院で勢至に知恵と集中力を願う——この二本立ては、旅の記憶を「観光」から「学び」へと確かなものにしてくれます。
馬頭観音とは?旅や家畜を守る観音
馬頭観音(ばとうかんのん)は観音菩薩の変化身の一つで、怒りの表情(忿怒相)に馬の頭部を戴く独特の尊格です。古くは馬をはじめとする家畜守護、道中安全、悪縁断ちの祈りを集め、街道沿いの石仏や寺院の秘仏として広く信仰されました。忿怒の相は「迷いや災いを断ち切る決意」の表れであり、慈悲の心はそのままに、厳しさの力で守護すると理解されます。能登・加賀の各地でも馬頭観音の石塔や堂宇が見られ、地域の暮らしと移動を長く見守ってきました。参拝では合掌して静かに礼をし、写真撮影は寺の指示に従います。石仏は風雨に晒されて傷みやすいので、触れたり、粉や水をかける行為は厳禁。供花や清掃などの奉仕をする場合は、必ず管理者に相談してから行いましょう。
羽咋市・豊財院の国重文「木造馬頭観音立像」を拝む
羽咋市の豊財院(ぶざいいん)には、平安時代の作と伝わる木造馬頭観音立像が伝来し、国指定重要文化財となっています。像高は約173.7センチ、檜の一木造、彫眼、白毫は水晶。宝冠正面に彫り出された馬頭と、耳の後ろに並ぶ忿怒面が強い存在感を放ち、全体はおおらかな量感と静かな緊張を合わせ持ちます。像は寺宝であり、公開形態は時期や状況によって変わります。拝観を希望する場合は、最新の公開情報や予約の要否を事前に確認しましょう。堂内は暗いことが多く、撮影可否や照明の扱いに厳格な決まりがあるため、許可がない限り撮影は控えるのが安心です。鑑賞のコツは、正面で全体を受け止めてから、斜め45度で量感を、側面で衣文の流れを見る三段階。細部に“刃の冴え”を感じたら、平安の息づかいを追体験できます。
お経や真言の唱え方(初めてでもできる手順)
寺で声を出すのが初めてでも、難しく考える必要はありません。合掌して背筋を伸ばし、息を静かに整えます。最初に日頃の感謝を一言述べ、次に願いを簡潔に。読経や真言は小さな声で、言葉を一つずつ置く気持ちで唱えると心が乱れません。となえる文句は寺の案内に従い、勝手なアレンジはしないこと。数よりも「途切れず落ち着いた呼吸」を大切にします。念珠の使い方が分からなければ無理に回さず、合掌だけで十分。堂内では私語を慎み、席の譲り合いを。香炉や蝋燭の扱いは係の指示に従い、火気の取扱いに細心の注意を払いましょう。終わりに一礼し、扉を静かに閉める。わずかな所作の積み重ねが、祈りの深さそのものになります。
お寺での礼儀と心構え
本堂に上がる前に帽子を取り、スマホはマナーモードに設定します。土足禁止の案内があれば靴を揃えて脱ぎ、荷物は通路をふさがない場所へ。拝観順路がある場合は逆走せず、撮影禁止の札があれば従います。僧侶や参拝者の導線をふさがず、椅子席があるときは席を譲り合いましょう。御朱印は“信仰の証”であり、スタンプラリーではありません。まず仏前に手を合わせ、落ち着いた所作で受付へ。わからない点は無理に推測せず、係の方に尋ねるのが最も丁寧です。寺宝や文化財は地域の共有財産ですから、触れない・近づきすぎないが鉄則。香水や整髪料の強い香りは控えると、周囲への配慮になります。静けさと清潔感を帯びた時間は、旅の疲れを確かに癒やしてくれるはずです。
能登の春を駆ける神輿と神馬:氣多大社「おいで祭(平国祭)」入門
祭の成り立ちと見どころ
能登国一之宮・氣多大社の重儀「平国祭(へいこくさい)」は、羽咋の大社から七尾側の気多本宮へ神輿が渡御する大規模な神幸祭で、地元では親しみを込めて「おいで祭」と呼ばれています。大国主神と少彦名命の物語を背景に、神輿・神馬・奉仕者が列をなし、沿道の人々が迎え送る姿は能登の春の風物詩です。行列が通る地域は年により変わることがあり、区間の調整や神事の簡略化が行われる場合もあります。日中だけでなく早朝や夕刻の儀式もあり、土地ごとに受け継がれた所作が息づいています。華やかな装束や太鼓の響きだけでなく、神輿が止まって静かに祝詞が奏される瞬間の緊張感も見どころ。写真を撮る人は、まず邪魔にならない位置を確保してから、儀式そのものを味わう心構えを持つと満足度が高まります。
開催時期の基本(通例と2025年の実施)
平国祭は通例では毎年3月18日から23日までの6日間にわたり執り行われます。ただし直近の令和7年(2025年)は事情により日程が短縮され、3月18日〜21日の4日間で執行されました。巡幸は公式の案内で「2市2町」を巡るとされ、行程距離は「約300km」という表現が用いられます。年や資料によっては自治体数の表現に揺れが見られますが、参加を検討するときはその年の公式告知に合わせるのが確実です。天候や地域の状況によっても運営は変わるため、事前に氣多大社および関係自治体の最新情報を確認し、現地の案内に従いましょう。早朝から動く日もあるので、防寒・防水・歩ける靴は必須装備。特に海沿いは風が強い日が多く、体感温度が下がるため重ね着で調節できる服装が安心です。
行程ハイライト(羽咋→七尾・気多本宮)
行列は羽咋市の氣多大社を発ち、能登路を北上して七尾市所口町の気多本宮(能登生国玉比古神社)に向かいます。往路では中能登町金丸の宿那彦神像石神社に宿泊し、翌日に少彦名命が神輿に同座するという古い作法が伝わっています(年により変更・中止の可能性あり)。気多本宮での神事を終えると、道筋の地域で祈りと祝意を受けながら帰途につき、羽咋の大社へ還御します。要所では神楽や太鼓が鳴り、地区ごとに受け継がれた迎え方が彩りを添えます。巡幸の中で「祈りが道をつなぐ」感覚を味わいたいなら、発輿の朝と要所の停止点に合わせて先回りするのがコツ。移動は余裕を持って計画し、車で追う場合は交通規制や通行の妨げにならない駐車を徹底しましょう。
行列に加わる神馬の役割と見学の注意
平国祭の行列には神馬が加わる年があり、神輿とともに巡幸の列を形作ります。神馬は“神が乗るための馬”という象徴で、儀礼に緊張感を与え、行列のリズムを整える存在です。ただし「どの位置を歩くか」「どの区間に参加するか」は年によって変わることがあり、先頭を切って進むと断定できるわけではありません。見学者は、馬の進路をふさがないこと、フラッシュを焚かないこと、係員の指示に必ず従うことを徹底します。近年は地域の団体や学生が馬の世話や装具の管理に協力する年もありますが、役割分担は運営判断で変わります。小さな子ども連れは、急な接近を避けるために列から十分に距離を取り、歩道の内側で鑑賞を。馬の足元は滑りやすい場面があるため、濡れた路面や砂地では絶対に駆け寄らないよう注意しましょう。
見学のコツ(混雑回避・服装・安全マナー)
混雑を避けたいなら、出発点や終着点の“始まる30分前”に着いて静かに待つのが最も確実です。行列は止まってから動き出すまでに時間差があるため、早足で追いかけるより要所に先回りする方が楽に楽しめます。服装は重ね着で体温調節し、耐水性のある靴を。風が強い日は帽子や手袋が役に立ちます。写真は望遠寄りで背景に人の列が入らない位置を探し、儀式中はシャッター音を控えめに。神輿や神馬の正面をふさがないこと、私有地に立ち入らないこと、沿道の生活と交通を妨げないことが最低限のマナーです。トイレは事前に済ませ、出たゴミは必ず持ち帰りましょう。最新の行程はその年の公式告知で必ず確認し、天候や地域の事情で予定の変更が発生したら現地の指示に従うのが安全です。
モデルコース&フォトスポット
【金沢 半日】久安と間明の御馬神社をめぐる
午前は静けさの残る久安の御馬神社へ。鳥居で一礼し、手水で清め、拝殿で心を整えます。境内は小ぶりなので、社殿全景は少し引いて撮ると収まりが良く、石造物は斜光で陰影が際立ちます。近隣で昼食をとったら、午後は間明の御馬神社へ移動。「間明」バス停から歩ける距離なので、公共交通と徒歩の相性が良いルートです。こちらは生活圏に溶け込む雰囲気で、長居をせず静かに参拝を。二社の距離は近いので、天候に合わせて順番を入れ替えても大丈夫。帰路は金沢中心部へ戻り、喫茶で一息つけば半日でも満足度は十分です。絵馬を奉納したい場合は、願いを一つに絞り、主語を“私”にして、肯定形・現在形で端的に書くのがコツ。叶ったら後日、お礼参りを忘れずに。
【能登 1日】豊財院の馬頭観音 → 氣多大社
朝は羽咋市の豊財院へ。国指定重要文化財・木造馬頭観音立像は公開形態が変わるため、事前確認をしてから向かいます。拝観では堂内の暗さに目を慣らし、正面→斜め→側面と視点を移すと量感と表情の変化がよく分かります。昼食後は氣多大社へ。鬱蒼とした社叢の空気に身を置き、拝殿で静かに合掌。時期が合えば「おいで祭」の関連行事に触れられることもあります。車なら海沿いの道で千里浜方面に回り、海風で頭をリセットしてから帰路へ。公共交通の場合は本数に余裕がない時間帯もあるので、往復の便を先に確保しておくと安心です。写真は本殿の屋根飾りや神門の細部も魅力。神事に遭遇した場合は、撮影よりもまず参列の妨げにならない立ち位置を最優先にしましょう。
神社の馬像・神馬を美しく撮るコツ
馬像を撮るときは“目と耳”に表情が宿ります。目の高さにレンズを下げ、背景がゴチャつかない角度を探します。石像は朝夕の斜光で陰影が深まり、45度の斜め前から狙うと立体感が出ます。望遠寄りにすると背景が整理され、像の存在感が際立ちます。実馬がいる場面では、まず安全第一。係の指示に従い、フラッシュ・連写音をオフにして、距離を取りつつ“気配”を切り取る意識で。鳥居や社殿は水平・垂直を丁寧に合わせ、参道の奥行きは手前に余白を残すと荘厳さが高まります。構図に迷ったら「主役(馬像)・相棒(社殿)・余白(空や参道)」の三要素を整えるだけで安定します。雨の日は石の濡れ色が深く、コントラストが増すので、レンズにかかる水滴だけ丁寧に拭き取りましょう。
願いが届きやすくなる「絵馬」の書き方
まず願いは一つに絞ります。主語は自分、文体は肯定形・現在形で短く。「第一志望に合格しました。ありがとうございます。」のように“叶った形”で書くと、行動が“叶った自分”に寄っていきます。氏名はフルネームでなくても構いませんが、取り違えを避けるためにイニシャルや居住地の市区町村などを添える人もいます。文字は丁寧に、雨天時は油性ペンで。奉納位置が指定されていれば案内に従い、掛け終えたら合掌して一礼。願いが成就したら必ずお礼参りをし、可能ならお礼の絵馬を奉納します。写真を撮る際は個人情報が写り込まないよう配慮を。絵馬は飾りではなく「神さまとの約束のメモ」。書いた後の行動(勉強時間を増やす、生活を整えるなど)までセットにすると、旅が日常の背中を押してくれます。
季節別の楽しみ方(梅雨・夏・紅葉・雪景色)
梅雨は苔や石畳がしっとりと深い色を見せる季節。レインウェアと滑りにくい靴底で足元の安全を確保し、透明な傘なら被写体を覆わずに済みます。夏は朝夕の参拝が涼しく、木陰で風を受けながら社殿の細部を観察する余裕が生まれます。紅葉の頃は逆光で葉を透かすと、屋根飾りや懸魚の彫りが浮き立ちます。冬は雪化粧の鳥居や狛犬が特別な表情に。路面凍結に注意し、防滑靴と手袋、ポケットカイロを。通年で、地域の暮らしと祈りに敬意を払うことが何より大切です。ゴミは必ず持ち帰り、神域での大声や飲食は控えめに。天候で計画を柔軟に調整できるよう、代替案(屋内の資料館や寺宝拝観など)を用意しておくと、どの季節でも満足度の高い行程になります。
まとめ
石川には、馬にまつわる信仰と物語が今も脈々と続いています。金沢の二つの御馬神社は、『延喜式神名帳』の御馬神社の比定社とされる伝承を現在へとつなぎ、地域の日常の祈りを支えています。羽咋の豊財院には、平安の息づかいをいまに伝える国指定重要文化財の馬頭観音が静かに佇み、能登の春には氣多大社の平国祭(おいで祭)が神輿と神馬、奉仕者の列で道と人の心を結びます。絵馬の由来や参拝・撮影の作法を押さえ、年ごとの最新情報を確認しつつていねいに歩けば、旅は確実に豊かになります。次の休日は、石川で“午(うま)”と人が紡いできた祈りの時間に身を委ねてみませんか。



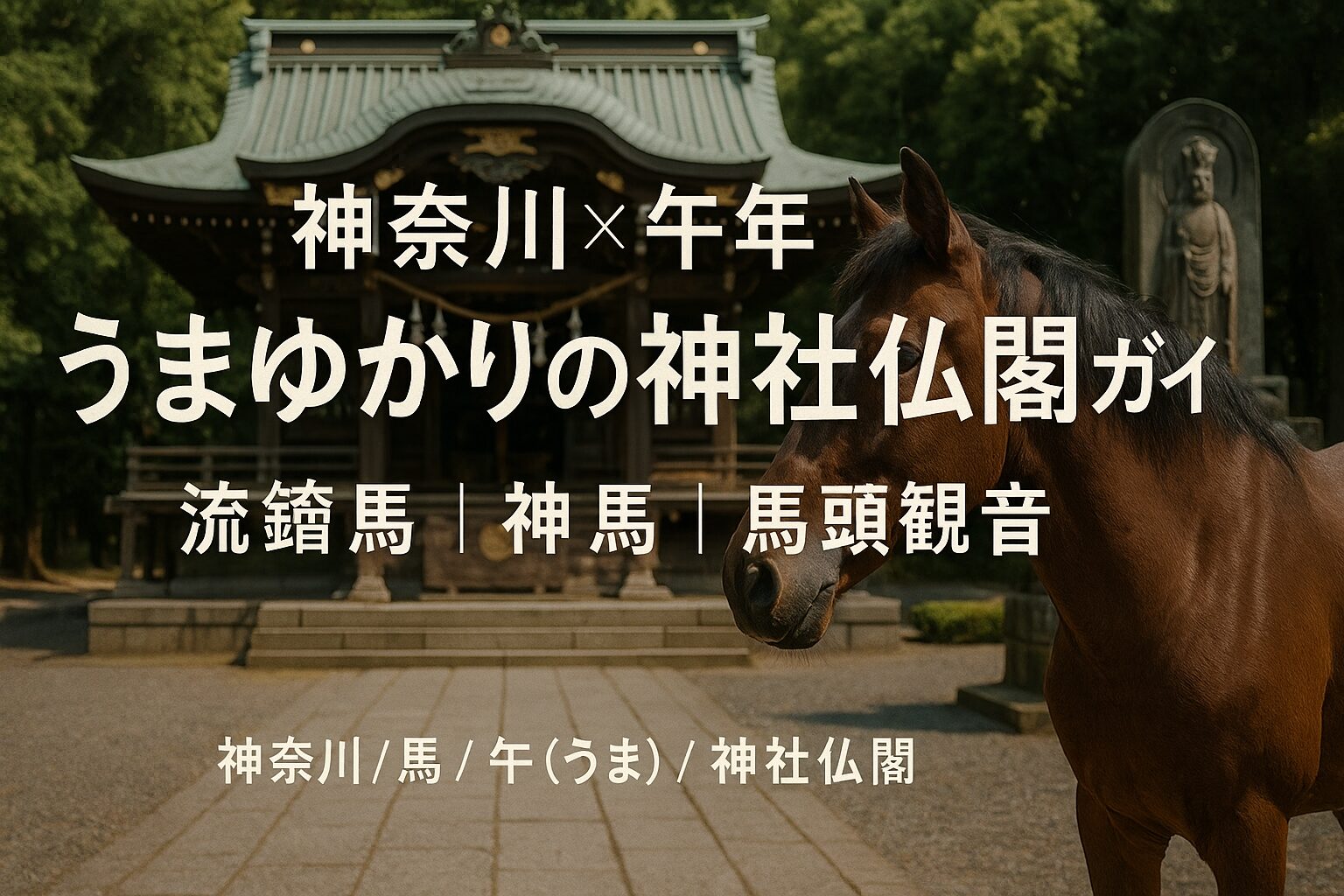
コメント