2026年は丙午!“午(うま)”の基礎と日本の信仰入門
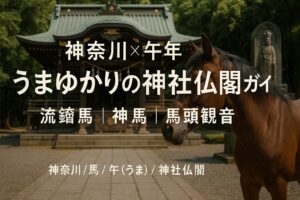
「馬は神さまの乗り物」。この言葉を知ると、神社の絵馬や境内の白馬像が急に身近になります。お寺では、怒りの表情で災いを断ち切る“馬頭観音”が、旅や動物を静かに見守っています。鎌倉の流鏑馬、寒川の例祭、平塚の神馬、厚木の観音さま、箱根の駒ヶ岳――神奈川には、午年に歩きたい“馬ゆかり”がぎゅっと詰まっています。本記事は、由来の基礎から参拝マナー、見どころ、モデルプランまで一気にわかる保存版。家族での小さな遠足にも、じっくり学ぶ一人旅にも、きっと役立つはずです。
干支“午”と60年に一度の丙午(ひのえうま)って何?
十二支の“午”は、十干と組み合わせると60通りの干支が生まれます。その中でも丙午は60年に一度。直近では1966年で、次が2026年です。十干の「丙」も十二支の「午」も五行では“火”に当たり、勢い・発展・情熱の象徴と説明されます。かつては迷信が話題になったこともありますが、現代では「節目の年」「新しい挑戦に向く年」と前向きに捉える人が増えています。干支の考え方は、年中行事や暦の見方、寺社の授与品デザインにも反映されるため、旅の計画づくりにも役立ちます。2026年を機に、馬に関わる神事・美術・言葉を学ぶと、普段見慣れた絵馬や神社の馬像がぐっと立体的に感じられるはず。干支の基礎だけ押さえておけば難解さはありません。「十二支は方角・時間・月にも配置がある」「干支は暦法の記号」と理解すれば、旅先の案内板も読みやすくなります。
神社にいる“神馬(しんめ)”と絵馬の由来をやさしく解説
“神馬”は神さまに奉仕する馬のこと。古くは雨乞いには黒馬、止雨には白馬を奉るなど、馬を通じて天候や実りを祈る風習が各地に伝わりました。やがて生きた馬の代わりに木馬や土馬が供えられ、さらに板に馬の絵を描いた「絵馬」へと移り変わります。現在は本物の馬を常時飼う神社は少ないものの、神馬舎の白馬像や馬のレリーフ、馬房を持つ社など、名残を多く見られます。参拝時は、馬がいる場合でも“静かに見る・柵を越えない・無断で餌を与えない”が基本。絵馬は願いを書き入れて奉納するのが一般的ですが、個人情報が気になる場合はイニシャルや図案に置き換えても構いません。馬は祈りを“運ぶ存在”として尊ばれてきました。社殿の装飾や境内の案内板を意識して眺めると、馬が担ってきた役割の豊かさがわかります。
お寺の“馬頭観音(ばとうかんのん)”とは?ご利益と特徴
馬頭観音は六観音の一尊で、忿怒相(怒りの表情)で表されるのが最大の特徴です。怒りは“害を断ち切る強い慈悲”の表れで、動物界を含むあらゆる苦しみを救う姿と説かれます。日本では中世以降、旅の安全や家畜守護の信仰として広まり、街道や峠、村境に石塔が多く建てられました。道端の石仏に「馬頭」「馬頭観音」「馬頭尊」などの銘が刻まれていれば、それが目印です。ご利益は無病息災・災難除け・道中安全・畜類供養など。礼拝の作法は観音さまと同様で、手を合わせて静かに祈れば十分です。寺院では堂内に本尊として安置される例もありますが、路傍にある石仏は地域で守られてきた民間信仰の証し。写真撮影は周囲の迷惑にならない範囲で行い、私有地や畑の中にある場合は立ち入らないのがマナーです。
日本の“流鏑馬(やぶさめ)”神事の意味と見方
流鏑馬は、疾走する馬上から三つの的を射抜き、五穀豊穣・天下泰平・悪疫退散を祈る神事です。鎌倉以来の歴史を持ち、作法には流派の違いがあります。代表的には小笠原流や武田流など。進行は修祓、奉献、所作の披露、試走、本走と続き、馬場沿いには三つの的が立ちます。見どころは、駆け抜ける瞬間の矢音、射手の掛け声、射的が決まったときの“カン”という的の響き。安全のため馬場周辺は規制が入り、観覧位置や撮影可否が細かく定められることがあります。行事は天候や社務の都合で時間変更や中止もありうるため、出発前に公式の最新案内を確認しましょう。席取りのコツは“早めに到着して、視界を遮らない場所を確保すること”。家族連れは、馬の急接近や大きな音に驚くことがあるので、耳栓や抱っこ紐などの準備も有効です。
参拝&観覧マナー:安全・撮影・御朱印のポイント
神社参拝の基本は「鳥居で一礼→手水で清める→拝殿で二拝二拍手一拝」。お寺では合掌して静かに礼拝します。行事観覧では、柵に登る、機材で場所を過度に占有する、大声での指示無視といった行為は厳禁。フラッシュや自撮り棒が禁止される場合もあります。SNS投稿は、写り込みへの配慮と場所のルール遵守が前提。御朱印は行事時間帯に授与休止・整理券制となることがあるので、早めに受けるか、混雑の少ない時間帯に。絵馬や守札は必要数のみを授かり、転売目的の購入は控えます。馬や動物が登場する行事では、給餌禁止・接触禁止の掲示を必ず守りましょう。最後に、式年で時間が変わる・天候で中止になる等は珍しくありません。「現地掲示と公式発表が最優先」という姿勢で動けば、気持ちよく参加できます。
“馬”に強い神奈川の神社5選(アクセスと見どころ)
鎌倉・鶴岡八幡宮:例大祭で行われる流鏑馬神事が圧巻(毎年9/14–16の行事内)
鎌倉の総鎮守・鶴岡八幡宮は、源頼朝ゆかりの名社。毎年9月14〜16日に例大祭が営まれ、最終日に流鏑馬神事が行われる年が多く、近年は午後早い時間帯の開始が案内されることがあります。進行や観覧区分、開始時刻は年度で変更がありうるため、必ず公式発表を確認しましょう。馬場は段葛の東側に沿って設けられ、三つの的が並びます。射手の一射ごとに的が鳴り、歓声が上がる瞬間は何度見ても胸が高鳴ります。鎌倉駅から徒歩圏で、混雑回避には早めの到着と公共交通の利用が鉄則。境内の舞殿や社殿の意匠にも、馬に関わる歴史が読み取れるので、行事の日以外でも学びの多い社です。
相模國一之宮・寒川神社:例祭前日の流鏑馬(例年9/19 14:00)
全国でも珍しい“八方除”の守護神として知られる寒川神社では、例祭(9月20日)の前日に流鏑馬が奉納されるのが通例で、例年は9月19日14:00開始の案内が出ます。進行は年ごとに一部異なることがありますが、馬場沿いを駆け抜ける一射の迫力は格別。流派名は公式で強調されない年もありますが、一般向けの案内では武田流の奉仕として紹介されることが多い行事です。最寄りはJR相模線「宮山」駅。広い参道と清浄な境内は散策にも向き、授与品に“方位除・八方除”の特色が表れています。行事当日は動線が一部制限されるので、撮影や移動は係員の指示に従いましょう。
平塚八幡宮:神馬「皐月」「東風」に会える社(奉仕時間の目安あり)
平塚八幡宮は、境内の神厩で神馬「皐月」「東風(こち)」が奉仕することで知られています。お勤めの時間帯はおおむね午前・午後に分かれて案内されますが、体調や行事で変更されることもあるため、現地掲示や公式情報の確認が安心です。給餌やフラッシュ撮影は禁止。神馬の前では静かに過ごし、子ども連れの場合は大声を控えて近づき過ぎないよう見守りましょう。社殿周辺には七社めぐりのコースがあり、境内の緑も豊か。駅から徒歩圏でアクセスが良く、家族での参拝にも向きます。馬にちなんだ絵馬や守札は、午年の記念にも人気です。
大和市・左馬神社:左馬頭義朝を祀る“左馬”の名社
大和市には“左馬神社”の社名を持つお社があり、由緒では源義朝(左馬頭)への崇敬が伝わります。“左馬”の文字は縁起字としても親しまれ、商売繁盛や勝運上昇の象徴とされてきました。境内は大規模ではないものの地域に根差し、季節の祭礼や清掃奉仕など、地元の手で清らかに保たれています。参拝の際は、鳥居前で一礼、境内では私語を慎み、社殿前で感謝と祈願を。授与所が開いている時間が限られる場合があるので、事前に時間帯を確認して訪れるとスムーズです。地名の由来や社名の読み方を学ぶと、地図に残る“馬文化”の影が見えてきます。
箱根神社(元宮)と“駒形権現”の伝承:駒ヶ岳に息づく“駒”の名を辿る
箱根では、駒ヶ岳の山岳信仰と箱根神社の歴史の中に“駒(馬)”の名が色濃く残ります。芦ノ湖南岸の箱根神社と、駒ヶ岳山頂に鎮座する元宮(箱根元宮)。古くは「駒形権現」という呼び名が史料に見え、山の神を“駒”に見立てて敬ったとも解釈されます。湖畔の社殿で参拝し、天候が許せば山頂の元宮へ足をのばすと、山岳信仰の荘厳さが体感できます。強風や霧が出やすいエリアなので、天気と運行情報の確認は必須。“駒”の名が付く地形・地名を手がかりに歩くと、馬と暮らしの結びつきが見えてきます。単独の「駒形神社」が箱根にあると断定するのではなく、箱根神社と駒ヶ岳の信仰史の中で“駒形権現”の呼称を学ぶ、という視点が安全で深い理解につながります。
お寺や路傍で出会う“馬の仏さま”スポットと学び方
厚木・七沢観音寺:本尊は馬頭観世音。愛馬供養に始まる縁起
七沢温泉の山あいに佇む観音寺は、本尊が馬頭観世音。寺伝には、武将の愛馬供養に端を発する縁起が伝わり、動物守護や交通安全の祈りがいまも息づいています。境内は素朴で落ち着いており、参道を吹き抜ける風まで穏やか。動物と暮らす人が祈りに訪れることも多く、ペット供養の相談窓口が設けられる時期もあります。観音堂前では、まず静かに一礼してから合掌。周辺は温泉とハイキングの拠点でもあるため、参拝と癒やしを同時に楽しめるのが魅力です。授与所の開所日や行事予定は季節によって変わることがあるので、出かける前に最新情報を確認しましょう。馬頭観音の忿怒相に戸惑う人もいますが、怒りは“害を断ち切る力強い慈悲”の表れ。手を合わせると、不思議と背筋が伸びます。
鎌倉・山ノ内界隈の馬頭観音石塔を歩いて探す(散策ヒント)
鎌倉は路傍の石仏が豊富で、山ノ内(北鎌倉・明月院周辺)には馬頭観音・庚申塔・地蔵などの石塔が点在します。寺社の境内だけでなく、路地の角や古い道筋、宅地の端などにひっそりと立っていることも。刻銘に「馬頭」「奉納」「某年某月」などが見つかれば、建立の事情が想像できます。散策のコツは、通学路や古道の雰囲気を残す細道を選ぶこと。石塔は私有地にある場合もあるため、無断で立ち入らず、遠目から合掌するだけでも十分です。写真を撮るなら、人や車の通行を妨げない位置を選び、フラッシュは使いません。季節の花と石仏を一緒に眺めると、暮らしの中に信仰が根づいてきた時間の厚みが感じられます。
旧街道と馬頭観音の関係を知る(東海道・大山道など)
馬頭観音の石塔は、旧街道沿いに多いのが特徴です。物資や人を運ぶため、馬はかつての交通の主役でした。坂や峠、川の渡し場、村の境など、事故や疲労が出やすい場所には、旅の安全や家畜の無事を祈るための石塔が建てられました。神奈川県内でも、東海道や大山道など歴史ある街道筋にそうした例が見られます。道標と兼ねた石塔や、供養の趣旨を刻んだ銘文が残るものもあり、読み解くと地域の暮らしが伝わってきます。見学の際は、交通量の多い道路で無理に接近しないこと。草刈りや清掃を地元の方が続けている場所では、作業の邪魔にならないよう配慮を。旅程に街道歩きの短い区間を組み込むと、神社仏閣巡りだけでは見落としがちな“道の信仰”が体験できます。
石仏の鑑賞ポイント:図像・銘文・建立背景を読み解く
馬頭観音の図像には、頭上に馬の頭を載せる表現、三面六臂の姿、忿怒の表情など、地域や時代で差があります。石塔の場合は、磨耗で馬の頭が判別しづらいことも多いので、「馬頭」「観音」「供養」といった刻字を手がかりにします。台座や側面に刻まれた年号、奉納者名、願意(たとえば「道中安全」)が読めると、建立の背景が具体的に見えてきます。道端の石仏は“地域の共有財産”。苔を剥がす、拓本を取る、触れて動かすといった行為は厳禁です。合掌し、静かに立ち去るだけでも十分な礼拝になります。写真は遠景中心に。こうした作法を守るほど、地域の信頼を得て、より豊かな情報に出会えるようになります。
博物館・資料で学ぶ(横浜・根岸「馬の博物館」は整備のため休館中)
馬の歴史や馬具、馬文化の資料を体系的に学びたいなら、博物館や資料館の活用が近道です。横浜・根岸の「馬の博物館」は、競馬と馬文化の貴重な資料を所蔵しますが、現在は整備工事のため長期休館中で、再開は2029年頃の見込みと案内されています。開館状況は公式の最新情報を確認してください。休館中でも、書籍や自治体の文化財データベース、図書館の郷土資料コーナーは有用です。図録や解説書には、馬頭観音の図像や歴史的変遷、地域ごとの特色が写真つきで載っていることが多く、現地での見方が一気にわかります。事前に少し調べてから出かけると、石仏の小さな違いにも気づけるようになります。
祭り・行事で“うま”を体感(年間カレンダー)
鶴岡八幡宮の流鏑馬神事:観覧のコツと注意点(例大祭内)
鶴岡八幡宮の例大祭は毎年9月14〜16日。近年は最終日に流鏑馬が行われる年が多く、午後1時前後の開始が告知されることがあります。ただし、時刻や観覧エリア、整理券の有無は年度によって異なるため、必ず直近の公式情報を確認しましょう。コツは、駅到着から観覧位置確保までの動線を逆算すること。段葛のどちら側から入るか、帰りの混雑をどう避けるかも事前に決めておくと安心です。服装は歩きやすい靴、日よけ・雨具、モバイルバッテリーを基本装備に。撮影はフラッシュ禁止・三脚不可の場合があるので、軽量の望遠側のレンズが便利です。
寒川神社の流鏑馬神事:毎年9/19の14:00から(例年)
寒川神社の流鏑馬は、例祭(9月20日)の前日、9月19日14:00開始が通例です。一般参拝者は馬場沿いの観覧スペースから見学することになりますが、混雑時は入場制限がかかることも。日差しが強い時期なので、帽子と飲料は必携。流派名は公式で固定的に出さない年もありますが、一般の案内では武田流による奉納として紹介されることが多い行事です。行事後は、八方除の御祈祷や授与所に立ち寄る人で列が延びることがあります。滞在時間に余裕を持って計画しましょう。
平塚八幡宮:神馬の奉仕時間と関連の取り組み
平塚八幡宮では、神馬「皐月」「東風」が神厩で奉仕しています。お勤めの時間帯は午前・午後の二部制で案内されることが多いものの、体調や天候で変わるため、現地掲示を最優先に。場内は給餌禁止。写真を撮る場合も、フラッシュと大声は控えます。神馬を中心にファンの支援活動が行われることもあり、奉納の窓口が整えられているのが特徴です。動物が登場する場所では、子ども連れほど十分な距離を取り、急な動きに備えると安心して楽しめます。
横浜・根岸「馬の博物館」最新情報(休館中〜再開は2029年頃見込み)
根岸競馬記念公苑にある「馬の博物館」は、2024年から大規模整備のため休館中です。再開は2029年頃の見込みとされています。園内のポニーセンター等も整備対象に含まれ、段階的な開放が行われる場合があります。最新の開館情報やイベント予定は、必ず公式の告知を確認してください。再開後は、寺社巡りとあわせて訪れることで、神事・民俗・競馬史まで“馬の文化”を総合的に学べる拠点になります。
初めてでも安心:混雑回避・服装・持ち物チェックリスト
基本は「手ぶらに近い軽装+天候対策」。歩きやすい靴、レインウェアまたは折りたたみ傘、帽子、飲料、携帯食、モバイルバッテリー、現金少額、身分証をセットに。カメラは軽量を選び、望遠側に余裕があると無理な前傾をせず安全です。混雑ピークは開始30〜60分前。最寄り駅のトイレ位置を把握し、帰りのルートをあらかじめ決めておくと快適。御朱印は行事開始直前・直後を避けるとスムーズです。小さな子どもは耳栓やヘッドホンを用意すると、馬の足音や歓声に驚きにくくなります。最後に、体調不良を感じたら無理をしないこと。安全とマナーが何よりの優先事項です。
午年にめぐる“馬×神社仏閣”モデルプラン&地図
鎌倉コース:鶴岡八幡宮と“馬文化”を半日で味わう
鎌倉駅から段葛を歩いて鶴岡八幡宮へ。行事の日でなくても、境内の案内や社殿、舞殿の装飾に歴史が漂います。参拝後は小町通りで休憩し、山ノ内方面へゆるやかに移動。路傍石仏を探しながら北鎌倉駅に抜けると、鎌倉らしい“信仰と生活の距離感”が体験できます。所要はゆっくり回って半日。行事に重なる時期は、動線規制や拝観時間の変更があるため、必ず最新情報をチェック。荷物は最小限にして、参道では立ち止まり過ぎないのがスムーズです。
湘南コース:平塚八幡宮→寒川神社で“神馬と流鏑馬”を一日で
午前は平塚八幡宮で神馬に会い、静かな時間を楽しみます。お勤め時間の掲示を確認し、無理な接近は避けましょう。午後は相模線で寒川神社へ移動し、例祭期なら流鏑馬のタイミングに合わせて観覧。日差し対策と水分補給を徹底し、帰路は最寄り駅の混雑を避けるため時間差の移動を。絵馬や御朱印は、行事の前後を外すとスムーズです。馬を中心にした“動”と、社の静けさという“静”。一日で両方を体験できる、午年にぴったりの王道ルートです。
厚木コース:七沢観音寺と温泉で“癒やしと合掌”
本尊・馬頭観世音に手を合わせ、静かな境内で心を整えたら、近隣の温泉で体を休めます。山の空気は季節で表情が変わり、春は新緑、秋は紅葉が美しいエリア。歩きやすい靴と、温泉の入浴セットを忘れずに。帰り道は、地元の直売所や食堂で旬の味を。観音寺では動物守護の祈りが広く受け付けられることがあり、ペットと暮らす人にも心強い存在です。参拝と温泉を組み合わせると、心身ともに軽くなります。
箱根コース:箱根神社と山頂の元宮、“駒”の名を眺める半日
芦ノ湖北岸の社殿で参拝し、天候が安定していれば駒ヶ岳山頂の元宮へ。雲の流れが速い地域なので、風と視界に注意し、無理のない計画で動きます。湖畔散策や遊覧船、近隣の史跡と合わせれば、山と湖と信仰の関係が体験的に理解できます。“駒形権現”という呼び名が歴史資料に見えることを知っておくと、箱根の風景に“駒”のイメージが自然と重なります。午年の旅にふさわしい、凛とした時間が流れます。
御朱印&おみやげ:馬モチーフの探し方とマナー
馬にちなむ授与品は、絵馬、馬みくじ、馬頭観音守、馬蹄形のストラップなど、多彩です。期間限定や行事限定の授与もあるため、在庫や頒布時間を事前に確認すると安心。御朱印は“書き置き”の用意がある社も増えていますが、転売は厳禁。撮影は授与所の掲示に従い、列の流れを止めないよう配慮します。おみやげ選びは、旅の目的と合うものを一つ。飾る場所や使い道を決めてから授かると、家に帰ってからの満足度が高まります。午年らしく、馬の意匠が入った絵馬を一枚だけ丁寧に書き、願いを込めて奉納するのも素敵です。
まとめ
“午(うま)”は、神社では神馬や絵馬の文化に、お寺では馬頭観音の信仰に結びついて、日本の祈りの形を今に伝えています。神奈川は、鶴岡八幡宮の流鏑馬、寒川神社の例祭、平塚八幡宮の神馬、七沢観音寺の馬頭観音、箱根神社と駒ヶ岳の信仰史など、“馬”を軸にめぐれる地点がコンパクトに集まる恵まれた土地です。2026年の丙午は、歴史を学び、行事を体感し、手を合わせる――その全てを一度に楽しめる好機。安全とマナーを守り、現地の最新情報を確認しながら、あなたらしい“馬巡礼”を計画してみてください。旅の一歩一歩が、きっと心強いお守りになります。
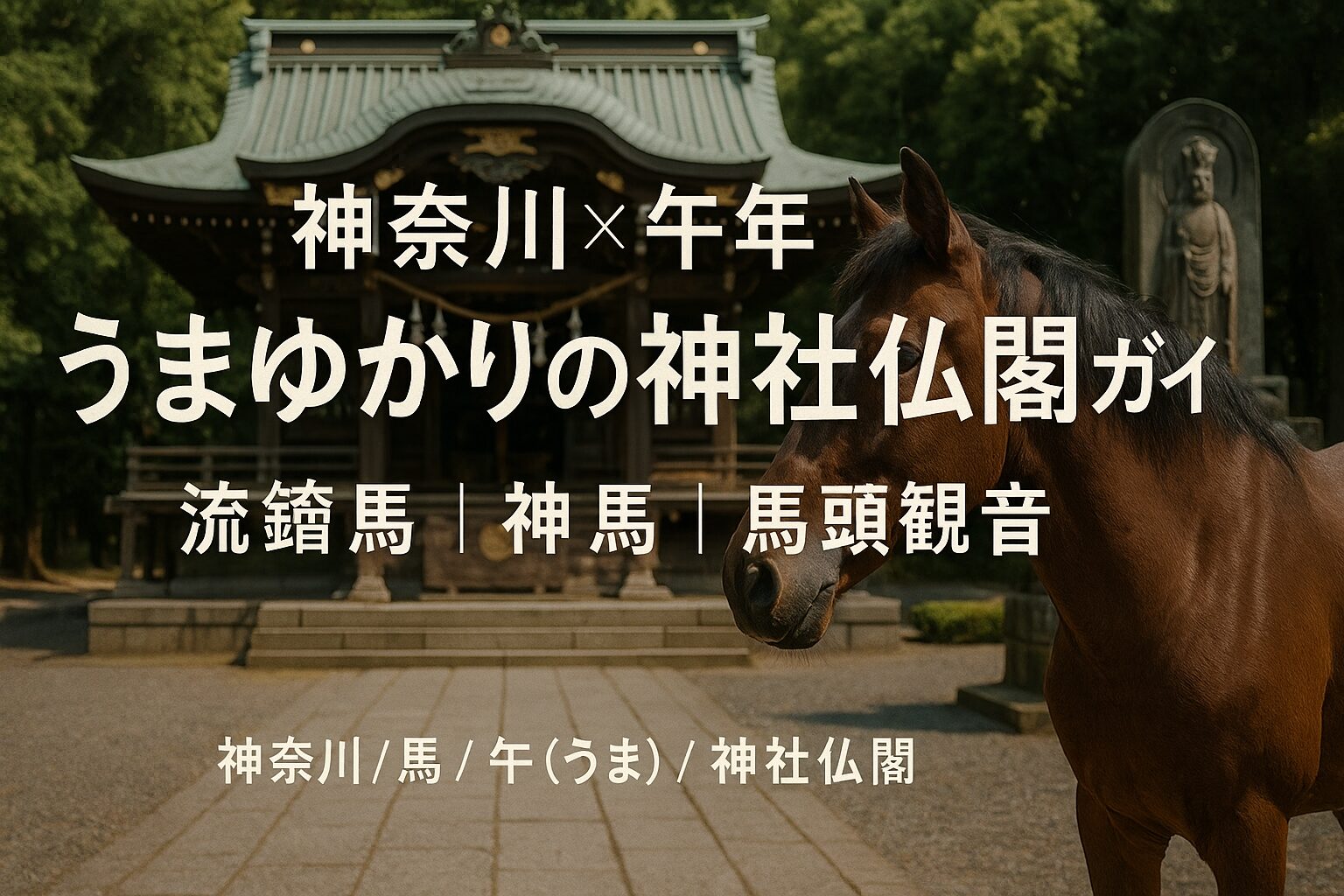



コメント