初めて蛇窪神社へ向かうとき、多くの人が迷うのは「何の神様が祀られているのか」「本当にご利益はあるのか」「どう回れば良いのか」の三点だ。本稿は、由緒や配置、参拝の流れや授与品の意味、巳・己巳の日の立ち回りまで、体験の順番で丁寧に整理した。特に「白蛇神符=継続所持推奨」という重要ポイントを明確にし、固定情報(名称・祭神・所在地など)と変動情報(混雑・頒布・導線など)を分けて説明している。白蛇の物語はロマンだけでなく生活を整える実用の知恵だ。祈りに小さな行動をひとつ重ねるだけで、参拝は現実の一歩に変わる。今日の一歩を決めて、静かに鳥居をくぐってほしい。

1. 蛇窪神社ってどんな場所?――歴史・場所・「何の神様」かをやさしく解説
1-1. 基本情報と行き方(最寄駅・参拝時間・混雑の目安)
蛇窪神社は正式名称を「天祖神社」といい、東京都品川区二葉四丁目に鎮座する地域の古社である。所在地は「東京都品川区二葉4-4-12」。最寄りは都営浅草線・東急大井町線「中延」駅(徒歩約5〜6分)、JR横須賀線「西大井」駅(徒歩約8分)、東急大井町線「戸越公園」駅(徒歩約12分)。都営浅草線のA3方面から商店街を抜けるルートは道標がわかりやすく、初めてでも迷いにくい。社務・授与所の対応は目安として9:00〜17:00だが、行事・季節・混雑状況で前後することがあるため、出発前に最新の公式案内を確認しておきたい。境内は住宅街に溶け込む落ち着いた空気で、檜の大鳥居と白蛇の意匠が訪れる人を迎える。混雑は正月三が日、12日に一度の「巳の日」、60日に一度の「己巳の日」に集中しやすい。待ち時間は天候や頒布内容で変動し、短時間で進む日もあれば長時間に及ぶ場合もある。整列や入場締切、導線の切替などは当日の掲示と係の指示が最終決定となるため、無理のない計画と体調管理(飲み物、雨具、モバイルバッテリー等の携行)を心がけたい。なお「深夜・早朝の整列はしない」「近隣への配慮を徹底する」といった基本ルールが示されることもあるので、マナーは厳守しよう。※社務時間は“目安”。必ず最新案内で確認すること。
1-2. 名称の由来と白蛇伝説――「蛇窪」の地名に秘められた物語
この一帯は江戸以前から「蛇窪村」と呼ばれ、蛇や龍神の物語が語り継がれてきた。干ばつの折に雨乞いが叶い、霊験に感謝して神霊を勧請したのが創祀と伝わる。社号は「天祖神社」だが、地域では古くから「蛇窪神社」の呼び名で親しまれてきた。令和元年(2019年)5月1日、この通称が表記上も明確化され、案内や授与品にも積極的に用いられている。白蛇は再生・清浄・財福の象徴として信仰され、弁財天・龍神への崇敬と重なって現代まで続いている。境内の白蛇像や白龍像、白蛇をあしらった授与品や案内板は、土地に根付いた記憶を視覚化したものだ。由緒は史料により表現差があるものの、「水の恵みに感謝し、再生と豊穣を祈る」という核が一貫している。参拝前に由緒掲示を一読すると、社殿や境内社の配置意図が理解しやすく、その後の回り方に迷いがなくなる。
1-3. 「何の神様?」主祭神と境内の神様(白蛇辨財天・蛇窪龍神・法密稲荷)
本殿の主祭神は天照大御神、配祀は天児屋根命・応神天皇。境内社には、財福・芸道・学問・弁舌を守護する「白蛇辨財天社」、水の気と“流れ”を象徴する「蛇窪龍神社」、稲荷信仰の「法密稲荷社」が鎮座している。蛇窪神社は「荏原七福神」巡拝では弁財天の札所にあたり、正月期には巡拝者で賑わう年もある。境内には七匹の白蛇像と全長約八メートルの白龍像が奉納され、昇りゆく力や再生のイメージを直感的に感じ取れる。初参拝の流れは、本殿→龍神社→辨財天社→稲荷社が理解しやすいが、繁忙日は導線が変更されることがあるため、順序はあくまで参考。最終的には当日の掲示・係の案内に従うこと。願いは一つに絞り、期限や数値を添えて言語化すると、後日の振り返りやお礼参りが実行しやすい。
1-4. 参拝の作法とまわり方:失敗しない順序と注意点
作法は難しくない。手水で身を清め、二礼二拍手一礼を基本に静かに祈る。社殿脇の「撫で白蛇」は、そっと手を添えて心を落ち着かせる象徴的な所作として親しまれている。白蛇清水での銭回し・銭洗いは現地の案内に従う。目安として、石臼の金杯を「時計回りに三回ゆっくり回す」→白蛇清水でお金をそっと清める、という流れが示されることが多いが、混雑時や特定日は衛生・安全面から運用が変更される場合がある(例:白蛇清水で神職が洗い清めた“白蛇種銭”のみ頒布に切替)。写真撮影は導線をふさがず、祈祷・授与所の撮影禁止表示に従い、他の参拝者のプライバシーにも配慮する。列の離脱・合流はトラブルのもとなので避けよう。順路・整列・入場締切など、その日の最終判断は当日の掲示・係の案内が最優先。本稿の回り方はあくまで参考と理解してほしい。
1-5. スペシャルデーの意味:巳の日・己巳の日の違いと楽しみ方
干支の「巳」は蛇を表し、弁財天と相性が良い日とされる。十二日に一度巡る「巳の日」と、六十日に一度巡る「己巳(つちのとみ)の日」があり、特に己巳の日は特別授与や行事が用意される場合がある。そのため参拝者が増え、行列が長くなる傾向があるが、実際の待ち時間は天候や頒布内容によって変動する。限定御朱印や特別授与が目的なら、朝の早い時間か午後のピーク後が現実的。参拝のみなら通常日を選ぶと落ち着いて回れる。年によって商店街イベントや露店が連動することもあるが、実施の有無はその年ごとの差が大きいため、直前の公式案内で確認しておきたい。状況によっては参拝規制や入場締切が告知される場合もあるので、無理のない計画で臨もう。
2. ご利益の正体を深掘り――スピリチュアル視点と現実的効果
2-1. 金運・財運はなぜ「白蛇」と相性がいいのか
白蛇は古くから財福・豊穣・知恵の象徴とされ、弁財天の眷属として描かれることも多い。蛇は脱皮を繰り返して成長する生き物であり、古い殻を脱いで新しい自分へ移るイメージは、停滞した財布や家計、仕事の惰性を整える比喩として実感しやすい。蛇窪神社では白蛇辨財天への祈り、白蛇清水の銭洗い、白蛇種銭の授与など、祈りを行動に落とし込む体験がそろっている。金運は偶然の一発逆転ではなく、日々の使い方と片づけ方の改善で体感が育つ。まず、財布を軽くし、レシートや不要カードを整理する。固定費を一つ見直す。収支の記録を「巳の日だけでも」つける。こうした小さな実践が祈願の“受け皿”を広げ、結果として金運の実感につながる。巳の日ごとに「今日は○○をやめる/始める」を一行で宣言し、次回見直すだけでも循環が良くなる。
2-2. 心身清浄・浄化の体感ポイント(境内スポット解説)
浄化を体感する順序は、まず本殿で姿勢と呼吸を整え、今日取り組む一つの課題を心の中で言葉にする。社殿脇の撫で白蛇で手を添え、気持ちを静める。蛇窪龍神社で“流れ”を整え、白蛇清水へ進み、掲示に従って銭洗い・銭回しを行う。ここでは手に触れる水の冷たさ、ざるに当たる水音、深い呼吸に意識を向けると、頭のざわつきが少しずつ静まっていく。最後に白蛇辨財天社で願いを一つだけ具体化して締めると、心身の澱が抜けたような軽さを持ち帰りやすい。繁忙日は導線・順番が変更されることがあるため、当日の掲示と係の案内を最優先にすること。静かな歩調と小さな声を意識するだけで、短時間でも“整う”感覚は得られる。
2-3. 立身出世・自己成長のご縁を呼ぶ考え方
境内に奉納された七匹の白蛇像と全長約八メートルの白龍像は、“段階的に昇る力”の象徴でもある。出世運に引っ張られると肩書だけを追いがちだが、ここでは“器を広げる”ことに焦点を当てたい。三か月で身につけたい技能を一つ、誰にどう貢献するかを一行で書き、参拝時に心で宣言する。次の巳の日に振り返り、半歩でも進んでいれば十分だ。進めないときは、目標が大きすぎるか、期限が曖昧になっていることが多い。週単位に細分化し、二十分でできる一歩に分解すると前進の実感が生まれる。外から運を持ってくる感覚より、自分の中の流れを整える感覚を養うことが、結果として評価や役割の拡大につながっていく。
2-4. 良縁・芸事・商売繁盛と弁財天の関係
弁財天は財福に加え、音楽・芸術・学問・話術など“表現する力”の守護として知られる。蛇窪神社は荏原七福神の弁財天札所でもあり、創作や舞台、営業や接客といった“伝える仕事”と相性が良い。良縁祈願なら、相手に求める条件を並べるより、自分が与えられることを一つ決めるのが近道だ。商売なら「今月、既存客の課題を三件解決」「次の発表は三日前に完成」など、期限と数値を添えた宣言が効く。参拝後、一時間だけ“仕上げ”に集中する習慣をつくれば、祈りが行動に変換され、成果に結びつきやすい。伝える力の向上と祈りをセットで運用することが、弁財天のご縁を受け取りやすくする。
2-5. 体験型の祈り方:銭回し・銭洗い・撫で白蛇・夢巳札のやり方
基本の巡りは、本殿での挨拶→撫で白蛇→蛇窪龍神→白蛇辨財天。白蛇清水での銭回し・銭洗いは現地掲示に従い、目安として「石臼の金杯を時計回りに三回ゆっくり回す→白蛇清水でお金を清める」という所作が案内されることが多い。混雑時は衛生・安全面から、白蛇清水で神職が洗い清めた“白蛇種銭”の授与に切り替わる場合がある。夢巳札は天然記念物「岩国のしろへび」の脱皮を納めた授与品で、正月期や巳・己巳の日を中心に授与されることが多いが、年により日程や方法は変更・延長される。授かったものは、財布や名刺入れ、毎日触れるポーチなどに納め、巳の日に数分の“感謝の見直し”を行うと意識づけが進む。順路や導線は当日の掲示・係の案内が最優先で、本稿の手順は“参考の回り方”として扱ってほしい。
3. お守り・授与品カタログ――初めてでも迷わない選び方
3-1. 白蛇神符・白蛇守:清めとご縁を呼ぶ定番(白蛇神符は継続所持推奨)
初めて授かるなら、白蛇神符や白蛇守がわかりやすい選択肢になる。ただし大切な違いがある。蛇窪神社の「白蛇神符」は、神社の公式方針として「一年経ってもお焚き上げせず、そのまま持ち続ける」ことが推奨される特別な授与品である。一方、一般的な守袋などは“おおむね一年を目安に感謝して納め直す”運用が広く行われる。つまり「白蛇神符=継続所持」「守袋系=年次の納め直しが多い」という違いを理解して選ぼう。置き場所は、財布・定期入れ・名刺入れ・毎日触れるポーチやデスクの引き出しなど、日々視界に入るところが良い。迎えた当日は、部屋の掃除や財布の整理をセットにすると、清浄の象徴としての意味が生活の整頓とつながり、体感がはっきりする。授与所で受け取る瞬間に心の中で目的をひとこと添えると、意識の切り替えが起きやすい。
3-2. 金運系:種銭・財運守・銭洗いアイテムの活用術(銭つなぎの作法も)
金運を意識するなら、白蛇種銭を中心に据えると運用がシンプルになる。参考手順として、種銭は新札と重ねて札入れへ。巳の日を“財布の棚卸し日”と決め、レシートや不要カードを整理する。臨時収入があったら一部を貯蓄や寄付に回し、循環の意識を育てる。銭洗い用のざるや布は現地に用意されている場合が多いが、混雑や衛生配慮で手順が簡略化されることもある。財運守は名刺入れや手帳と相性が良い。名刺を清潔に整え、約束の時間を守り、返信を早めるといった丁寧な行動とセットで使うと効果を実感しやすい。さらに覚えておきたいのが「銭つなぎ」。一定の節目(収穫があった時期や年末年始、次の己巳など)にお礼参りを行い、授与所の納め棒に種銭を結んで“循環を返す”所作をしてから、新しい種銭をいただく流れを意識すると、金運=循環の感覚が腑に落ちる。金運は“物”より“扱い方”に反応する。小さな整えを続けることが最短の近道だ。
3-3. 健康・厄除け:再生を象徴する「脱皮」のメタファー
健康や厄除けを願う人は、蛇の「脱皮」を生活に置き換えると続けやすい。夢巳札のように「岩国のしろへび」の脱皮を納めた授与品は、再生の象徴を手元で意識させてくれる。祈りだけで体調が自動的に変わるわけではないが、やめる習慣・始める習慣を一つずつ決めるだけで流れが変わる。就寝一時間前にスマホを置く、夕食時間を一定にする、週二回は一駅歩くなど、小さな脱皮で十分だ。厄除けでは、参拝の前後三日間を“静かな時間”に設定し、夜更かしを避け、通知を整理し、部屋を片づける。お札やお守りの納め方、返納・お焚き上げの受付は時期で運用が変わる場合があるため、当日の掲示と公式案内に従うこと。体調に不安があるときは医療機関の判断を優先し、参拝は心を整える補助として取り入れるのが健全だ。
3-4. 仕事運・学業成就:目標設定とお礼参りのコツ
仕事や学業の願いは、宣言と振り返りのサイクルに落とすと実現率が上がる。期限と数値を添えた一文を作り、参拝時に心で読み上げ、紙に書いて財布にしまう。「今月は既存顧客の課題を三件解決」「次の試験までに過去問三周」などが良い。達成できたら必ずお礼参りをし、次の目標を一つだけ掲げ直す。弁財天は“伝える力”の守護でもあるため、プレゼンや演奏の前に深呼吸をし、声を整える儀式を一つ決めておくと緊張が和らぐ。名刺入れに財運守を忍ばせ、商談前に名刺を整える――この小さな丁寧さが自分の気持ちを整え、結果として信頼を得やすくする。成果が出にくいときは、目標を週単位に細分化し、二十分でできる一歩に落とすのがコツだ。
3-5. 御朱印の楽しみ方:季節・限定・己巳の日のチェックリスト
蛇窪神社の御朱印は季節や行事で意匠が変わり、切り絵作家のデザインが採用されることもある。己巳の日など特定日は特別版の頒布や整理券配布が行われることがあり、混雑が予想される。狙いの図柄があるなら、直近の頒布方法・数量・受付時間を公式で確認しておこう。繁忙日は午前に列が伸びやすいが、午後に波が引く日もある。参拝が主、授与は従という意識で、まず手を合わせてから授与所へ向かうと、全体の体験が締まる。書置きか直書きか、数量限定かどうかは日によって変わるため、当日の掲示に従うのが安全だ。御朱印は“旅の記録”であると同時に“祈りの記録”でもある。焦らず、心の動きを一行メモするだけで、冊子が自分だけの成長ログに変わる。
4. 不思議体験・口コミ集――“感じたこと”を上手に受け取る
4-1. 白蛇を感じた瞬間の話:夢・サイン・偶然の一致
「白蛇の夢を見た」「参拝の帰りに白い羽根を拾った」「銭洗い直後に良い知らせが届いた」――そんな声は少なくない。無理に霊験と断じる必要はないが、自分がどう感じ、何を行動に変えるかを決めると前に進みやすい。夢巳札の由来にならい、参拝後一週間だけ夢日記をつけると、願いの芯や繰り返す不安のパターンが浮き上がる。サインを感じたら、次の巳の日までに「名刺の整理」「提案書の改訂」「家計簿の更新」など二十分で終わる一歩に落とす。体験は人と比べるものではない。静かに続けるほど、出来事の意味は自分の生活に根を下ろしていく。
4-2. 参拝後の変化:臨時収入・人間関係・心の軽さの声
参拝後の変化は人それぞれだ。臨時収入がすぐ入る人もいれば、数週間かけて人間関係が整う人、心の重さがふっと軽くなる人もいる。共通しているのは、祈りに日常の工夫をひとつ結びつけている点である。財布の整理、部屋の掃除、早寝、即レス、朝の散歩――小さな行動が意思決定の速さに直結し、良い流れを生む。弁財天の文脈から、プレゼンや面談の成功談も多いが、その裏には準備の丁寧さがある。成果が見えにくいときは、目標が大きすぎるか、期日が曖昧なことが多い。巳の日ごとにチェック表を作り、できたことに丸を付けるだけでも視点が「足りない」から「進んだ」へ切り替わる。焦らず、静かな積み重ねを続けよう。
4-3. 己巳の日の熱気:行列、神楽、商店街イベントの臨場感
己巳の日は参拝者が増え、境内は独特の熱気に包まれる。限定御朱印や特別授与がある場合は朝から列が伸び、状況によっては参拝規制や入場締切が告知される。こうした日は整列場所や動線が通常と変わる可能性が高いので、当日の掲示と係の案内を必ず確認しよう。待ち時間に備えて飲み物、帽子、雨具、モバイルバッテリーを用意し、体調管理を最優先にする。地域の商店街で限定メニューやイベントが行われる年もあり、行列の合間に軽食でエネルギー補給をする人が多い。写真撮影は周囲の導線を妨げないよう心掛け、プライバシーに配慮する。混雑が苦手な人は、朝一番かピーク後の時間帯を選ぶのが現実的だ。
4-4. スピリチュアルとの向き合い方:思い込みを整える習慣
ご利益の有無を短期で判定しようとすると、できていない点ばかりに目が向き、心が荒れがちになる。おすすめは、願いを小さく言語化し、期限を付け、巳の日に振り返る習慣に落とすこと。できた部分に丸を付け、できなかった部分は更に細かく分けて次回に回す。白蛇の“脱皮”になぞらえ、古い習慣を一つ脱ぎ、新しい習慣を一つ迎えるだけでも、心の軽さが違う。他人の霊験談は参考にとどめ、自分の生活に合う方法だけ取り入れる。参拝は“行動のスイッチ”を押す場であり、スピリチュアルは日常の工夫とセットにしてこそ実感に変わる。
4-5. Q&A:よくある疑問(何回行けばいい?タイミングは?)
Q. どのくらいの頻度で行けばよいか。
A. 回数に決まりはない。巳の日を“見直し日”として月一にする、季節の節目に合わせるなど、無理のない頻度が続きやすい。
Q. ベストな時間帯はいつか。
A. 己巳や特別頒布日は朝から混みやすい。参拝のみなら通常日の午前や、ピーク後の時間帯が落ち着くことが多い。
Q. 写真撮影は可能か。
A. 参拝や授与の妨げにならず、禁止表示がある場所では控える。プライバシーにも配慮する。
Q. 何の神様が祀られているのか。
A. 本殿は天照大御神、配祀に天児屋根命・応神天皇。境内社は白蛇辨財天社・蛇窪龍神社・法密稲荷社。
Q. 白蛇の観覧はできるのか。
A. 巳の日などに公開される場合があるが、天候や安全面で変更・中止されることもある。実施の有無は当日の掲示・公式発信を確認する。
5. 実用モデルコース&周辺スポット――“運が動く”半日プラン
5-1. さくっと60分:初参拝ショートコース
中延駅から参道を歩き、到着したら手水で清める。まず本殿で“来られた感謝”と“今日の一歩”を心で言葉にする。社殿脇の撫で白蛇で気持ちを整え、蛇窪龍神社に進んで一礼。白蛇辨財天社では願いを一つだけ具体化して伝える。授与所で白蛇守や神符を受けたら、近隣の商店街で短い休憩を取り、ノートに三行だけ感想と次の予定を書く。短時間でも、挨拶→整える→具体化→記録という参拝の骨組みを体に入れられる。混雑時は整列ルールが設けられるため、案内に従って静かに移動する。参拝だけ先に済ませ、授与は人の波が落ち着く時間に回すのも現実的だ。順路や導線は当日の掲示・係の案内が最優先であることを忘れない。
5-2. じっくり120分:体験スポット総なめコース
最初の三十分で本殿・撫で白蛇・龍神社を巡り、白蛇清水へ。掲示に従い銭洗いを行い、清潔な布で軽く拭く。混雑時は白蛇清水で洗い清めた種銭の授与に切り替わる場合があるので、その運用に従う。乾かしている間にノートへ“今日やる一歩”を一行記す。続いて白蛇辨財天社で祈願し、夢巳札などの授与有無を確認する。後半四十分は御朱印受付へ。数量や整理券のルールは日ごとに変わるため、当日の掲示に合わせて動く。残りの時間で商店街を散策し、軽食でエネルギー補給。最後に近隣の公園で深呼吸して気持ちを整え、帰路に就く。二時間の中に“整える・体験する・記録する・余韻を味わう”を全部入れるのが狙いだ。
5-3. 撮影&マナー:映えるポイントと禁止事項
写真映えの定番は、大鳥居の遠近、連なる社殿、白龍像と白蛇像、御朱印の意匠。人物を入れるなら導線をふさがない端から短時間で。祈祷所や授与所は撮影禁止表示が出ることがあるため、必ず従う。己巳の日は背景に他の参拝者が入りやすいので、プライバシーに配慮し、顔が判別できる写真の公開は控えるか了承を得る。フラッシュは基本不要で、シャッター音も最小限に。雨天時は足元が滑りやすいので注意する。写真は“記録”であり、主役は“祈る時間”という原点を忘れない姿勢が、場の雰囲気を守るいちばんの近道だ。
5-4. 商店街&ご当地グルメ:白蛇モチーフのおすすめ
参道周辺には昔ながらの商店街が続き、和菓子や惣菜、喫茶の小さな名店が点在する。白蛇モチーフの菓子や縁起の良い名前の品を見つけたら、銭洗い後の“お礼のおやつ”にしても楽しい。長い列に備える日は、こまめな水分補給と軽食が体力温存に直結する。待ち時間を使って財布やノートを見直し、今日の気づきを数行メモすれば、参拝の余韻が生活の改善へ変わる。イベントや限定メニューは年によって異なるため、現地の掲示や店頭案内の確認を。食べ歩きは導線を妨げない場所を選び、ゴミは所定の場所へ。近隣への配慮が、次に来る人の体験を守る。
5-5. 荏原七福神や近隣社寺と合わせて巡るルート提案
七福神巡りが好きなら、蛇窪神社(弁財天)を起点に、徒歩圏や沿線の寺社を組み合わせると充実する。交通の結節が多く、JR・私鉄・地下鉄の乗換えがしやすいのも利点だ。コース作りのコツは、歩く→参拝→休憩のリズムを一定にし、撮影は要点だけに絞ること。歩数計で“巳の日の歩数”を記録すれば、体調管理の指標にもなる。複数社寺を回るときも、願いはどこか一か所で一つに定め、他は感謝の挨拶に徹する。帰宅後、御朱印のページに学びを一行書き添え、次の訪問日を決めておくと、巡拝が自然に続く。
アクセス早見表
| 出発駅 | ルート | 所要目安 | 降車後の目印 |
|---|---|---|---|
| 中延(都営浅草線/東急大井町線) | A3方面から商店街を直進 | 徒歩約5–6分 | 檜の大鳥居 |
| 西大井(JR横須賀線) | 東口から住宅街を抜ける | 徒歩約8分 | 白蛇モチーフの案内 |
| 戸越公園(東急大井町線) | 駅前から北へ直進し住宅街へ | 徒歩約12分 | 参道の案内板 |
住所:東京都品川区二葉4-4-12
社務・授与所の目安:9:00〜17:00(季節・行事により変更あり。最新の公式案内を必ず確認)
※授与所・祈祷の受付時間、整列ルール、頒布内容・数量は日によって変更される場合があります。順路や導線は当日の掲示・係の案内が最優先です。白蛇の観覧は実施日・時間が事前告知される場合がありますが、天候や安全面により変更・中止されることがあります。
まとめ
蛇窪神社(正式名:天祖神社)は、白蛇と龍の象徴を通じて、金運・良縁・芸事・学業・再生など現代の願いに寄り添う体験型の神社だ。主祭神は天照大御神、境内社に白蛇辨財天社・蛇窪龍神社・法密稲荷社を配し、荏原七福神の弁財天札所でもある。白蛇清水の銭洗い、白蛇種銭、夢巳札、白龍と白蛇像、切り絵御朱印など、祈りを行動へ結びつける仕掛けが多い。特に「白蛇神符」は一年で納め直さず継続所持を推奨する点を正しく理解したい。混雑や運用は日ごとに変わるため、当日の掲示・公式発信が最終情報となる。大切なのは“祈り+行動”の両輪。巳の日ごとに小さな改善を一つ積み上げ、白蛇の脱皮にならって古い殻を一枚ずつ脱いでいけば、生活の巡りは静かに、しかし確実に整っていく。
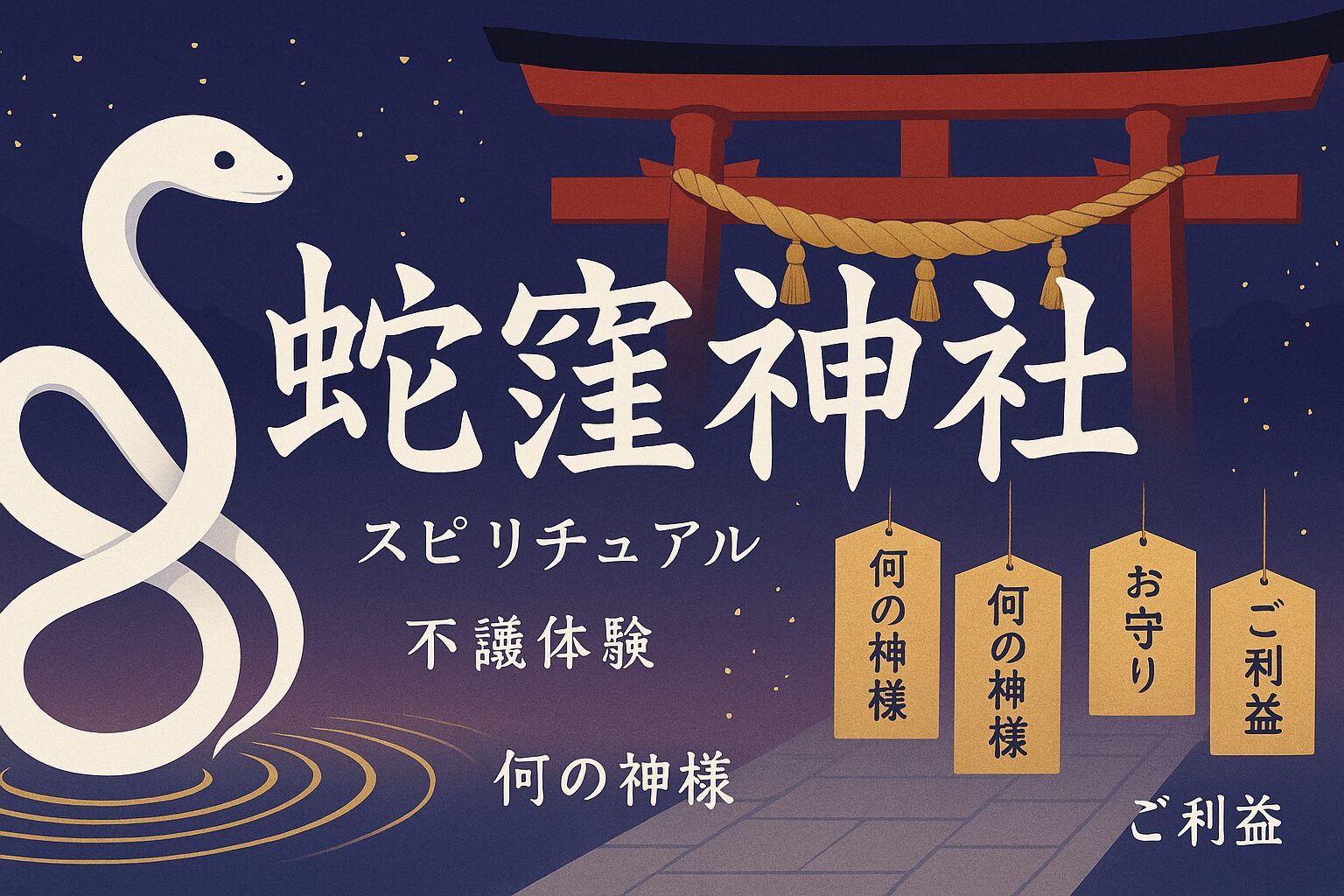

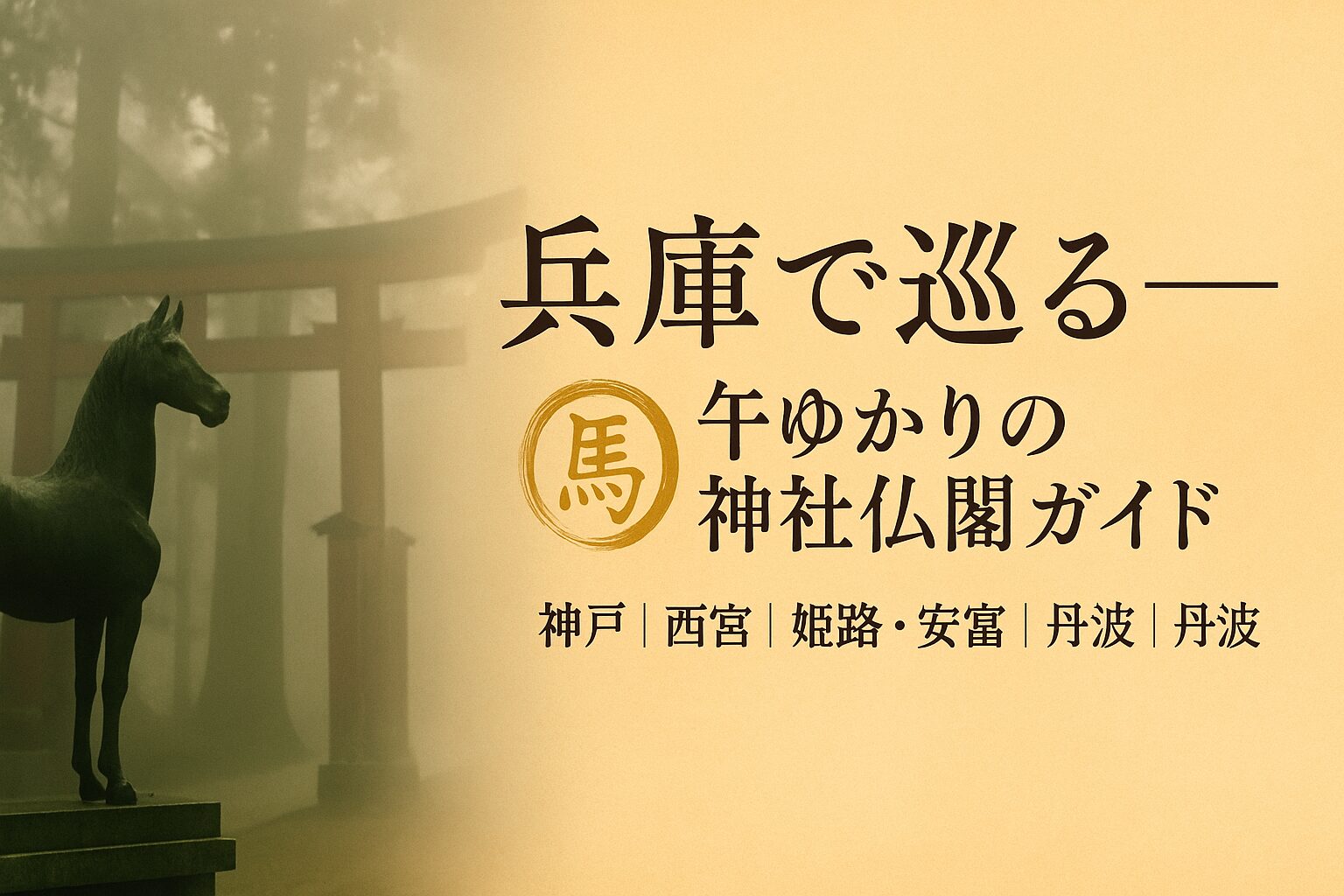

コメント