① 茨城×「うま」文化の基礎知識

「馬が好き」「午年にあわせて運を上げたい」「家族の交通安全を祈りたい」。その願いに応える場所が、茨城には数多くあります。本記事は、勝負運で知られる大杉神社(勝馬神社)、歴史が香る駒形神社、馬頭観音の古像や石仏、そして馬の名を残す古墳と地名まで、やさしい作法と実用的な旅のコツをそえて案内する保存版ガイドです。写真の撮り方、持ち物、モデルコース、家族で楽しむ自由研究プランまで、すべて一冊に。読みながら、そのまま旅の計画が立てられます。
午年の縁起と意味
十二支の「午(うま)」は、方角では南、時刻では正午ごろを示します。太陽が高くのぼり勢いが満ちるイメージから、物事の成長や前進を象徴すると語られてきました。干支は十干十二支の組合せで60年を一巡し、次の午年は2026年です。節目に合わせて新しい挑戦を始めたり、これまでの努力を結果につなげる“仕上げ”の年として意識すると、日々の行動が前向きになります。カレンダーでは「午の刻(うまのこく)」が昼の区切りで、ここから「午前・午後」という言葉も生まれました。とはいえ、運は待つだけでは育ちません。茨城の社寺で手を合わせ、目標を具体的に言葉にして、今日から一つ行動を足してみる。小さな積み重ねが、午年の大きな成果につながります。家族や仲間と宣言を共有するのも、続けるための良い工夫です。
茨城に伝わる「馬」信仰のルーツをやさしく解説
日本では、古くから馬は“神さまの乗り物”と考えられてきました。豊作や雨を願うときに本物の馬を奉る例があり、やがて木や土で作った馬、人が描いた「絵馬」へと簡略化され、誰もが願いを託せる形になりました。「黒馬は雨を呼び、白馬は雨を止める」といった伝承も各地に残っています。常陸国(今の茨城)は古代から牧が置かれ、街道も発達していました。運搬・農耕・軍事のすべてで馬が活躍し、人びとの暮らしと信仰が重なった結果、「駒形」「馬場」「馬渡」などの地名、神社の神馬舎、寺の馬頭観音、社殿の馬に関する彫刻など、多くの痕跡が今も見られます。参拝のときに地名や彫刻の意味を知ると、風景が一段と鮮やかに感じられます。茨城の旅は、そうした“馬の記憶”を訪ね歩く楽しさに満ちています。
「うま」と相性の良い参拝日・持ち物ミニガイド
落ち着いて祈りたいなら、朝の時間帯がいちばん。空気が澄み、人も少なく、写真もきれいに撮れます。持ち物は、①賽銭・おみくじ用の小銭(10円・50円・100円を少し多めに)②御朱印帳とペン(境内メモにも便利)③ハンカチと小さなゴミ袋(手水や簡単な清掃に)④歩きやすい靴。参道の中央は“正中”といって神さまの通り道とされるので端を歩き、鳥居の前後で軽く会釈、手水で身を清めてから拝殿へ進みます。寺院では合掌一礼が基本で、香や供花の扱いは掲示に従いましょう。馬に関する願いは具体的に。「2026年の大会でベスト更新」「愛馬○○が一年健康に」「家族の交通安全」など、期限や状況を入れると行動につながります。帰宅後24時間以内に旅の気づきをメモするのもおすすめ。次の参拝までの“行動計画”が自然に決まります。
参拝のマナーと絵馬・蹄鉄の奉納アイデア
神社では「二拝二拍手一拝」。姿勢を正し、心の中で住所・氏名・日付・願意を落ち着いて伝えます。願いを形に残すなら絵馬が最適です。表に願いを肯定形で、裏に日付と名前、達成の目安を書き添えると、読み返したときに気持ちが整います。馬とのご縁を深めたい人には、蹄鉄モチーフの授与品や“馬蹄絵馬”が人気。レース名や大会日時、目標順位、感謝の言葉まで入れると、努力の方向が見えやすくなります。奉納するときは他の参拝者の妨げにならない場所で静かに掛け、撮影はマナー優先。寺の馬頭観音や石仏は風化が進む場合があるため、むやみに触れず、供花や清掃の奉仕で敬意を表しましょう。旅ごとにテーマを決めて絵馬を集め、ノートに貼って“願いの記録帳”を作るのも、学びと振り返りに役立ちます。
半日/1日で回れるモデルコース
〈午前〉成田方面から車で稲敷市・大杉神社へ。境内の「勝馬神社」で勝負運や安全を祈り、蹄鉄モチーフの絵馬に願いを書いて奉納します。〈昼〉霞ヶ浦周辺の直売所や食事処で一息。湖の景色を眺めながら、地元の野菜や甘味を楽しみましょう。〈午後A(競馬・乗馬好き)〉JRA美浦トレーニング・センターは関係者施設ですが、主催者が不定期に見学会や公開イベントを行うことがあります。予定が合えば公式情報を確認して参加し、合わない場合は周辺の資料展示や乗馬関連ショップを楽しむのがおすすめ。〈午後B(歴史好き)〉那珂市の駒形神社で彫刻を鑑賞→笠間市の馬頭観音の古像へ。〈1日満喫〉時間に余裕があれば守谷・清瀧寺で花の境内と石仏を拝し、夕暮れはカフェで旅のノートをまとめます。車が便利ですが、公共交通+タクシー併用でも十分回れます。
② 勝負運を上げたい人へ:稲敷「大杉神社(勝馬神社)」で祈願
勝馬神社ってどんなところ?(由緒とポイント)
稲敷市阿波958に鎮座する大杉神社は、関東随一のあやかり神として知られる古社です。境内には、馬とのご縁が深い「勝馬神社」が祀られています。古くは「馬櫪社(ばれきしゃ)」と呼ばれ、地域の人びとが馬の守護と勝負ごとの成功を願って参拝してきました。近くに競馬関係施設がある土地柄もあり、競馬・乗馬の必勝祈願はもちろん、受験や商談、スポーツなど“ここ一番の勝ち運”を求める参拝者が多いのが特徴です。境内には馬にちなむモチーフや授与品がそろい、絵馬掛けも活気があります。初めてでも、拝殿前に立つと自然に背筋が伸びるはず。参拝は朝の時間帯が静かでおすすめ。混雑期は駐車や順路の案内に従い、静粛を心がけましょう。
美浦トレーニング・センターとあわせて楽しむコツ(アクセス便利帳)
大杉神社から車で行きやすいのが、稲敷郡美浦村美駒2500-2にあるJRA美浦トレーニング・センターです。普段は関係者以外立ち入りできませんが、主催者が不定期に見学会や公開イベントを告知することがあります。見学では調教コースの迫力や厩舎の雰囲気を肌で感じられ、馬の息づかいに胸が高鳴ります。予定は時期によって変わるため、事前に公式情報を確認しましょう。開催がないときは、周辺の資料パネルや記念品を扱うショップを巡ったり、霞ヶ浦沿いの道で景色を楽しむのも一案です。大杉神社→美浦→土浦・霞ヶ浦周辺とつなぐと、半日でも“馬づくし”の満足感が得られます。
蹄鉄モチーフの授与品・絵馬の楽しみ方
勝負運にあやかるなら、蹄鉄モチーフの授与品や“馬蹄絵馬”が心強い味方です。願いは具体的に、肯定形で、日付や数字を添えて。“いつ・どこで・何を達成するのか”が明確になるほど、行動がぶれません。例:「2026年○月の○○大会でベスト更新」「今季、愛馬○○が無事完走」「商談成功、チーム一丸で」。奉納の前後で深呼吸し、感謝の言葉を心に置くのも大切です。お守りは“持ち歩く誓い”として使い、毎朝見たときに小さな行動を一つ決めると、願いが日常に根づきます。授与所の受付時間は季節で変わるので、現地掲示の案内に従いましょう。
写真に映える境内スポット案内
写真を撮るなら、「朱の構造物×木漏れ日」の組み合わせが王道です。参道の端から、拝殿へ伸びる直線を生かすと、気持ちがスッと引き締まる一枚になります。馬にちなんだカットなら、絵馬掛けや蹄鉄モチーフの授与品を“寄り”で撮影し、背景に参道や社殿の気配を入れると物語性が増します。順光なら色がはっきり、逆光なら光の輪郭が美しく写ります。人物を入れる場合は導線の妨げにならない端で、拝礼中の方は写さないのが基本。撮影禁止や立入禁止が表示されている場所は必ず守りましょう。曇りの日は濃淡が柔らかく、彫刻の細部が見えやすくなります。
周辺の休憩・甘味・土産リスト
参拝の合間は、霞ヶ浦周辺の道の駅や直売所でひと休み。新鮮な野菜や湖の加工品、地元の和菓子や焼き菓子は旅のお供にぴったりです。湖畔のカフェは窓が大きく、午後の光が気持ちよく差し込みます。季節の変わり目は身体を冷やしやすいので、温かい飲み物を一杯。土産は“馬”モチーフのキーホルダーや栞、ノートなど、日常で使える小物が喜ばれます。運転は無理をせず、時間に余裕を持って安全第一で。営業時間や定休日は時期で変わることがあるため、出発前に最新情報を確認しましょう。
③ 馬の名を持つ社を訪ねる:那珂・小美玉の「駒形神社」
那珂市・駒形神社の見どころ(文化財の本殿など)
那珂市南酒出の駒形神社は、食を司る神をまつる古社と伝わり、神体を“葦毛馬”とする伝承も残ります。見どころは市指定文化財の本殿。安永10年(1781)の年紀が確認され、江戸後期の力量ある大工・彫物師による意匠が楽しめます。三面をめぐる大きな彫刻群は、海の理想郷を思わせる場面や武の物語など、多様な主題が一体となって社殿を飾ります。戦後の混乱期に一部が失われたと伝わりますが、現存部分からも当時の技術の高さがよく伝わります。正面からだけでなく、側面や背面も丁寧に観察してみてください。衣のひだ、雲や波の“抜き”、余白の取り方など、彫刻の呼吸が分かってきます。境内は静かで、朝の光が斜めに入る時間帯が特に美しいです。
小美玉市・駒形神社の立ち寄りメモ(アクセスと周辺)
小美玉市には同名の「駒形神社」が複数あり、地域に根づいた“馬の社”の歴史を今に伝えています。なかでも中根所在の本殿は元禄16年(1703)の建造として知られ、江戸前期の素朴で端正な造りが魅力です。周辺は田畑が広がるのどかなエリアで、車での参拝が便利。ナビで住所を確認し、現地の社標や案内板に従って静かにお参りしましょう。近くには直売所や乳製品が評判の店も点在します。空港のある市だけにアクセス道路が整備され、ドライブの合間に短時間で立ち寄れるのも魅力です。季節の花が咲く時期は、社殿と緑のコントラストが映えるので、カメラを持って散策するのもおすすめ。地域の生活道路が多いので、歩行者と自転車に十分注意して走行してください。
御朱印・駐車・トイレ情報の比較(目安表)
| 名称 | エリア | 特徴・見どころ | 参拝のコツ |
|---|---|---|---|
| 駒形神社(南酒出) | 那珂市 | 本殿は市指定文化財。江戸後期の彫刻が見事 | 朝の光がきれい。社殿の側面・背面も観察 |
| 駒形神社(中根ほか) | 小美玉市 | 元禄期の本殿を伝える。素朴で端正 | 車が便利。周辺は生活道路、徐行と駐車マナー厳守 |
※御朱印・駐車・トイレの詳細や受付時間は寺社・自治体・現地掲示で最新をご確認ください。地域行事の日は混雑することがあります。
社殿彫刻の読み解き方入門
江戸期の社殿彫刻は、信仰の内容を物語として伝える“立体の本”です。龍は水と守護、波は吉兆、鳳凰は調和と再生、松竹梅は不老長寿、武将図は武運長久を象徴します。駒形神社の本殿では、海の理想郷を思わせる場面や名将にちなむ主題が、社の守りと繁栄への願いを重ねます。鑑賞のコツは三つ。①全体を一度に見ず、面ごとに主題を探す。②衣のひだや雲の渦、波頭の形など“線の流れ”を追う。③陰影を観察する。朝夕の斜光は彫りの起伏を強調し、職人のノミ跡まで浮かび上がらせます。小さな双眼鏡が一つあると、見落としがちな細部の“抜き”や、背面の仕上げまで楽しめます。彫刻の前では声をひそめ、手で触れないことも大切です。
近くで寄り道したい公園・カフェ
参拝の余韻を味わうなら、緑の見えるベンチや、静かなカフェでノートを開きましょう。那珂・小美玉は空が広く、夕方の光が社殿や田んぼの水面に反射してとてもきれいです。テイクアウトの飲み物と甘味を用意し、御朱印帳や写真を並べて、今日の学びを三行でメモ。次に見たい社や石仏も書き添えておくと、次回の計画がすぐ立ちます。地域の直売所では旬の野菜や果物、乳製品が手頃で、手土産にも向きます。駐車は指定場所に、路上ではドアの開閉にも配慮を。小さな祠や石仏を見つけたときは、長居をせず、合掌一礼して静かに立ち去るのが礼儀です。
④ 仏教に宿る“うま”の守り:茨城の「馬頭観音」をめぐる
馬頭観音とは?(やさしい基礎知識)
馬頭観音は観音菩薩が怒りの相を示す姿の一つで、頭上に馬の頭部をいただく像容(地域差あり)で表されます。忿怒の表情は、迷いを断ち切って救う強い慈悲をあらわし、古くは家畜守護や道中安全の信仰が広がりました。街道沿いの石仏や峠の祠に多いのは、旅人や馬の無事を願った名残です。現代では交通安全やペットの健康を祈る人も増え、供花や清掃の奉仕で感謝を伝える姿が見られます。参拝の基本は、静かに合掌一礼。石仏は風化や欠損があることも多く、触れずに距離を保つことが大切です。写真は地域の方の迷惑にならない範囲で。香やろうそくの扱いは、お堂や寺の掲示に従いましょう。
笠間市・本戸の木造馬頭観音立像(市指定文化財)
笠間市本戸には、市指定文化財の「木造馬頭観音立像」が伝わります。制作は南北朝末から室町前期と推定され、三面八臂という古い形式を保つ貴重な存在です。漆箔がほどこされ、手には剣や索、斧、宝棒などの持物を備えます。頭頂の馬頭部は欠失していますが、像全体からは力強い忿怒のエネルギーが感じられます。所在地は本戸4021-1とされ、地域の方々によって大切に守られてきました。拝観の可否や見学方法は時期や管理形態によって異なるため、現地の案内に従い、無理な接近・撮影は控えましょう。堂内外の環境を損なわないよう、履物や声の音量にも配慮して、短時間で礼を尽くす参拝を心がけたいところです。
守谷市・清瀧寺の馬頭観音と「花の寺」散策メモ
守谷市の清瀧寺は天台宗の寺院で、創建は大同2年(807)との伝承が伝わります。境内は季節の花が豊かで、春は新緑、夏は青もみじ、秋は紅葉、冬は凛とした空気が心地よい場所です。馬頭観音も祀られ、交通安全や家畜守護を願って参拝する人が訪れます。拝観や御朱印の受付時間は時期によって変わることがあるため、現地の掲示や公式の案内を確認しましょう。最寄り駅から徒歩圏ですが、荷物が多い場合はバスやタクシーの併用が便利です。花や石仏を撮影するときは、他の参拝者の動線をふさがないよう注意を。土の道が湿っている日は滑りやすいので、歩きやすい靴で出かけると安心です。
日立・筑西エリアの石仏小旅行アイデア
“道端の仏”を探す小旅行も魅力です。筑西市上中山の鹿島神社境内には、大正7年(1918)に造立された馬頭観音の自然石型石仏が残る例が知られています。日立エリアでも街道沿いの石仏や道標、観音群が地域の歴史を物語り、短時間の散策で多くの気づきが得られます。石仏は地域の方々が守ってきた大切な文化財です。私有地や生活道路では、駐停車や通行のマナーを最優先に。供花や清掃を行う場合は、地元のルールに従い、短時間で静かに。石の上にのぼる、像に触れる、チョークでなぞるなどは厳禁です。帰り際には合掌一礼し、「大切に守られてきた場所にお邪魔させていただく」気持ちを忘れないようにしましょう。
供養と祈願の作法・持ち物
寺院では、合掌一礼、静かな足取り、そして周囲の人への配慮が基本です。線香やろうそくは可否が分かれるため、堂前の掲示で確認を。風の強い日は火の取り扱いに特に注意し、灰が飛ばないように手で囲むと安心です。持ち物は、薄手の手袋(清掃用)、花を入れる小さな袋、ウェットティッシュ、賽銭用の小銭、メモ帳。願いは「交通安全」「旅の無事」「馬やペットの健康」など具体的に。石仏には触れず、倒壊の恐れがある像には近づきすぎないこと。御朱印がある寺では、筆耕時間や書置き対応を事前に確認し、混雑時は静かに順番を待ちます。志納は無理のない範囲で、維持管理への感謝の気持ちを添えて納めましょう。
⑤ 地名・古墳・伝承で味わう“馬”の歴史
水戸・「馬塚古墳」をのぞいてみよう(基礎データ)
水戸市の愛宕山古墳は、那珂川流域でも有数の規模をほこる前方後円墳で、国の史跡に指定されています。墳丘長は136.5メートルとされ、古代の強い首長の力を今に伝えます。この周辺には古墳がまとまって存在し、愛宕山古墳群の一つとして「馬塚古墳」と呼ばれる円墳が知られています。名称の由来には諸説ありますが、地域の人びとが古墳に馬の伝承を重ねてきたことを示す、貴重な痕跡です。見学の際は、史跡の掲示や遊歩道の案内に従い、植生を傷めない歩き方を心がけましょう。愛宕神社の参拝とセットにすると、古代から続く“祈りの地形”を体で感じられます。季節ごとに光や風の表情が変わるので、同じ場所を時間を変えて再訪するのも楽しい体験です。
地名に残る「駒」「馬」を探すまち歩き
“駒”“馬”の文字が付く地名や社名は、古くから馬が暮らしや交通、戦や儀礼に深く関わってきた証です。たとえば「駒形」は馬の姿に由来し、「馬場」は流鏑馬や稽古の場、「馬渡」は渡河点に由来する可能性が考えられます。実際の由来は地域ごとに異なるため、案内板や郷土誌、古地図を手がかりに歩くと発見が増えます。コツは三つ。①神社や祠、石仏、道標が直線や曲線でどのようにつながるかを地図に落とす。②水の流れ(川・湧水・湿地)と地名を重ねる。③坂や台地の“端”に注目する。馬の通行は勾配や水に敏感なので、地名と地形のリンクが見えてきます。歩くときは、生活道路や私有地に配慮し、写真撮影は住民の方に配慮して短時間で。小さな学びを積み重ねるほど、まちの“見え方”が変わります。
午年の開運アクションカレンダー
節目は“行動のスイッチ”です。2026年の午年、毎月の午の日、そして一日の“午の刻”。この三つを合図に、小さな習慣を一つずつ重ねていきましょう。たとえば、午の日に参拝して目標を更新、午の刻に5分だけ片づけやストレッチ、月末は“馬の記録帳”を見返して次の一歩を決める、といった具合です。旅では、①早朝参拝で心身のスイッチを入れる、②直売所や市場で旬の味をいただく、③帰宅後24時間以内に学びを三行で記録、の三本柱がおすすめ。記録はスマホでも紙でもOK。行動の証拠が積み重なるほど、自信が静かに育ちます。午年を迎える頃には、もう“結果の芽”が見えているはずです。
交通・拝観・志納の目安(早見表)
| 項目 | 目安・ポイント |
|---|---|
| 交通 | 車が便利。公共交通+タクシー併用も可。生活道路では徐行と歩行者優先。 |
| 開門・拝観 | 神社は早朝参拝可の所が多いが、授与は日中中心。寺は拝観・御朱印の時間を事前確認。 |
| 作法 | 神社:二拝二拍手一拝。寺:合掌一礼。掲示と職員の案内を最優先。 |
| 志納・初穂料 | 御祈祷は数千円〜(社寺で異なる)。御朱印は書置き・直書きで金額や時間が変わる。 |
| 撮影 | 立入禁止・撮影禁止の掲示を厳守。拝礼中の人物は写さない。SNS投稿は節度を。 |
子どもと一緒に学べる“うま”自由研究プラン
テーマ例は「絵馬の歴史とデザインの変化」。手順は、①神社で絵馬のデザインを観察し(撮影や掲載は個人情報に配慮)、色・文字・モチーフを記録。②図書館や博物館の資料で、神馬奉献→馬形→絵馬への流れを調べる。③家族の願いを言葉にして、厚紙でオリジナル絵馬を制作。④旅で訪ねた駒形神社、馬頭観音、古墳を地図にまとめ、「馬の信仰マップ」を作る。⑤最後に発表会。評価を高めるコツは、地域ごとの違いと“願いを形にする工夫”を自分の言葉で書くことです。作った絵馬は家で掲げ、毎月一度見直して行動を一つ追加。研究が生活に結びつき、続けるほど効果が実感できます。
まとめ
茨城には、馬の文化と祈りの記憶が、神社仏閣・地名・古墳・石仏のいたる所に息づいています。稲敷の大杉神社(勝馬神社)で“勝ち運”を願い、那珂と小美玉の駒形で彫刻と歴史に触れ、笠間・守谷・筑西・日立で馬頭観音の慈悲に合掌する。水戸の古墳群では、古代の首長権力と祈りの地形が重なって見えてきます。午年を待たずとも、今日の一歩が明日の運を育てます。作法を尊び、地域の暮らしに敬意を払いながら、学びと感謝を重ねていく。そんな“うま”の旅は、きっとあなたの日常に静かな追い風をもたらすでしょう。
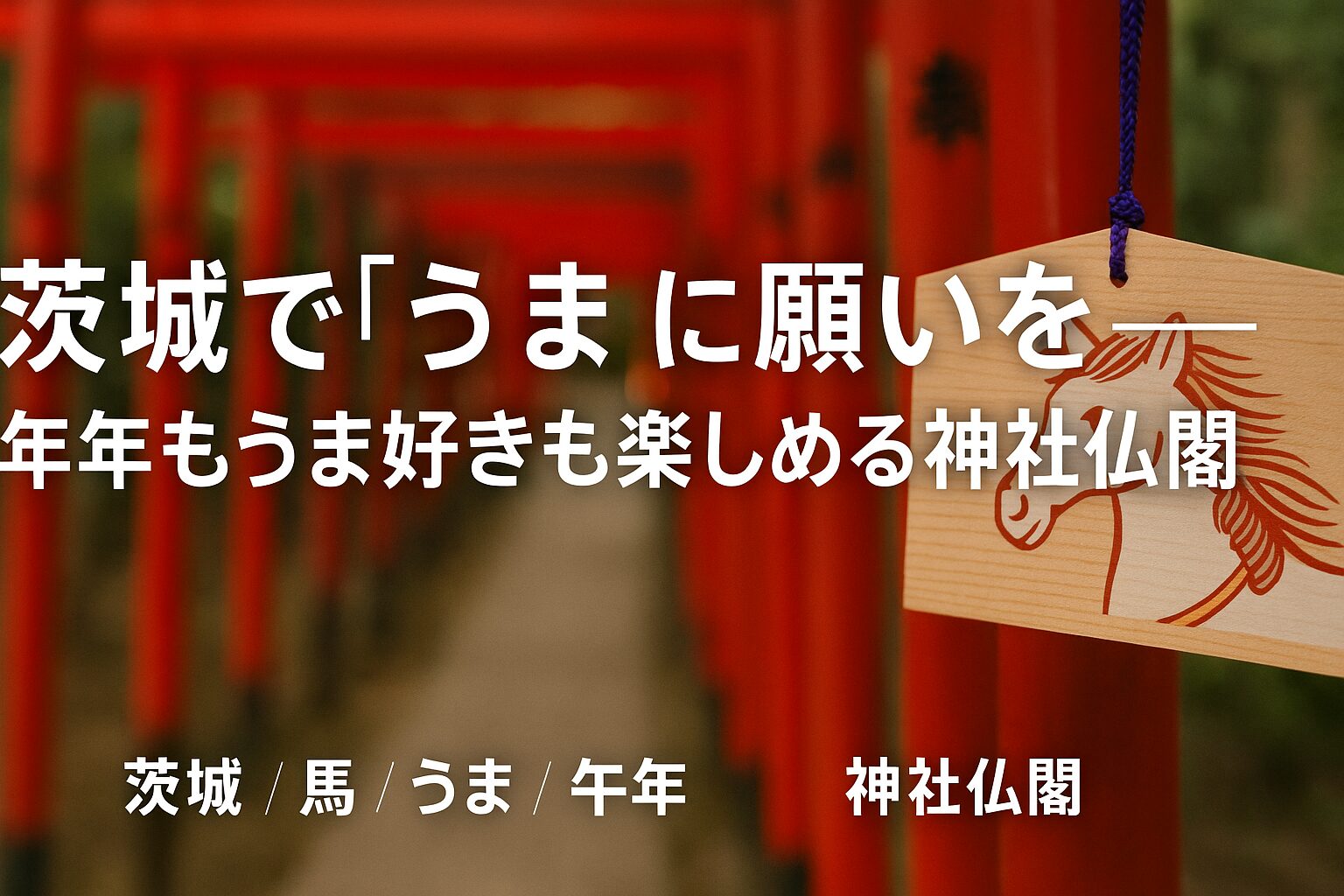

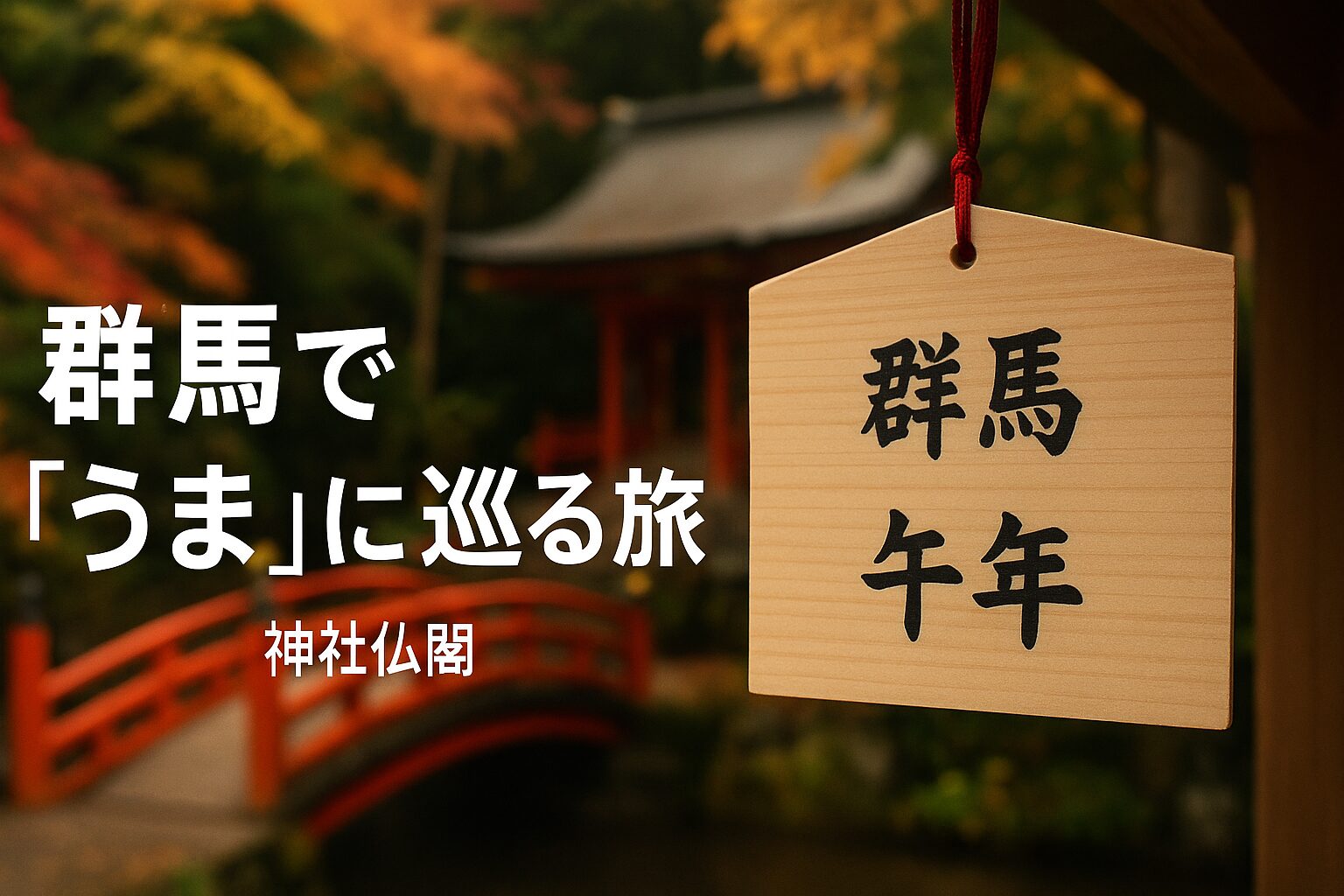
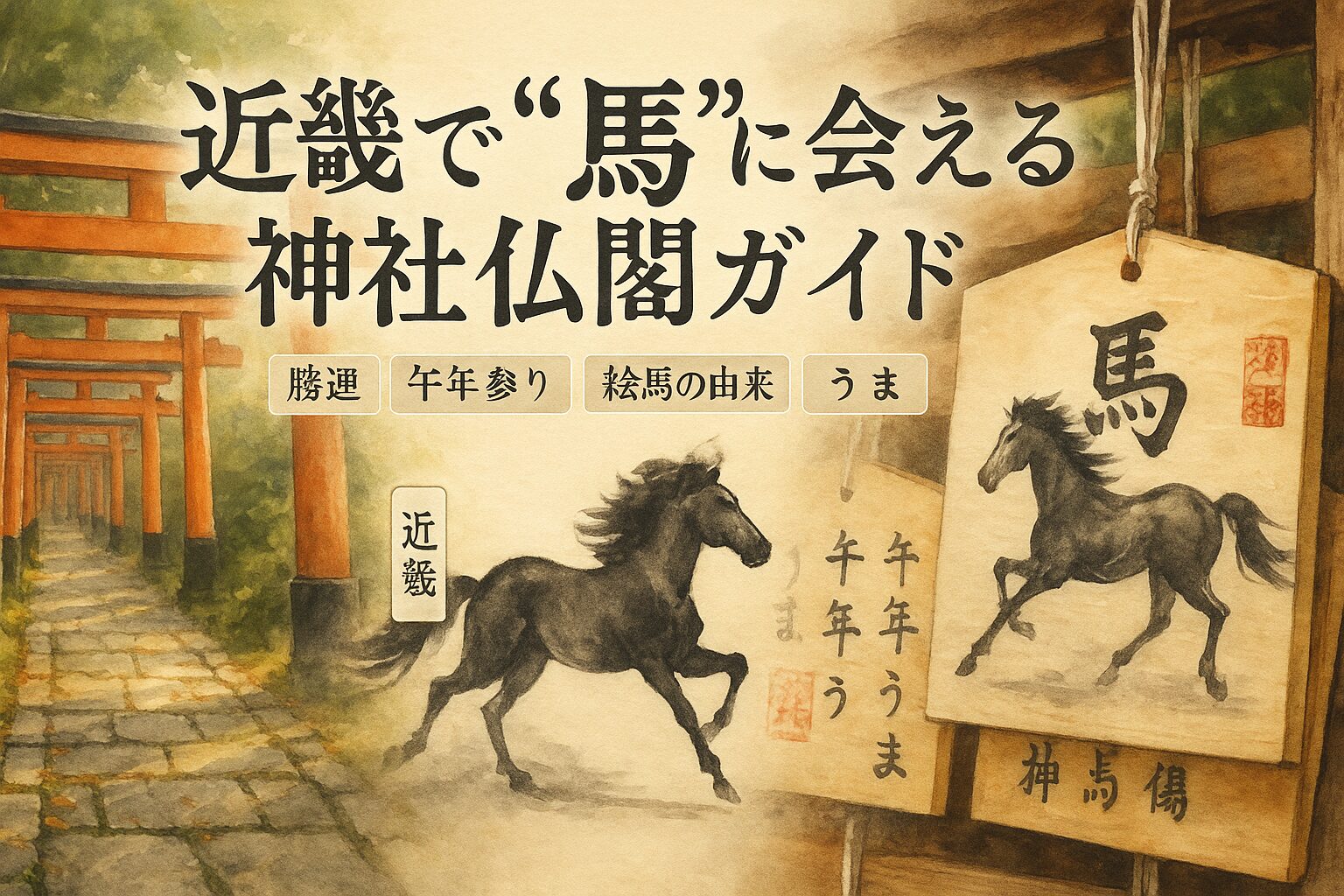
コメント