うま入門:午年と馬信仰のキホン
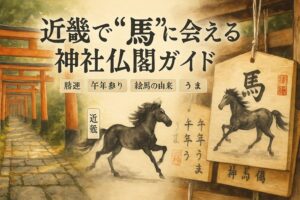
午年生まれでなくても、“馬にあやかって飛躍したい”。そんな気分の日に手に取りたいのが、この近畿「うま」巡りガイド。京都の駈馬・流鏑馬、貴船の絵馬伝承、奈良の古道と国宝社殿、滋賀の馬頭観音、兵庫の競馬場、熊野の牛馬童子まで、現地で役立つマナーとアクセス、撮影と御朱印のコツを一冊にまとめました。準備を整えたら、今日の小さな一歩を地図に描きに行きましょう。
午年の意味とご利益の考え方(勝負運・仕事運・健康運)
午(うま)は十二支の七番目で、方角では南、五行では火に配されます。古来「疾きこと馬のごとし」と例えられ、勢い・機運・突破の象徴として語られてきました。ただし干支そのものが願いを叶えるのではなく、暦が“行動のスイッチ”になることが本質です。参拝の際は、願いを一つに絞り、期日と測れる指標を添えるのが実践的。例えば「三か月以内に提案Aを成約、関係者が納得して契約完了」など、プロセスの姿勢まで言語化すると日々の判断がぶれません。勝負運を意識するなら“準備で勝つ”を合言葉に、具体的な行動(毎朝15分の復習、毎週の面談記録など)も誓うと効果的。参拝時間は午=太陽が高い時間帯を意識し、朝〜昼の明るい気の流れで心身を整えるのもおすすめです。大切なのは「感謝→お願い→報告」の循環を作ること。叶った後は必ずお礼参りをし、次の一歩の覚悟を神前で新たにしましょう。
絵馬のはじまりと「馬」を奉納してきた歴史
かつては本物の“馬”を神前に奉る風習がありました。旱天には黒馬、長雨には白馬(または赤馬)という“色”の使い分けが記録に見え、やがて生馬に代えて木板に馬を描いた「板立馬(いただてうま)」が奉納されます。これが現在の絵馬の原型とされ、特に京都・貴船神社は天候を司る神を祀る社として朝廷の祈雨・止雨祈願を受け、白馬・黒馬の故事を今に伝えます。現代の絵馬は“神さまへの見える手紙”。願いは一枚に一件、叶ったら奉納所にお礼の言葉を返すと筋が通ります。奉納の向きは境内の指示に従い、紐はほどけにくく結ぶのが基本。なお、絵馬の意匠は社ごとに特色があり、馬、神紋、祭礼、季節の図柄なども楽しい見どころです。旅先では授与所で起源やおすすめの奉納場所を尋ねると、由緒や小話を教えてもらえることも少なくありません。
神馬・馬頭観音・牛馬守のちがいをやさしく整理
神社の「神馬(しんめ)」は神の御乗物としての馬で、かつては生きた馬をつなぐ厩がありました。今は木像や青銅像、絵馬の図柄としてその象徴が残ります。仏教の「馬頭観音(ばとうかんのん)」は六観音の一尊で、馬の頭をいただく姿。畜生道の救済を担い、家畜や旅人、道中の安全を守るとされ、旧街道の分岐や峠に石仏・石碑として多く祀られています。道端の「馬頭観音」刻字碑は、交通の難所・事故の多い場所の目印でもあり、地域の暮らしに根ざした“祈りのランドマーク”。お守り名の「牛馬守(ぎゅうばまもり)」は家畜安全の系譜に連なり、現代では車両や仕事道具の安全を重ねて授かる人もいます。参る先が神社なのか寺院なのかで祈りの言葉や所作は少し異なるため、入口で掲示や係の方に従うのが最善です。違いを知って歩くと、同じ“馬”でも祭祀・信仰の層が立体的に感じられるでしょう。
参拝の基本マナーと動物ゆかりの社寺での注意点
鳥居の前で一礼し、参道は中央を避けて歩く、手水舎で手口を清める、拝殿では「二拝二拍手一拝」。この基本をまず整えます。動物に縁のある社寺では、神馬舎や像に触れない、餌を与えない、フラッシュを焚かない、の三点を徹底。祭礼や神事の最中は関係者の導線を妨げない位置から短時間で撮影し、係の指示に即座に従いましょう。寺院は堂内撮影不可の場所が多く、掲示の有無を必ず確認します。授与品は「身につけるもの(守)」「境内に納めるもの(絵馬)」「家で祀るもの(神札・お軸)」の違いを理解して受けるのが大切。帰宅後は神棚や清浄な場所に安置し、月次の挨拶を心がけると関係が育ちます。最後に、参拝はお願いだけでなく「感謝」と「報告」までが一連の作法。小さくても達成できたことを神前で告げると、次の行動の背中を押してくれます。
年間のおすすめ時期と時間帯(初詣・節分・例祭の活用)
近畿で“馬”をテーマに巡るなら、京都の5月がハイライト。上賀茂神社の「賀茂競馬(かもくらべうま)」は毎年5月5日、古式ゆかしい行列と午後の競馳が見どころです。下鴨神社の流鏑馬神事は毎年5月3日(葵祭の前儀)として知られ、春の若葉のなか馬と射手が駆け抜けます。藤森神社の藤森祭は同じく5月初旬、勇壮な駈馬神事が名物。冬の節分期は石清水八幡宮の「鬼やらい神事」が季節の風物詩です。いずれも開始時刻や観覧方法は年ごとに変動するため、出発前に当年の公式案内を確認するのが安全。混雑を避けるなら午前から現地入りし、見たい神事の前には水分補給とトイレを済ませ、撮影ポイントは早めに確保しましょう。マップ上で退避路・最寄り駅・臨時便の有無を押さえておくと、家族連れでも安心して楽しめます。
京都で“馬”巡りベストスポット
藤森神社(伏見):勝運と“駈馬”で知られる馬の守護
伏見の藤森神社は、勝運・学業成就、そして“馬の守護”で広く知られます。端午の節句の頃に行われる藤森祭では、参道馬場で伝統の「駈馬神事」が披露され、手綱潜りや逆乗りなどの妙技が続き、境内にどよめきが広がります。授与所には「勝馬守」「うまくいく守」など馬にちなむ品が豊富で、受験やスポーツ、商談を控えた人の背中を押す存在。境内は紫陽花の名所でもあり、雨上がりの石畳と社殿、咲き始めの花が写真映えします。アクセスはJR奈良線「JR藤森」駅から徒歩約5分、京阪本線「墨染」駅から徒歩約7分とシンプル。祭礼日や頒布物は年度で変わるため、出発前に公式の最新案内を確認すると安心です。参拝の所作は落ち着いて丁寧に、そして願いははっきりと。駈馬の疾走を胸に刻み、日常の一歩を軽くしましょう。
上賀茂神社(北区):神馬の伝統と社殿意匠に宿る“うま”
世界遺産・上賀茂神社(賀茂別雷神社)は、葵祭の前儀として「賀茂競馬」を伝えます。平安装束の行列、古式の作法、そして午後の競馳。古のリズムが一日を貫き、馬と人、神と氏子の関係が目の前に立ち上がります。見学は午前から境内に入り、式次第に沿って場所を移すのがコツ。社殿や玉垣、細部の装飾には“馬”に関わる意匠が潜み、絵馬所や神馬舎にも注目したいところです。勝負運・道中安全の祈願先としても定評があり、交通は市バスや地下鉄北山駅からのバス、タクシーが便利。近年は観覧席設定や導線が告知されることもあるため、当年の案内を事前にチェック。境内の小川や芝地は四季の表情が豊かで、静かな日に再訪してもまた違う魅力に出会えます。行事の熱気と日常の静けさ、両方を知ると“神社と馬”の時間の厚みが実感できます。
貴船神社(左京区):絵馬発祥と伝わる物語を歩く
貴船川に沿って連なる社域は、本宮・奥宮・結社の三社から成り、水の神を祀る総本宮として信仰を集めます。古来、雨乞いには黒馬、止雨には白馬(または赤馬)を献じた故事が伝わり、のちに木板の板立馬を奉納するようになったとされます。これが今日の絵馬の源流とされ、社頭では白・黒など馬を象った絵馬も授与されています。参拝は本宮から奥宮、結社へと上流に向かう順路で、水音と杉の香りに包まれながら歩くのが醍醐味。叡山電車とバス、あるいは車でのアクセスになるため、繁忙期は朝早くが快適です。石段や濡れやすい木道もあるので、滑りにくい靴が安心。水占いみくじを清流に浮かべれば、文字がゆっくり現れる体験が旅の記憶を鮮明にします。奉納の前に由来に触れ、願いを具体化してから絵馬を書くと、行為そのものが学びに変わります。
石清水八幡宮(八幡):弓馬の精神と勝運祈願の作法
男山の山上に鎮座する石清水八幡宮は、弓矢・武運・厄除の神として崇敬を集めます。節分期の「鬼やらい神事」では、桃弓・桃剣で四方と恵方を祓い、豆を撒いて災厄の侵入を防ぐ古式が続けられています。弓馬の精神に通じる所作は、勝運祈願や心身の引き締めに最適。参拝はケーブルで山上へ、歩いて上る参道も整備されており、家族連れでも安全にアクセス可能です。祈願のコツは「住所・氏名・願意」を静かに心で唱え、深呼吸ののち二拝二拍手一拝。授与所で勝運・厄除の神符や破魔矢を授かり、毎日目にする場所に納めます。社殿は国指定重要文化財の八幡造本殿を中心に荘厳な空気を湛え、四季の眺めも格別。行事の時間・拝観範囲は年で変わるため、当年の案内を確認してからの参詣が安心です。
淀エリア散策:京都競馬場周辺で寄り道したい小社とカフェ
京阪本線「淀」駅から京都競馬場までは徒歩約2分。歩道が整備され、家族連れでも移動しやすい動線です。開催日には阪急「西山天王山」駅と競馬場を結ぶ有料直通バスが運行されるため、京都市内や大阪北摂側からのアクセスもスムーズ。場内は芝生広場やキッズスペース、ピクニック向きのベンチが充実し、パドックでは馬の息づかいを間近に感じられます。非開催日の見学可否やイベントは時期で変動するので、訪問前にJRA公式の最新情報を要確認。周辺は宇治川の堤や旧街道筋に小社が点在し、帰りに中書島で下車して伏見の町家や酒蔵を巡るコースも心地よい締めになります。写真撮影は人の流れに配慮し、馬の進路や係員の指示を最優先。大勢で移動する場合は待ち合わせ場所を先に決め、迷子時の合流手順を家族で共有しておくと安心です。
奈良で体感する“駈ける”伝統
宇太水分神社(宇陀):秋の大祭と“水の神”の物語
宇陀の森に包まれた宇太水分神社は、鎌倉時代建立の本殿三棟が国宝。10月第3日曜を中心に「うたの秋まつり」が行われ、惣社水分神社の女神(速秋津姫命)が神輿で宇太水分神社の男神(速秋津彦命)へ“御渡り”する行列が地域を練り歩きます。各地区の太鼓台が勇壮に競演し、山里に太鼓の響きがこだまします。水配りの神を祀る社らしく、豊穣と無事を願う祈りが今も生活の芯に息づいていることを実感できます。普段は静謐な社域で、社殿の意匠や境内の杉木立、石段の風合いをゆっくり味わえます。祭礼時は交通規制や駐車制限があるため、公共交通と臨時便の情報を事前に確認。雨天時は石畳が滑りやすいので、底の新しい靴と雨具を用意しましょう。近隣の古道や古社と組み合わせると、奈良の「水と信仰」の文脈が立体的に見えてきます。
大和路で出会う馬頭観音:石仏・お堂の探し方
奈良から滋賀にかけての大和路・湖東路は、路傍の信仰が濃いエリアです。馬頭観音の石仏や刻字碑は、旧街道の三叉路、峠の登り口、田の畦、村落の辻に静かに立ち、旅人と家畜を守る“見えない結界”の役目を担ってきました。探し方のコツは、古地図で旧道の筋をなぞり、カーブや橋、集落の入口を重点的に歩くこと。寺社の境内に一緒に祀られる例や、地蔵堂の内部に安置される例も多く、住民の方に一声かけると丁寧に教えていただけることもあります。撮影は短時間・低姿勢で、私有地や農地に勝手に入らないのが鉄則。滋賀・湖北の長浜周辺には中世作の優品も点在し、事前予約で拝観できる寺院もあります。路傍仏を巡る一日は、派手さはないものの、地域の暮らしと祈りに触れる“深い観光”。帰路、ノートに場所・刻字・表情をメモすれば、次の旅の地図が自然に広がります。
山の辺の道:古代の交通と馬の役割を歩いて学ぶ
日本最古級の古道「山の辺の道」は、JR・近鉄天理駅からJR・近鉄桜井駅までの約16kmが標準ルート。古墳群や杜、古社をつなぐ背骨のような道で、古代の物流・祭祀・政の移動に馬が重要な役割を果たしました。初めてなら無理せず、天理駅〜JR柳本駅の約8.8kmなど短縮区間が歩きやすいです。路面は土や石畳が混在し、田畑脇の細道や小さな峠越えもあるため、滑りにくい靴と少量の飲み物、行動食を携行。途中の休憩所やトイレは点在なので、地図アプリで現在地と次のポイントをこまめに確認します。見どころは、大神神社の三輪山遥拝や古墳の葺石、集落の井戸など“生活と祭祀が隣り合う”景観。歩き終えたら最寄り駅からの帰路を柔軟に組み替えられるのも魅力です。道が語る歴史に耳を澄ませながら歩けば、馬が運んだ物資や情報の重みが身近な実感になります。
馬見丘陵公園:古墳文化と“馬”の地名を味わうコツ
奈良県営の馬見丘陵公園は、古墳群と四季の花で知られる広大な公園です。アクセスは近鉄田原本線「池部」駅から緑道口へ徒歩約2分、または近鉄「五位堂」駅から奈良交通バスで「馬見丘陵公園」下車すぐ。無料駐車場も大規模で、家族連れにやさしい設備が整います。地名「馬見」には、古代に朝廷の牧(放牧地)が置かれ、馬を“見た・管理した”ことに関わるとする伝承などがあり、園内の解説と合わせて地名の記憶に思いをはせるのが楽しいポイント。季節イベント時は混雑するため、午前到着と歩きやすい靴、帰路バスの発車時刻の事前確認が快適です。園内は芝地と木陰が豊富で、古墳の周濠や高低差を生かした散策路も整備。花のフェスタ時は写真スポットが多数生まれるので、広角と望遠の二本立てで臨むと構図の幅が広がります。
奈良での参拝&散策モデルルート(近鉄利用)
朝は桜井側から山の辺の道の一部を歩いて大神神社に参拝。三輪山遥拝所で深呼吸し、午前中にJR柳本駅方面へ抜けます。昼食は天理駅周辺で補給し、午後は近鉄で榛原へ移動してバスまたは車で宇陀の宇太水分神社へ。社域で国宝本殿の意匠を味わい、夕方は北上して馬見丘陵公園で古墳群と夕景を楽しみ、近鉄「五位堂」から帰路へ。雨天時は山の辺の道が滑りやすくなるため、撥水の靴、替え靴下、折りたたみ傘を携行。祭礼期は交通規制や臨時便が出ることがあるので、当日の運行情報・開門時間・頒布状況を直前確認して動くと安心です。ICカードは近鉄・JR・バスをまたいで使えるエリアが広く、乗り換えがシンプル。移動の隙間で御朱印の整理や写真のバックアップを行えば、一日の充実感がぐっと増します。
滋賀・兵庫・和歌山の“馬”スポットを賢く見つける
滋賀の甲賀・湖北:馬頭観音の石仏群と里道ハイク
琵琶湖の北・湖北は“観音の里”として名高く、馬頭観音の優品が点在します。鎌倉期の木彫や磨崖仏、江戸期の刻字碑など幅広く、寺院収蔵の像は事前予約や特別公開で拝観するスタイルが一般的。里山の道は舗装・未舗装が混在するため、歩きやすい靴と小型ライト(お堂の暗所で手元確認用)があると安心です。甲賀方面は石仏・庚申塔の密度が高く、道標や道祖神と並んで馬頭観音碑が見られます。地元資料館や観光案内所で配布されるマップは宝の地図。場所の成り立ちや作者、奉納者名を知ると、単なる“石”が一気に語り始めます。撮影時は所有者や管理者の許可に留意し、志納の習慣がある地域では感謝の気持ちを形に。里道ハイクは静けさも魅力なので、話し声を控え、植生や農作業の妨げにならない歩き方を心がけましょう。
兵庫の丹波・但馬:弓馬の民俗行事を知るキーワード
兵庫北部・但馬の一宮である出石神社は、天日槍命を祀る古社。境内は素朴ながら気品があり、城下町・出石の歴史と呼応する落ち着いた空気が漂います。参拝後は出石城跡や寺町を巡り、名物・皿そばで昼をとれば、“祈りと暮らし”の距離感が体に馴染みます。弓馬の所作は日本各地で伝承されていますが、近畿では京都の賀茂社・下鴨社や八幡社の系譜につらなる神事が多く、兵庫の地でも地域行事の節々にその影響を見いだせます。見学の心得は、土地のルールに従うことと、行事の“意味”を理解しようとする姿勢。社頭の掲示や地域紙の特集を事前に読み、撮影よりもまず祈りの流れに身を置く。そうすれば、表面のにぎわいに隠れていた“人と馬の関係”が、ふとした所作の美しさとして立ち上がってきます。
神戸・阪神間:都市部で“馬”の痕跡をたどる歩き方
都市圏でも馬文化は生きています。阪急今津線「仁川」駅から専用地下道・通路を通り、阪神競馬場へは徒歩約5分。開催日にはパドックで周回する馬の筋肉や呼吸、返し馬の集中がすぐそばで感じられ、芝生エリアでは家族が思い思いに過ごします。場内の展示や案内板は、競馬が地域の交通・都市計画とどう結びついてきたかを教えてくれます。周辺の社寺には神馬像や馬意匠が奉納されている例もあり、駅から半径2kmの街歩きに“馬モチーフ探し”を加えると発見が倍増。移動のコツは、人流と逆向きに歩ける裏動線を把握すること、帰路の改札混雑を避けるために一駅歩く余地を残しておくこと。都心近郊で“馬と祈り”の断片を拾い集める時間は、意外な充足をもたらしてくれます。
和歌山・熊野:古道沿いの地名・社伝に残る馬の記憶
熊野古道・中辺路には、僧姿の童子が牛と馬にまたがる「牛馬童子像」があり、花山法皇の熊野詣の旅姿を象る像として知られます。箸折峠近くの山道を辿ると出会える小像は、素朴ながら巡礼の象徴として存在感があり、千年単位の祈りの流れを今に伝えています。古道歩きは滑りにくい靴と雨具、飲み物、行動食、モバイルバッテリーが基本装備。道の駅など拠点で情報を集め、王子社跡や道標とセットで歩くと、地名や地形に“馬と人の移動”の痕跡が見えてきます。天候が変わりやすい山間部では、引き返す判断が命を守ります。無理をしない計画と早めの行動で、石畳や杉の香り、鳥の声を心ゆくまで味わいましょう。帰路に温泉を一つ加えれば、足の疲れも和らぎ、古道の体験が体の芯にしっかり刻まれます。
交通アクセス・混雑回避・駐車のコツ(家族連れ向け)
家族連れの成功ポイントは「最寄り駅の把握」「退避動線」「休憩場所」の三つ。京都競馬場は京阪「淀」駅から徒歩約2分と至近で、開催日は阪急「西山天王山」駅からの有料直通バスが便利。阪神競馬場は阪急「仁川」駅から徒歩約5分、専用地下通路で雨天でも移動しやすい。馬見丘陵公園は近鉄「池部」駅から緑道口へ徒歩約2分、または「五位堂」駅からバスで「馬見丘陵公園」下車すぐ。車利用は駐車場満車の時間帯を避け、早到着・早撤収を基本に。表で主要拠点を整理しておきます。
| 場所 | 鉄道・バス | 所要 | 家族向けポイント |
|---|---|---|---|
| 京都競馬場(淀) | 京阪「淀」徒歩約2分/阪急「西山天王山」駅から直通バス | 2〜15分 | 動線がわかりやすく芝生・ファミリー設備が充実 |
| 阪神競馬場(宝塚) | 阪急今津線「仁川」徒歩約5分(専用地下通路) | 約5分 | 平坦でベビーカー移動がしやすい |
| 馬見丘陵公園(奈良) | 近鉄「池部」徒歩約2分の緑道口/「五位堂」→奈良交通バス | 2〜16分 | 無料駐車場・トイレ・カフェが揃い滞在しやすい |
御朱印・授与品・写真の撮り方ガイド
馬みくじ・馬蹄守・勝馬守:名前と意味のちがい
“馬”モチーフの授与品は、願いの焦点で選ぶと日常で効きます。藤森神社の「勝馬守」は勝負運に特化し、試合・受験・商談など“勝ちに行く局面”で御守として心を支えます。「うまくいく守」は語呂の楽しさがあり、前向きに行動したい人の毎日のスイッチに最適。馬蹄形のチャームは“幸運を受け止める器”の象意があり、玄関内に上向きに掲げると心が整うと語られます。持ち歩く場合は、財布・定期入れ・スマホケースの内側など、必ず毎日目に入る場所へ。授与は現地でご縁を結ぶのが基本で、転売品は避けます。祭礼期は特別授与や数量限定の品が出ることもあるため、頒布方法・初穂料・書置き可否は事前確認を。受けた後は「感謝→実践→お礼参り」のリズムを作り、破損や汚損が進んだら感謝して納札所へ丁寧に返納しましょう。
絵馬の書き方と願いが伝わるフレーズ例
絵馬は“神さまへの手紙”です。基本は「住所(市区町村まで)・氏名・願意・期日」を簡潔に。願意は一件に絞り、「2026年○月○日までに志望校合格、努力を楽しみ続けられますように」「家族が一年間、無事故で健やかに過ごせますように」など、結果と姿勢の両方を書くと心が定まります。裏面にお礼参りの予定日を小さく記すと、自分への約束にもなります。奉納時は、紐をしっかり結び、他の方の個人情報が写り込まない角度で記念写真を一枚だけ控えるのがスマート。SNS投稿時は名前・住所を隠し、位置情報も必要に応じてオフに。貴船や藤森など“由来に直結する社”で奉納すると、行為の意味がより深く感じられ、旅の満足度も上がります。
御朱印で“うま”デザインを集める楽しみ方
“馬”意匠の御朱印は、祭礼期や限定頒布で出会えることが多いのが特徴です。藤森神社では祭礼期間に関連印が出る年があり、上賀茂・下鴨・貴船でも季節や行事に合わせた朱印が見られることがあります。混雑時の作法は「参拝を先に、朱印は後で」。列が長い場合は書置き対応の有無、頒布時間、初穂料を先に掲示で確認しましょう。集印帳は防水カバー付きが便利で、ページには日付・天気・見どころを一言メモ。帰宅後にページを眺めると、香りや音まで思い出され、“旅が二度楽しい”感覚が訪れます。保管は直射日光と湿気を避け、長期旅行の際はクリアファイルで別持ちに。御朱印はあくまで参拝の証。印そのものを“集める目的”にせず、祈りと学びの記録として大切に扱いましょう。
境内での写真作法:神馬や像を撮るときの注意
神馬像や馬のレリーフは信仰の対象です。柵の内側に入らない、像に触れない、順番を守る、この三原則を徹底しましょう。動きのある神事(流鏑馬・駈馬)は、安全柵の外から望遠寄り・シャッタースピード優先でブレ対策を。午前と午後で光が変わるので、馬体の毛並みや装束の色をきれいに出すには順光と背景の抜けを意識すると効果的。下鴨の流鏑馬は午後開催が通例のため、早めの現地入りで人垣の後ろに回らない立ち位置を確保すると快適です。人物の顔が映り込む場合は声かけや配慮を。記録より安全が最優先で、係員の指示に従うこと。公開範囲が限定される寺院では撮影自体が不可のことも多く、掲示の有無を必ず確認してからカメラを構えましょう。
旅の持ち物チェックリスト(服装・現金・雨具・下調べ)
必携は、滑りにくい靴、小銭・千円札(初穂料・ロッカー・バス用)、折りたたみ傘と薄手ポンチョ、モバイルバッテリー、クリアファイル(御朱印・パンフの保護)、小型ライト(暗所の石仏堂で手元を照らす)。加えて、帽子・日焼け止め・虫よけ、替え靴下、常備薬があると万全です。直前チェックは、神事の開始時刻、授与の有無、鉄道・バスの運行情報、京都競馬場の直通バスの設定や乗り場、混雑予測。家族連れは迷子時の合流場所と時間を決め、連絡が取れないときの“最終集合点”を紙で持たせると安心です。写真は一日ごとにバックアップし、充電ケーブルと予備メモリも携行。荷物は両手が空くリュックにまとめ、貴重品は体の前側で管理するのが安全です。
まとめ
“馬”は、勝負や道中安全を願った日本人の祈りの象徴です。京都では駈馬や流鏑馬の躍動、貴船の絵馬伝承が息づき、奈良では古道と国宝社殿、地名に記憶が残る。滋賀では路傍の馬頭観音が地域の時間を語り、兵庫では都市の競馬場が馬の迫力を日常に近づけ、和歌山では熊野古道に巡礼の像が佇む。それぞれの土地で形を変えながら続く“馬の物語”を、足で、目で、耳で確かめてください。最初は一社からで大丈夫。次にもう一歩だけ足を延ばす。そうして地図に自分だけの“うま巡礼”が少しずつ描かれていけば、午年でなくても、日々の背中を押す追い風が必ず吹いてくれます。
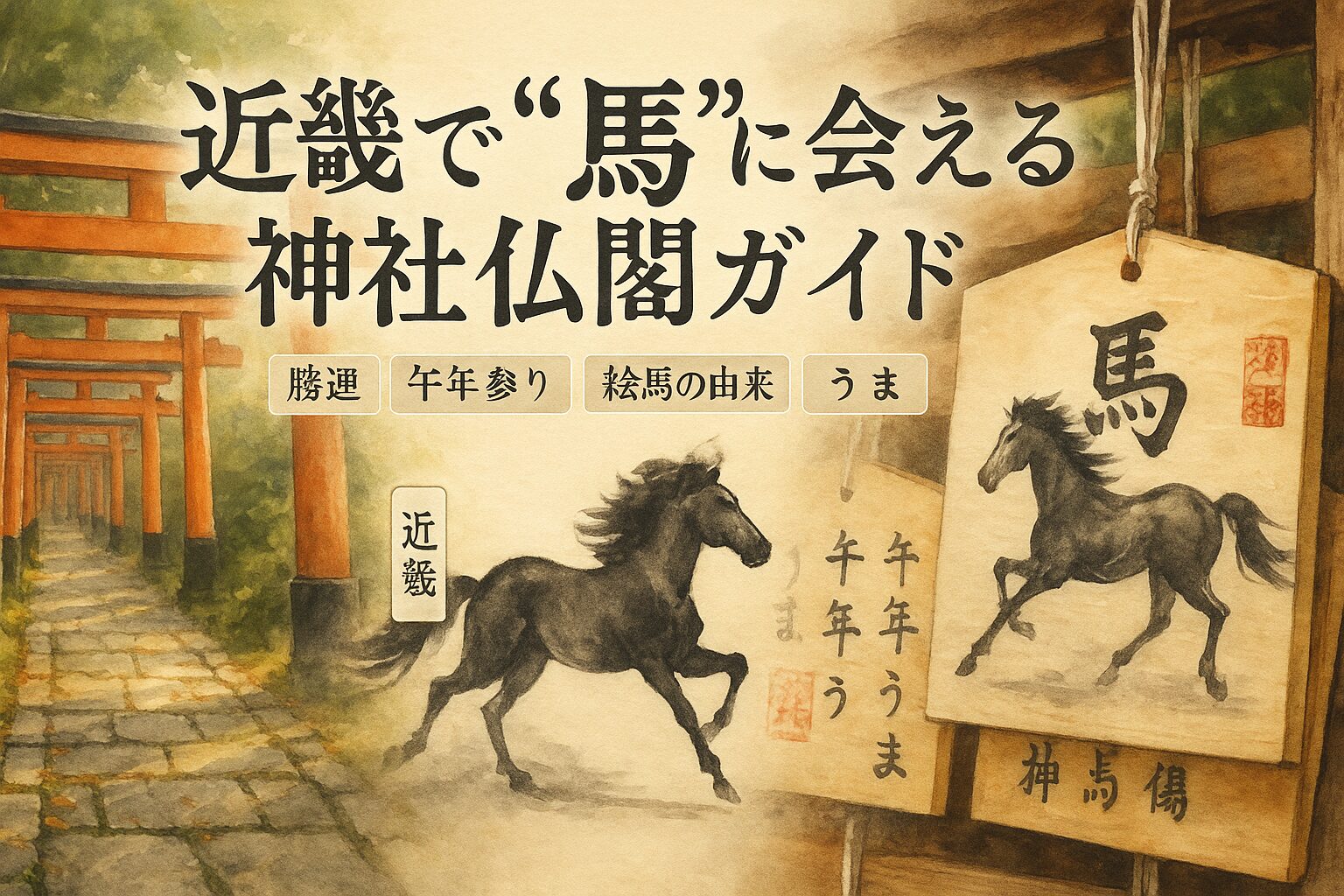

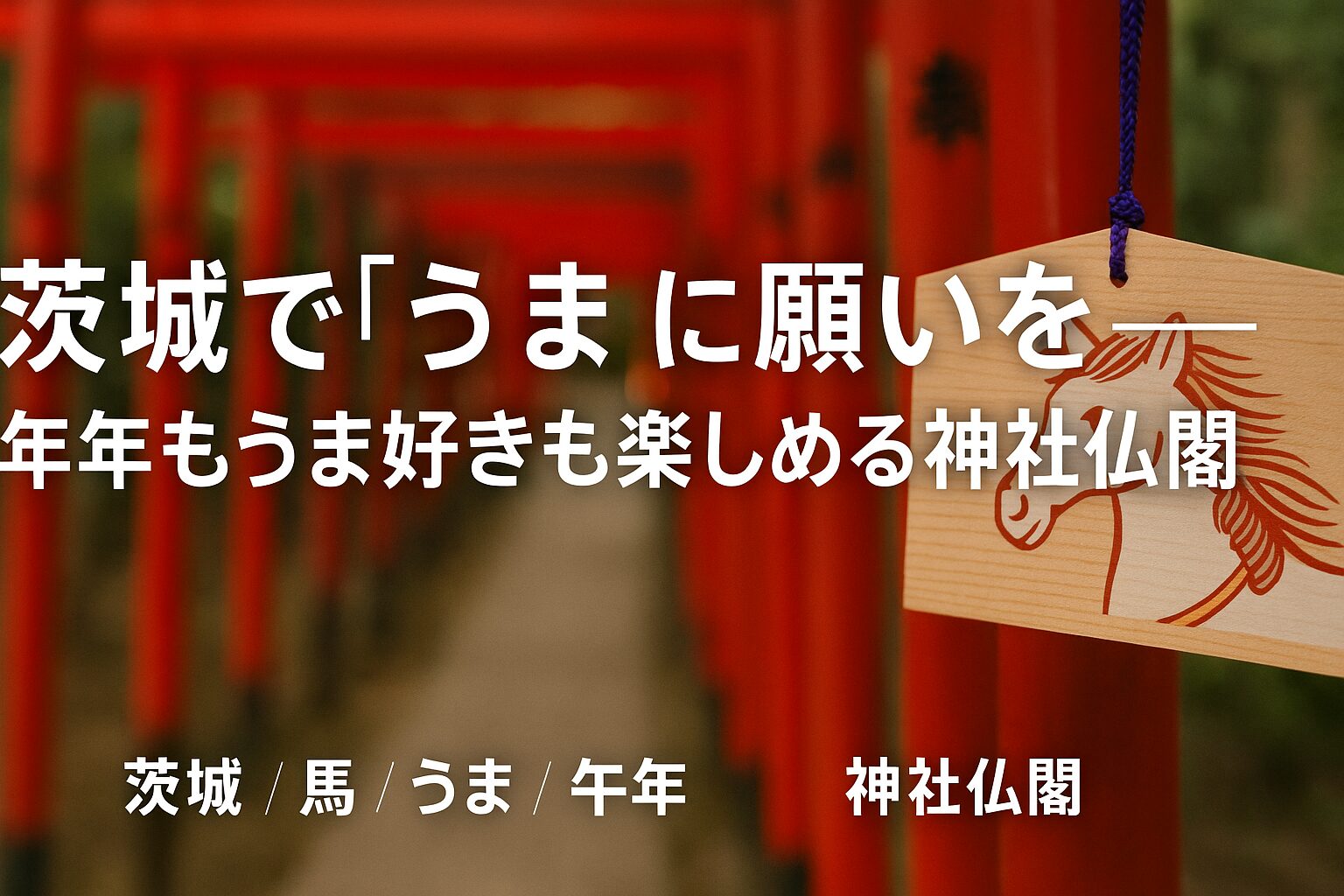

コメント