佐賀×馬×信仰の基礎(「午」と干支/絵馬の由来/馬頭観音)

佐賀の旅は「午(うま)」を知るほど面白くなります。日本三大稲荷に数えられるとされる祐徳稲荷で成就を願い、武雄では流鏑馬の矢が放たれる瞬間に息をのむ。道端の馬頭観音に手を合わせれば、馬と共に生きた土地の時間が目の前に現れます。作法や混雑対策、モデルコース、交通の勘所まで本記事に集約しました。初めてでも迷わない視点と準備で、祈りと歴史に寄り添う旅へ。地図にない心の道筋まで、静かに確かめに行きましょう。
「午(うま)」の意味と干支の基礎
十二支の「午(うま)」は七番目に位置し、方角では南、季節では夏の盛りを象徴する概念として伝わってきました。干支は本来、年・月・日・時刻や方位を表すための暦法で、現代の性格診断のような単純な占いに留まりません。日本各地、とくに平野が広がる地域では、馬は農耕と運搬の主力であり、街道の安全や作業の成就を祈る対象でした。佐賀平野は用水網と街道が発達し、馬の働きと人の暮らしが密接に結びついていた土地です。旅で「午」を手がかりに社寺や石塔を巡ると、祭礼の日取り、社殿の意匠、道端の祠が一本の線で理解でき、単なる観光の寄せ集めから、土地の時間をなぞる“学びの旅”へと質が変わります。勢いを象徴する「午」と、無事を見守る「馬」という二つのキーワードを持って歩くと、祈りの言葉も自然に絞られます。まずは“何を成し、何を守るか”を心の中で明確にし、次章の稲荷・絵馬・馬頭観音へと進みましょう。
初午と稲荷信仰のつながり
稲荷信仰では、和銅四年二月の“初午”の日に稲荷大神が鎮まったという伝承が広く伝わり、全国の稲荷社で毎年「初午祭」が行われます。鹿島市の祐徳稲荷神社でも、二月最初の“午の日”に神事や奉納が組まれるのが通例で、参拝者の願いが境内に折り重なります。2025年の初午は二月六日(木)。混雑は午前から午後にかけて高まりやすい傾向にありますが、神事や催しの細かな時間は年によって調整され、直前の公式告知で更新されます。旅程を初午や「二の午」に合わせると、授与や祈祷の機会が増えて雰囲気も一段と華やぎます。計画時の要点は二つ。第一に、時間割や参列方法は当年の告知で必ず再確認すること。第二に、人出を見越し、参拝・休憩・移動の動線を先に描いておくことです。暦を意識して訪ねるだけで、同じ参拝でも“意味の濃度”が確かに変わってきます。
絵馬の由来と現在の形
絵馬は、古くは神に生きた馬(神馬)を奉じた祈願が、土馬・木馬を経由して板札へと簡略化したものとされます。やがて板には馬だけでなく、稲穂や社紋、干支、地域の吉祥図が描かれるようになり、願意に合わせた選択が可能になりました。祐徳稲荷神社には「うまくいく絵馬」という名の授与品があり、仕事・学業・商い・挑戦ごとに“伸ばしたい一点”を素直な言葉で書くのが実践的です。書き入れは短文で十分。奉納時は他の参拝者を妨げない位置で静かに一礼し、撮影は流れを止めない範囲に抑えます。雨天に備え、耐水ペンや透明袋を携行すると文字が滲みにくく安心です。絵馬は記念品ではなく、願いの“預け先”。帰宅後も節目に写真や手帳で振り返ると、行動が言葉に追いついているかを自省する手がかりになります。古代の神馬奉納の精神が、現代の旅人の背中を静かに押してくれるはずです。
馬頭観音とは何か(六(七)観音の一)
馬頭観音は観音の変化の一つとして、六観音(あるいは七観音)に数えられます。柔和な姿が多い観音の中で、馬頭観音が忿怒の相で表されるのは、迷いを断ち切る働きを象徴するためと解されます。民間信仰では特に牛馬の安全・供養と結びつき、街道沿い、村境、田畑の畔などに石塔が数多く建てられました。佐賀では街道と水田の地勢ゆえに、馬の働きと祈りが密に絡まり、今も地域の方が小さな祠を掃き清め、供花を絶やさず守っています。旅人は大仰な作法を要しません。まずは立ち止まり、合掌し、短く感謝を伝えること。写真は通行の安全を最優先にし、フラッシュは避ける。長く続く祈りの場では、この控えめさこそが最上の礼になります。牛馬を守る祈りは、現代では“働く者の無事”という広い意味へ自然に拡張されて受け継がれています。
佐賀の“馬にまつわる行事”年表
| 時期 | 行事 | 場所 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 2月初午(2025年は2/6) | 初午祭 | 祐徳稲荷神社 | 日付は固定。神事の時間は毎年告知で更新。午前〜午後に混雑しやすい傾向。 |
| 10月22日 | 宵のまつり(エイトウ) | 武雄 | 夕刻〜夜に行列が練り歩く前夜祭。導線・規制は当年告知で確認。 |
| 10月23日 | 流鏑馬奉納 | 武雄神社周辺 | 例年14:00〜15:00に奉射。会場や観覧エリアは年により微調整あり。 |
祐徳稲荷神社で“うま”にあやかる
参拝と境内の歩き方(懸造の社殿)
祐徳稲荷神社は、日本三大稲荷に数えられることが多い名社(呼称は諸説あり)で、山腹に張り出す懸造(舞台造)の社殿と、豪華な漆塗り・彩色で知られます。参拝は原則として終日可能で、夜間は照明が入り雰囲気が一変します(特別な夜間演出は時期による)。拝殿で心を整えたら、時間と体力に応じて奥の院へ。公式に所要時間の明記はありませんが、一般的な旅行案内では“登り約10分”とされることがあり、混雑・脚力・天候で差が出るため安全見積もりで10〜30分を確保すると安心です。雨後は石段や回廊が滑りやすく、下りで集中力が切れがちなので特に注意。境内は告知により通行止め区間や休憩所の新設などの変更が出ることもあるため、出発前に最新情報を確認しましょう。車は武雄北方IC/嬉野ICからおおむね30〜40分、公共交通は肥前鹿島駅からバス・タクシーが現実的です。
授与品「うまくいく守」「うまくいく絵馬」と“左馬”の縁起
祐徳稲荷神社の授与所には「うまくいく守」「うまくいく絵馬」など、名前から意志が引き出される授与品が並びます。旅のテーマを“うま”に据えるなら、いずれも相性良好で、後日の御礼参りで進捗を確かめる目印にもなります。参道や門前では“左馬(ひだりうま)”の文字や意匠に出会うことがあります。左馬は将棋駒で名高い山形・天童の飾り駒に由来する縁起物とされ、「うま」を反転させると「まう(舞う)」に通じる、馬は左から乗るので安全、袋の口が閉じず福を集める、など複数の説が伝わります。どれか一説に絞って断定するよりも、招福・商売繁盛・千客万来の象徴として素直に受け止めるのがよいでしょう。授与所では願意(家内安全・仕事成就・学業など)を最初に伝えると最適な品を案内してもらいやすく、迷いが減ります。
門前で楽しむ買い物・食事のポイント
参拝後は門前商店街へ。羊羹や最中などの甘味、温かいうどんやいなり寿司などの軽食が、歩き旅の回復に効きます。買い物は参拝を済ませてから、両手が空くバッグにまとめるのが基本。石段や細い通路、車の導線に近い場所では立ち止まりすぎないこと。土産の選び方は「家に帰ってから旅の記憶をもう一度開けるか」を基準に、消えものに加えて長く使える台所道具や紙もの、書が印刷された札などを一つ選ぶと余韻が長持ちします。雨の予報なら紙袋の補強に折りたたみのビニール袋を携帯。写真は店舗や通行の妨げにならない位置で、人物が写る場合は声をかける。小さな配慮の積み重ねが、地域の受け入れ空気を穏やかにします。
初午・午の日の参拝作法と混雑対策
初午や土日祝の“午の日”は境内が混み合います。鳥居で一礼し、手水で身を清め、拝殿では二礼二拍手一礼。願いは短く明確に。混雑を避けるなら、早朝到着→本殿参拝→奥の院→授与所の順で回ると流れがよく、家族連れは役割分担(並ぶ人・撮る人・荷物をまとめる人)で効率が上がります。神事の時間や駐車誘導は年により調整が入るため、出発直前に最新の公式告知を必ず確認しましょう。授与や御朱印も混雑に合わせて対応が変わることがあります。小銭・雨具・薄手のタオルをサコッシュにまとめ、両手を空けて移動すれば安全かつ所作も整います。焦らず譲り合いを基本にすることが、結果として一番の近道です。
写真スポットと安全配慮(撮影マナー)
楼門の正面シンメトリー、山肌に張り出す舞台を見上げるローアングル、朱の鳥居が続く奥の院参道は定番の撮影ポイントです。晴天は朱が鮮やかに、雨の日は石畳が反射して落ち着いた表情になります。午前は影が短く輪郭がくっきり、夕方は光が柔らかく人物の肌がきれいに出やすい傾向。いずれも安全最優先。三脚は通行の妨げになりやすいため、人の流れが切れた場所と時間を選び、係員の指示に従いましょう。階段や回廊での長時間の場所取りは避け、撮影後は小さく一礼してから退くと、次の人も気持ちよく撮れます。祈りの場であることを忘れず、静けさを守る振る舞いが、結果的に良い一枚につながります。
武雄神社の流鏑馬を体感(毎年10月23日)
起源とストーリー
武雄の流鏑馬は、源頼朝の戦勝祈願にまつわる伝承を背景に、領主が奉納したのが始まりと伝えられます。以来、町ぐるみで受け継がれてきた年中行事で、装束の行列、神前の儀、馬場での奉射が一体となって展開します。疾走する馬上から三つの的を矢で射抜く妙技は、瞬時の判断と集中、弓・馬・人の一体感が求められ、見る側の呼吸まで速まる迫力です。単なる見世物ではなく、地域の祈りの表現であることを理解して臨むと、一射ごとの緊張と歓声の意味が深まります。担い手は装束の準備から馬の手配、射手の鍛錬、馬場整備に至るまで長い時間を重ねています。旅人はその労に敬意を払い、安全に配慮しながら見学しましょう。
例年の当日進行(行列/神事/奉射)
基本的な流れは、22日の「宵のまつり(エイトウ)」で気運を高め、23日の本祭で行列(上り馬)→神事→馬場見せ→奉射→行列(下り馬)という順序です。奉射は例年14:00〜15:00が中心。会場は武雄神社前から武雄市図書館・歴史資料館の北側馬場周辺が案内される年が多く、交通規制や歩行者天国の時間帯が設定される場合もあります。行列のコースや観覧エリア、規制の範囲は年ごとに微調整が入るため、開催週に必ず最新の市・観光の告知を確認してください。行列中は太鼓や幟、装束の色合いが映え、奉射では的の割れる音と歓声が重なります。撮影は安全優先で、ロープ際や進路直前での立ち止まりは禁止です。
観覧エリアと安全マナー
観覧で最優先は安全です。ロープの内側に出ない、馬の進路に踏み出さない、フラッシュを使わない。この三点は厳守しましょう。初めてなら直線区間が見やすく、的・射手・馬の動きが把握しやすい位置です。カーブ外側はスピード感のある写真が狙えますが、馬の挙動が変化しやすいため、係員の指示に注意を。子ども連れは後方で見通しの良い場所を選び、荷物は最小限に。帽子・飲み物・タオルは季節を問わず役立ちます。撮影に集中すると周囲への反応が遅れがちなので、シャッターチャンス待ちの間も前後左右の気配を意識してください。譲り合いは全員の満足度を上げます。終了間際の移動は人流が重なりやすいため、時間に余裕を持たせるのが賢明です。
アクセスと温泉合わせプラン
会場は武雄神社周辺。JR武雄温泉駅から車で約5分、武雄北方ICから約8分が目安です。行事日は市役所などの臨時駐車場に誘導されることが多く、歩行者天国の時間帯が設けられる年もあります。午前は御船山や図書館・資料館で散策、昼食後に神社周辺へ移動して奉射を観覧、夕方は武雄温泉で汗を流すのが王道。祐徳稲荷からの移動は車でおおむね30〜40分、距離は約19km。公共交通は祐徳神社前と各駅を結ぶ路線があるものの、ダイヤは改定されやすく本数も季節で変わるため、出発前に最新の時刻表を必ず確認してください。温泉は混雑時間帯を避けると快適。タオル・替え靴下・水分補給を忘れず、帰路の渋滞を見越して時間差で動くとスムーズです。
雨天・子連れの楽しみ方(最新情報の確認)
小雨決行となる年もありますが、最も滑りやすいのは行列の合間の移動時です。防水性のある靴とフード付きのレインウェアを一着用意し、傘は人混みではなるべく避けましょう。子ども連れは行列中心に短時間で区切るのが無理のない楽しみ方。音やスピードに驚くことがあるので、耳当てやおやつを用意すると安心です。ベビーカーは混雑区間で持ち上げが必要になることがあるため、抱っこひも併用が現実的。開催可否・導線・規制は天候と安全配慮で当日朝に更新される場合があります。必ず開催週の最新告知を確認し、情報に従って観覧場所や移動計画を選んでください。終了後は周辺の喫茶や温泉で休憩して時間をずらせば、帰路の混雑を和らげられます。
佐賀の馬頭観音をめぐる小さな旅
佐賀市・西与賀の馬頭観音(基礎情報)
佐賀市西与賀町には、地域に守られてきた馬頭観音の石塔が伝わります。牛馬の供養や無病息災の祈りと結びついた小さな祈りの場で、生活道路のすぐ脇に置かれていることも珍しくありません。訪ねる際は、私語を慎み、長居を避け、私有地には入らないのが基本。供花や線香の扱いは地域の作法に従い、片付けまで自分の責任で行います。写真は通行を妨げない位置からフラッシュなしで。夕方や雨の後は足元が暗く滑りやすいので注意してください。場所が分かりにくい場合は、無理に探し回らず、地元の方に丁寧に尋ねるのが最短です。石塔の前では由来の札や銘、脇の道標も確認し、誰が、いつ、どんな思いで建てたのかに思いを寄せましょう。短い滞在でも、静かに合掌するひと時が、旅の芯を落ち着かせてくれます。
佐賀市・久保田町草木田の「三馬レリーフ」
佐賀市久保田町草木田には、三頭の馬をレリーフ状に彫り出した珍しい馬頭観音像が現存します。昭和十五年(1940)の紀元二千六百年記念に建立された比較的新しい作例で、古像に比べて摩耗が少なく、彫りの線が読み取りやすいのが特徴です。近隣にも別の馬頭観音が点在し、同じ地域の中で年代や意匠の違いを見比べられます。訪問前に地図上で候補地点を複数ピン留めし、住宅地の細道を安全に回れる順路を組むのがコツ。長居は避け、ゴミは必ず持ち帰りましょう。午前と午後で光の角度が変わり、レリーフの陰影も印象が変化します。真正面だけでなく斜めから眺めると、馬体の線や鬣の彫りが立ち上がって見えるはずです。祈りの対象であることを忘れず、観察が終わったら合掌一礼を。旅の時間と地域の記憶が静かに重なります。
江北町・小田宿の伝説と観音堂(1998年再建)
長崎街道の宿場・小田宿には、奈良時代に行基が大楠へ馬頭観音を刻んだという伝説が伝わります。観音堂は嘉永四年(1851)の火災で焼失しましたが、平成十年(1998)に再建され、街道文化と信仰の交差点として今に引き継がれています。伝説の真偽はさておき、街道の要衝に祈りの場が置かれたこと自体が、旅の無事を願う人々の切実さを物語ります。訪ねる際は、宿場の町割りや道の曲がり、往来の痕跡に目を凝らすと、当時の賑わいが想像しやすくなります。案内板や古写真があれば、観音堂と街道の関係を具体的に読み解けます。堂内外は清潔に保たれているため、履物や手の泥を落としてから一礼を。近隣の史跡とも徒歩でつなぎやすく、短時間でも街道歩きの実感を得られます。静かなふるまいが、地域の長い信仰環境を守る第一歩です。
神埼市・千代田の馬頭観音菩薩像塔(天保十二年〔1841〕)
神埼市千代田町・上犬童地区の公民館敷地内には、天保十二年(1841)の銘を持つ馬頭観音菩薩像塔が残ります。江戸後期の作で、像容や刻銘が比較的明瞭に読み取れる点が特徴です。周辺には時代の異なる石塔も点在し、意匠や大きさ、安置のされ方を比較すると、信仰の広がり方や建立の目的が見えてきます。街道に近い石塔は旅の安全を、集落の入口の石塔は地域の守りを、それぞれ強く意識して建てられた可能性が高いと考えられます。訪問時は地域行事や会合の妨げにならない時間帯を選び、車の駐停車には特に注意。石塔は風雨にさらされるため、触れたり擦ったりせず、目で観察するのが基本です。写真は斜め光で陰影を出すと刻線が読みやすく、ストロボは使用しないのが無難です。最後に小さく一礼し、来た道を静かに戻りましょう。
参拝の心得と言葉
寺社・小祠・石塔に向かうときは、まず一礼。賽銭は音を立てて投げ入れず、そっと納めます。願いはたくさん並べるより、一番大切な一点に絞ると心が定まり、言葉も自然に短くなります。写真は通行の妨げにならない位置から、フラッシュは基本的に使わないのが無難。人物が写る場合は声をかけましょう。生活道路や私有地に近い場所が多いため、路上駐車や長時間の滞在は避け、音量を控えめに。唱える言葉は難しいものでなく、「おかげさまで」「どうぞ無事で」。この二つで十分です。帰り道に小さなゴミを一つ拾う、靴の泥を払ってから門を出る。そんな小さな行動が旅先の信頼を育て、次の旅人の居心地をよくします。祈りの場は地域の日常の場所でもある。借り物の時間に入れてもらっている意識を忘れないことが、良い旅の作法です。
旅を組み立てる:モデルコース&実用情報
日帰り定番:祐徳→武雄→佐賀市
| 時間帯 | 行程 | 目安とポイント |
|---|---|---|
| 朝 | 祐徳稲荷(本殿参拝→奥の院) | 公式所要の明記なし。一般案内では登り約10分。混雑・脚力で10〜30分見込み、安全は下り重視。 |
| 昼 | 門前で昼食・買い物 | 参拝後に甘味と軽食で回復。荷物は両手が空く形にまとめる。 |
| 午後 | 武雄へ移動→神社周辺散策 | 祐徳から武雄は約19km、車で30〜40分目安。行事期は規制情報を直前確認。 |
| 夕方 | 武雄温泉で湯上がり | 奉射期以外でも温泉街は楽しめる。帰路は時間差行動が快適。 |
公共交通派は、祐徳神社前と各駅を結ぶ路線バスの利用が選択肢になります。ただしダイヤは改定されやすく、季節や曜日で本数が変わります。出発前に最新の時刻表と運行情報を必ず確認してください。車の場合は、臨時駐車や一方通行の設定に注意し、誘導に従うのが最短です。参拝と観覧の所要は混雑で大きく変わるため、各所で30分程度の余白を持たせると、食事や休憩をストレスなく挟めます。
1泊2日:社寺×温泉×景観を満喫
1日目は祐徳稲荷で本殿参拝と奥の院、門前で昼食。有明海の干潟景観を眺めてから武雄へ。夕方は温泉で体を休めます。2日目は御船山楽園や図書館・歴史資料館で建築とアートを楽しみ、日程が合えば宵のまつりや流鏑馬を観覧。夜の移動が不安なら駅前の宿を選べば徒歩圏で完結します。荷物は最小限に、御朱印帳・小銭・雨具・モバイルバッテリー・薄手の防寒具をサコッシュへ。撮影派は予備バッテリーとメモリーカードを忘れずに。食事は行事の合間に取りにくいため、ナッツや羊羹など携帯できる軽食を一つ。二日間の終わりに、石塔や社前で「今日も無事で」と小さく合掌すると、旅の体験が静かに結び直されます。
御朱印と授与の基本
御朱印は参拝後にお願いするのが基本です。書置き対応の時は、折れや雨濡れを防ぐためクリアファイルやジップ袋で保護しましょう。記帳の場合は表紙を開いて受け渡すとスムーズです。授与では目的(家内安全、交通安全、仕事成就、学業など)を最初に伝えると選びやすくなります。祐徳稲荷神社には「うまくいく守」「うまくいく絵馬」があり、旅のテーマ“うま”と相性良好。複数受けるときは願いが重複しないよう整理して選びます。古いお守りは感謝を込めて神社に返納するか、自治体の指示に従って適切に処分を。御朱印も授与も「祈りの記録」であって、スタンプラリーではありません。落ち着いた所作と感謝の気持ちが、何よりの作法です。
服装・持ちものチェックリスト
階段・坂道を安心して歩ける靴、急な天候変化に対応するレインウェア、汗を拭けるタオルは必携。小銭は賽銭・バス・授与で役立つため、小さなコインケースに分けておくと便利です。モバイルバッテリーと充電ケーブル、替えのメモリーカードは撮影派の必須装備。夏は帽子・水・塩飴で熱中症対策、冬は手袋・ネックウォーマーで冷えを防ぎます。傘は混雑で危険になることがあるので、フード付きジャケットを優先。御朱印帳は透明カバーとジップ袋で保護し、出し入れは屋根の下で。身軽さは旅の質に直結します。必要最低限を整え、よく歩く覚悟が安全と満足度を高めます。
季節別注意点と交通案内(鉄道・バス・車)
春は花粉と強風で視界が変わりやすく、目の保護があると安心。梅雨から夏は雷雨が増えるため、濡れても滑りにくい靴底を選びます。秋は武雄の行事期で人出と規制が増えるため、開催週の最新告知を必ず確認。冬は石段が冷え、朝夕は霜や結露で滑りやすくなります。車のアクセス目安は、祐徳稲荷が武雄北方IC・嬉野ICから30〜40分、武雄神社が武雄北方ICから約8分。鉄道とバスの組み合わせは可能ですが、路線と本数は季節・曜日で変動するため、必ず最新の時刻表を確認してください。各所で30分の余白を持たせるだけで、食事・撮影・祈りの時間が安定し、旅の質が上がります。
まとめ
「午(うま)」を手がかりに佐賀を歩くと、祐徳稲荷の懸造の迫力、武雄の流鏑馬の緊張と歓声、そして道端の馬頭観音の静けさが一本の線で結ばれます。古代には生きた神馬を奉じた祈りが、やがて板の絵馬へ。街道の安全を願う気持ちは石塔として今も残りました。形は変われど、感謝し無事を願う心は変わりません。参拝で姿勢を正し、行事で地域の熱量に触れ、小さな石塔の前で深呼吸を一つ。そんな積み重ねが、旅の手触りを豊かにしてくれます。最後にもう一度だけ静かに一礼を。今日ここまで無事に来られたことへの感謝が、次の良い巡りを招きます。


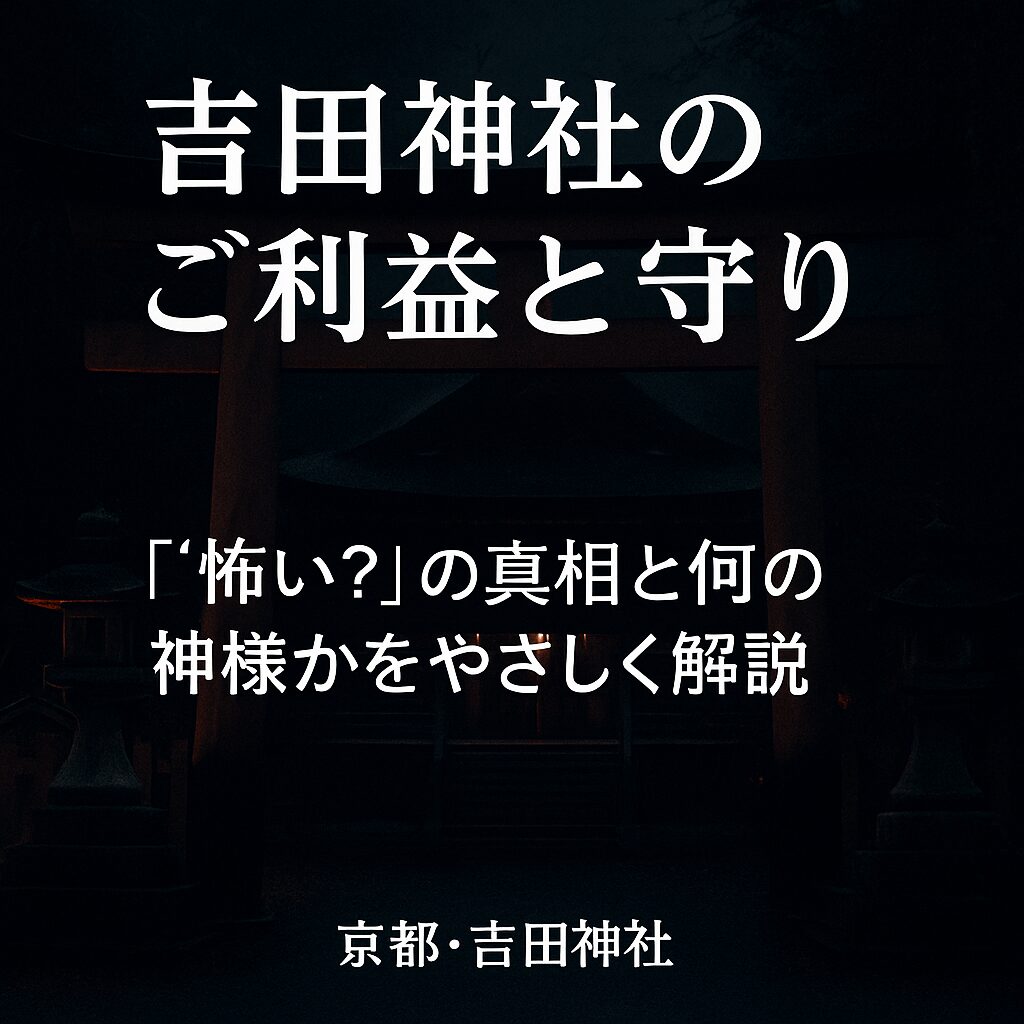

コメント