1. 午(うま)年の基礎と“馬”信仰をやさしく解説

午(うま)年に合わせて、東京の“馬”ゆかりを丁寧に歩く一日旅を提案します。浅草・駒形の駒形堂(ご本尊は馬頭観世音菩薩)から始まり、武蔵国の総社・大國魂神社と“馬のまち”府中、2023年にリニューアルした世田谷の馬事公苑、龍の鳥居で知られる杉並の馬橋稲荷神社まで。地名に潜む“馬”の痕跡を拾いながら、参拝作法、御朱印の受け方、持ち物や写真のコツまで、中学生でも迷わない手順でまとめました。歴史と日常が交差する東京で、馬の文化を丸ごと体感してください。
1-1. 「午」と「うま」のちがい:十二支の基本をおさらい
「午(ご)」は十二支の一つで、本来は動物の馬とは別の“時間・方角・季節”を示す古い符号です。対応関係は、時間なら11時〜13時ごろ、方角は南、五行は“火”。のちに覚えやすいよう十二の動物が当てられ、「午=うま」と教わるようになりました。さらに暦では“十干(甲乙丙…)×十二支(子丑寅…)”の組み合わせで60通りを一巡させるため、60年で生まれの干支が戻ることから“還暦”と呼びます。つまり「干支=十干と十二支のセット」で、「十二支だけ」とは別物。ここを押さえると、午年に馬ゆかりの社寺を訪ねる理由づけが明快になります。昼の太陽が真南に上るイメージや、火の要素の活発さが「前へ進む」「勢いを得る」という連想を呼び、旅のテーマにぴったり重なります。
1-2. 神社とお寺で“馬”はどう祀られてきた?(馬頭観音など)
日本の暮らしにおいて、馬は運搬・農耕・旅の安全を支える相棒でした。神社では、神さまに奉仕する“神馬(しんめ)”が奉納され、祈雨・止雨の祈りに毛色を使い分けた古例も伝わります。やがて生きた馬の奉献が減り、板に描いた“絵馬”を奉納して願いを託す形が広まりました。お寺では、観音菩薩が憤怒の姿で畜生の苦を救う「馬頭観音(ばとうかんのん)」が民間信仰と結びつき、街道沿いの辻や寺社境内に石塔が建てられました。台座に「右○里」などの刻字を添え、道標を兼ねた例もあります。東京でも旧街道に沿って点々と残り、かつての往来や物流の記憶を今に伝えています。境内で像や石塔を見つけたら、建立年や寄進者、場所の由来を示す札に目を通すと、単なる“モチーフ”から地域史を語る“証言者”へと見え方が変わります。
1-3. 神馬(しんめ)ってなに?由来と行事の豆知識
神馬とは、神前に奉仕する聖なる馬のこと。古くは実馬が奉献され、祭礼で牽かれることもありました。現在は木像や青銅像、あるいは絵馬として受け継がれる社が多く、境内の厩の跡や神馬像にその面影を見つけられます。参拝時は、像の前で軽く会釈し、撮影可否の掲示に従い、順路をふさがないのが基本。鼻先に触れる、台座に上がるといった行為は文化財保護の観点から厳禁です。授与所では馬を意匠にした御守や絵馬が並び、願意は勝運、交通安全、健脚、道中安泰など幅広いのが特徴。行事では“神馬牽参”など、地域に伝わる神事が今も行われる所もあります。旅行計画では、祭礼期や特別公開の日時を公式情報で確かめること。静かな日常の姿と、祭りの熱気のどちらを見るかで、同じ社でも印象ががらりと変わります。
1-4. 東京に残る“馬”地名のヒミツ(駒形・馬込・馬喰町 ほか)
地名をたどると、馬文化の痕跡が地図の上に浮かび上がります。浅草の「駒形」は隅田川の川岸に建つ駒形堂にちなむ名で、江戸期には水運の船着き場から上陸した人びとがまずここに手を合わせ、浅草寺へ向かったと伝わります。中央区から千代田区にかけての「馬喰町(ばくろちょう)」は、牛馬の売買や世話を担った“博労(ばくろう)”に由来する説が広く知られ、付近に馬市や馬場があった記録が残ります。大田区の「馬込(まごめ)」は放牧地を示す“牧(まき)”や地形・旧村名に結びつける説など複数が伝わり、どれも土地の歴史を映す手がかりです。看板や橋名、交差点名、商店の屋号などに“馬・駒”の文字が潜んでいることも多く、散歩中に見つけると街がぐっと立体的になります。由来は一つに決めつけず、複数説を“地域の物語”として受けとめる姿勢が大切です。
1-5. お参りの作法と御朱印の基本ポイント
神社では、鳥居の前で一礼してから参道の中央を避けて進み、手水舎で左手・右手・口の順に清めます。賽銭は静かに入れ、鈴があれば軽く鳴らし、「二拝二拍手一拝」で感謝を伝えます。お寺では拍手をせず、合掌と一礼が基本。まず“神社か寺か”を社号標や山門の表記で確かめ、場に合った所作を選びましょう。御朱印は参拝の“しるし”で、拝礼を済ませてから授与所へ。直書き・書置き・整理券の有無、受付時間は場所ごとに違います。書き手の前での私語やフラッシュ撮影は控え、ページ指定や日付の伝達は簡潔に。古い御守・御札は授与を受けた社へ返納するのが基本で、遠方なら近隣社に相談を。地域によっては年末から小正月に“どんど焼き”で焼納する習わしもあります。要は、感謝と節度。小さな気づかいが参拝を心地よくします。
2. 東京で出会う“馬”ゆかりの寺社スポット
2-1. 府中エリア:大國魂神社と“馬のまち”の歴史背景
府中の大國魂神社は、武蔵国の総社として千年以上の歴史を刻む古社です。春の例大祭「くらやみ祭」では太鼓や神輿が欅並木を進み、地域の誇りとして受け継がれてきました。近代の府中はJRA東京競馬場を擁し、馬とともに歩む街としても知られます。駅から神社へは歩いてすぐ、さらに競馬場へ足をのばす動線もよく、史跡と現代のホースカルチャーを一日で味わえるのが魅力です。境内には古碑や境内社が点在し、祭礼期には特別な授与品や御朱印が頒布される年もあります。レース開催日は人出が増えるため、午前中や平日の参拝が快適。参拝後は国府跡やけやき並木の喫茶で一息つくのもおすすめです。歴史の静けさと“走る現在”が一本につながる経験は、馬の文化を東京で学ぶ入門として最適です。
2-2. 浅草〜駒形:隅田川ほとりで“駒”の名をたどる散歩
隅田川に架かる駒形橋の袂に建つ駒形堂は、浅草寺の発祥伝承に関わる聖地です。ご本尊は**馬頭観世音菩薩(馬頭観音)**で、毎月19日が縁日として開扉法会が営まれ、特に4月19日は年に一度の大祭にあたります。堂の名の由来については諸説ありますが、馬頭観音を祀ったことや、馬形の奉納物が起源という考えが伝わっています。江戸時代、堂前は船着き場で、上陸した人びとはまずここに手を合わせ、それから浅草寺へ向かいました。朝の光がやわらかな時間に川沿いを歩き、堂から浅草寺本堂、浅草神社まで進むと、水上交通の記憶と参詣の導線が自然に体に刻まれます。寺と神社で作法が異なる点を意識し、撮影は人の流れを妨げない位置から。絵馬に書かれた個人名や奉納物の詳細が写り込まないよう配慮しましょう。
2-3. 杉並:馬橋稲荷神社と「東京三鳥居」という通称
杉並区の馬橋稲荷神社は、龍が巻き付く彫刻を配した石鳥居で知られます。同様の意匠を持つ品川神社、高円寺境内の稲荷社の鳥居と合わせ、通称で「東京三鳥居」と呼ばれることがあります。制度化された称号ではなく、愛称として広まった呼び名という理解が適切です。境内は清浄で、拝殿・社殿や神門の回廊など見どころが多く、阿佐ケ谷・高円寺の商店街と組み合わせた散策に向いています。周辺の「馬橋」という地名には諸説があり、古い橋の形状や牧の存在に由来する説などが伝わります。参拝は静かな時間帯が快適で、住宅街に隣接するため声量や長居に配慮を。御朱印は受付時間や書置きの有無が季節で変わることがあるため、境内の掲示や公式情報で直前に確かめてから訪れるとスムーズです。
2-4. 都内で見つける馬頭観音:石仏の見方と探し方
馬頭観音の石仏は、旧街道の辻や寺社の片隅に静かに立ち、地域の交通と暮らしを今に語ります。観音の頭上に馬の意匠をいただく像容が特徴で、台座や側面に「右○里」「左△宿」と刻んで道標を兼ねた例もあります。世田谷や板橋、小金井などにも点在し、自治体の文化財ページ、郷土資料館の案内、町会の掲示が探索の糸口になります。探訪の心得は三つ。第一に、私有地や生活道路への配慮。短時間で静かに拝観し、駐輪や駐車は指定の場所に。第二に、撮影マナー。フラッシュや接写で摩耗を進めない、立て札の指示に従う。第三に、読み解き。刻字の年代・地名・寄進者を控え、周辺の庚申塔や地蔵、道の屈曲と照らすと、道の記憶が立体的に見えてきます。石仏は“触るより読み取る”が基本。静かな敬意が最良の保護になります。
2-5. 神田・日本橋:“馬喰町”に残る江戸の物流と馬文化
神田から日本橋にかけての一帯には、今も「馬喰町(ばくろちょう)」の地名が残ります。語源として知られるのは、牛馬の売買や治療、仲介を担った“博労(ばくろう)”にちなむ説。江戸期、この界わいは旅籠や問屋が集まる物流の要衝で、近隣には馬市や馬場が設けられていました。現在はオフィス街の印象が強いものの、壁面のレリーフや案内板、古地図の展示などに“馬”の痕跡を見つけることができます。歩き方のコツは、旧街道の分岐や橋の位置を地図で重ねること。道の曲がりや河岸の跡を意識して歩くと、江戸の動脈が足もとに蘇る感覚があります。史跡めぐりの後は、日本橋の老舗や甘味処で一服を。早足で通り過ぎがちな街に、馬と人が織りなした時間の厚みを感じられるはずです。
3. 午年・うま年生まれにおすすめ!東京1日モデルコース
3-1. 朝:浅草寺→駒形エリアで開運スタート
朝は人出が少ない時間帯に、雷門から仲見世を抜けて浅草寺本堂へ。線香や常香炉の前では周囲に配慮しつつ、合掌・一礼で静かに参拝します。参拝後は隅田川沿いへ移り、駒形橋のたもとに建つ駒形堂へ。ご本尊は馬頭観世音菩薩で、毎月19日は縁日として開扉。4月19日には年に一度の大祭が営まれます。堂の前に立ち、川面をわたる風を感じるだけで、江戸の水上交通と参詣の導線が自然に体に入ってくるはずです。寺と神社で作法が異なる点を忘れず、浅草寺では拍手をしない、境内の撮影は案内に従うなど基本を守りましょう。御朱印は参拝後に授与所で。直書きと書置きの別、受付時間や待ち時間の目安を確かめ、慌てずにお願いすれば、朝の短い時間でも落ち着いて巡れます。
3-2. 昼:府中へ移動—大國魂神社と並木さんぽ
浅草からは都心経由で京王線方面へ。府中駅に着いたら、欅並木が美しい参道を歩いて大國魂神社へ向かいます。拝殿で感謝を伝え、境内社や古碑に目を凝らすと、武蔵国の総社としての歴史が手触りをもって迫ってきます。余力があれば東京競馬場方面へ。開催日やイベントの予定によって混雑は変わるため、公式情報で確認してから動くと安心です。昼食は門前の老舗や並木沿いの喫茶で、季節の甘味や軽食を。授与所では並びの列が長くなることもあるので、通路を空けて静かに待つのがマナー。参道の木陰で休んだ後、府中本町駅側の古道へ回れば、古代から近代へつながる時間の層を一度に踏みしめられます。午後の柔らかな光は写真にも好都合。石畳や玉砂利で足を取られない靴選びも忘れずに。
3-3. 夕方:世田谷・馬事公苑エリアで静かな余韻
午後は世田谷の馬事公苑へ。東京2020大会の整備を経て、2023年11月にリニューアルオープンしました。入苑は無料で、開苑時間は3〜10月が9:00〜17:00、11〜2月が9:00〜16:00(イベント等で変更の場合あり)。芝生広場や馬術施設の外観を眺めながら散策し、厩舎や馬場周辺の見学ルールに従って静かに過ごします。夕方は人出が落ち着き、風と蹄の音が心地よく感じられる時間帯。近隣には東京農業大学方面へ続く散歩路や、ベーカリー・カフェも点在しています。写真は望遠よりも広角寄りで“空気”を入れると記録性が上がり、動く被写体は連写よりシャッタータイミングを意識するとうまくいきます。都市の真ん中で“馬と過ごす時間”に浸り、午年の一日をしずかに締めくくりましょう。
3-4. サブプラン:中野〜杉並「馬橋」界わいの寄り道
高円寺・阿佐ケ谷エリアを歩くなら、馬橋稲荷神社を中心に路地散歩を組み込むと満足度が上がります。龍が巻き付く彫刻の石鳥居、社殿の意匠、神門の回廊と、見どころが凝縮。品川神社と高円寺境内の稲荷社と合わせ、通称「東京三鳥居」として語られることがあります。称号ではなく愛称という理解で気軽に楽しみましょう。御朱印は時期によって直書き・書置きの対応が変わることがあるため、境内の掲示をよく読みます。帰り道はアーケード商店街で甘味や総菜をテイクアウト。夕方の参道は陰影が深まり、写真のコントラストがきれいに出る時間帯です。住宅街に近いので、声量を落とし、長居を避ける配慮を。歴史と日常が寄り添う空気感を味わえば、“馬橋”の二文字がぐっと身近になります。
3-5. 交通アクセス&タイムセーブ術(混雑回避の要点)
計画の骨子は「朝は人気地、午後は郊外」。ラッシュの谷間時間に移動し、主要駅では一駅手前で降りて歩くと混雑を避けやすくなります。各社寺で“開門・閉門・授与”の時間が異なるため、公式情報と路線アプリを併用して動線を設計しましょう。雨天は参拝者が少なく撮影もしやすい一方、石畳や木道が滑りやすくなるので、滑りにくい靴と折りたたみ傘を。書置き御朱印の折れ防止にA5クリアファイルは必携です。レースやイベント日は駅やバス停が混み合うため、到着・出発を15〜30分ずらすだけで体感が変わります。荷物は最小限、両手を空ける。財布・御朱印帳・スマホはすぐ出せる位置に。迷ったら“早めに出る・歩いてショートカット・並ぶ前に表示を読む”。この三つで、時間のロスが目に見えて減ります。
4. 授与品・御朱印・“馬”モチーフの楽しみ方
4-1. 馬モチーフの御守の意味と選び方
馬は古くから“機運の高まり”“前進”“脚の健やかさ”の象徴として語られてきました。御守の願意も、勝運、交通安全、健脚、道中安泰、仕事運など多彩です。選び方の基本は三点。第一に願いを一つに絞ること。日々の祈りが具体的になります。第二に身につけやすさ。財布や定期入れに入れる小型、鞄の内ポケット向きの袋型など、生活動線に合う形が長続きの秘訣です。第三に由緒の理解。いただいた社のご神徳や沿革を知っておくと、自然に感謝が深まります。持ち帰ったら直射日光と湿気を避け、清潔で高い場所に安置を。複数持つ場合は“相性”より“丁寧さ”が大事で、どれも粗末に扱わないこと。紐が切れた、汚れたといった時は買い替え時のサイン。感謝をこめて返納し、あらためて新しい一年を始めましょう。
4-2. 干支(午)関連の御朱印を見つけるコツ
干支モチーフの御朱印は、正月や干支年、祭礼期に頒布される例が多く、種類・期間・方法は社寺ごとに異なります。確実にいただくには、公式サイト・境内掲示・公式SNSの三点を直前に確認すること。直書きは待ち時間が読みにくいため、整理券の有無や最終受付時刻を先に押さえるのが賢明です。書置きの場合は、湿気と折れを防ぐA5クリアファイルが便利。お願いする際は、参拝後に静かに申込み、ページ指定や日付の伝達は簡潔に。郵送対応は例外で、現地授与が基本です。和暦・西暦の日付をメモしておくと記帳がスムーズ。なお、御朱印は“作品”ではなく“参拝の記録”。家での扱いも丁寧にし、定期的にページの反りや糊付けの具合を点検すると、長く良い状態を保てます。
4-3. 乗馬・競馬の安全祈願:祈祷の流れとマナー
乗馬の安全、競技の必勝、馬の健康長寿などの祈祷は、多くの社で受けられます。事前に公式案内で受付時間・初穂料・所要時間を確認し、当日は10分前を目安に到着。申込書に住所氏名と祈願内容を明記します。服装は清潔感のある普段着で十分ですが、境内では帽子を取り、通話機器の音を切るのが礼儀です。修祓ののち授与される御札やお下がりは、馬具の近くや目線より高い棚上などに丁寧に祀り、毎日一度は手を合わせましょう。返納の目安は一年。願意が成就したと感じたら感謝を添えて納めます。祈祷中の撮影可否は社ごとに異なるため、必ず事前に確認を。混雑時は席の詰め合いと静かな入退場を心がけるだけで、全体の雰囲気が大きく整います。小さな心配りが、祈願体験をより良い記憶に変えます。
4-4. “馬みくじ”や絵馬で楽しむ境内の小さな発見
馬の形をしたおみくじや、午年限定の意匠を取り入れた絵馬は、授与の有無やデザインが時期で変わることがあります。現地の掲示や公式情報で最新を確認し、その場のルールに従いましょう。撮影はまず参拝を優先し、通路をふさがない位置から。鳥居、神馬像、馬頭観音の石仏、社名板は定番の被写体ですが、台座に乗る、触れる、立入禁止の境界を越えるといった行為は避けます。広角寄りの画角で“周囲の空気”を入れると、場所の記憶が写真に宿りやすく、馬モチーフのかわいらしさも引き立ちます。おみくじは結ぶ場所が指定されることが多いので、案内に従って静かに結びましょう。絵馬は個人情報の集まりでもあります。他人の願いが読み取れる撮り方は控える。小さな配慮が、神仏と人への敬意になります。
4-5. 御守・御札の保管とお焚き上げの基本
御守・御札は、直射日光と湿気を避けた高い場所に安置します。神棚がなければ、清潔な棚上や玄関の上部などでかまいません。埃を払う習慣をつけると、毎日自然に手を合わせる時間が生まれます。古くなった御札・御守は、原則として授与を受けた社へ返納します。遠方で難しい場合は近隣社に相談し、年末から小正月に“どんど焼き”等で焼納する地域もあります。郵送返納に対応する社もありますが、可否や条件は社ごとに違うため事前確認を。燃えない素材の飾りや人形類は受け付けに制限があることも。何より大切なのは“感謝をこめて丁寧に扱う”ことです。紙袋に無造作に入れて放置するより、薄紙や清潔な布で包むだけでも、気持ちの整い方が違ってきます。扱いそのものが、信仰の姿勢を形にします。
5. 旅をもっと楽しく!グルメ・持ち物・撮り方・注意点
5-1. さんぽの合間に寄りたい甘味&カフェの選び方
参拝の合間に挟む休憩は、旅の満足度を左右します。浅草では仲見世の裏手や駒形橋近くの川沿いに、朝から開く和菓子店や喫茶が点在。府中ではけやき並木沿いのベーカリーや老舗の茶店、世田谷では農大通り周辺の気軽なカフェが歩きやすい距離にあります。選び方の軸は“人混みから半歩外す”。大通りから一本裏へ、開店直後やアイドルタイムを狙うだけで待ち時間が短くなります。持ち歩きしやすい最中や団子、焼き菓子は、御朱印帳やカメラと相性が良く、荷物を増やしにくいのも利点。飲食は境内を出てから行い、ベンチや公園で静かに楽しむのが作法です。水分補給はこまめに行い、夏場は塩分補給も意識。店内では席の譲り合いと短めの滞在を心がけ、地域の暮らしに敬意を払いましょう。
5-2. 御朱印帳とカメラの持ち物チェックリスト
| 持ち物 | 目的・ポイント |
|---|---|
| 御朱印帳・下敷き | 書置きの折れ防止にA5クリアファイルも用意 |
| 小銭(賽銭・初穂料) | 両替待ちを避け、静かに支払いできる |
| モバイルバッテリー | 公式案内や路線検索の確認に必須 |
| 折りたたみ傘・レインカバー | 石畳・木道の滑り対策、紙ものの濡れ予防 |
| ハンドタオル・除菌シート | 手水後の拭き取り、御朱印帳やカメラのケア |
| 予備マスク | 授与所や混雑エリアでの配慮に |
| クリップ・ミニ洗濯ばさみ | 書置き御朱印の仮固定や封入時の補助 |
| A5封筒・ジッパー袋 | 御朱印・案内紙の保護、雨天時の湿気対策 |
| 歩きやすい靴 | 滑りにくいソール、長時間歩行に適したもの |
一覧をスマホに保存し、出発前にチェックすれば忘れ物が減ります。荷物は最小限、両手を空ける配置に。財布・御朱印帳・スマホはすぐに取り出せるポケットへ。これだけで参拝も撮影もスムーズになります。
5-3. 季節・天気別の服装アドバイス(雨・猛暑・寒波対策)
夏の参道は照り返しが強く、体感温度が上がります。つば広の帽子、通気性のよい長袖、首元を守る薄手の布、こまめな水分と塩分補給で熱対策を。冬は北風が抜ける場所が多いので、首・手首・足首を温める重ね着が効きます。雨の日は滑りにくいソールと撥水アウター、バッグのレインカバーが安心。紙類を守るA5ファイルは必携です。どの季節でも“両手が空く”装いが基本。軽量のショルダーやウエストバッグにまとめ、上着の内ポケットに御朱印帳を入れて取り出しやすく。石段や玉砂利を歩くことを想定し、靴はクッション性とホールド感を重視。汗や雨で冷えた体は、温かい飲み物でこまめにリセット。無理をしない計画が、最後まで心地よく歩き切る最大のコツです。
5-4. SNSで映える撮り方:鳥居・石仏・街角サインのコツ
鳥居は正面だけでなく、わずかに斜めから“額縁”のように空や樹々を入れると立体感が出ます。神馬像や馬頭観音の石仏は、目線の高さを合わせて敬意を示すアングルを。地名サイン(駒形・馬喰町・馬込など)は、道路の奥行きや交差点の広がりを取り入れると、その土地らしさが伝わります。人が映り込む場合は顔が特定できない角度を選び、絵馬の個人名や授与所の掲示は写さない。露出は一段明るめにして社殿の黒つぶれを防ぎ、広角では垂直を意識して歪みを抑えると、落ち着いた一枚になります。朝夕の斜光は立体感が増す時間帯。混雑を避けて撮るなら、開門直後や閉門前の数十分が狙い目です。撮る前に一礼して周囲を見渡し、場の流れを止めない。これだけで写真の印象も旅の印象も良くなります。
5-5. 写真マナーと注意事項(参道・本殿・周辺住民への配慮)
参道は“歩く人が優先”。三脚や自撮り棒は混雑時に使わない、または使用可否の掲示に従うのが原則です。祈祷・祭礼・読経の最中は撮影を控え、神職・僧侶・参拝者が写る場合は許可を得ます。住宅街に隣接する社寺が多いため、早朝・夜間の大声、長時間の立ち話は避けましょう。石仏や社殿、植物に触れる、立入禁止区域に入る、ドローンを飛ばすといった行為は厳禁。わからないことは社務所や掲示で確認し、それでも不明なら“やらない”のが最善です。境内は誰かの祈りの場であることを忘れず、静かに歩いて静かに去る。小さな所作の積み重ねが、次に訪れる人の心地よさを守ります。写真は記録であり、場との対話でもあります。ルールと敬意を土台にすれば、時間が経つほど価値の増すアルバムになります。
まとめ
東京の“馬”ゆかりをたどると、地名、社寺、石仏、そして競馬や馬術といった現代文化までが一本の線でつながります。浅草・駒形では、馬頭観世音菩薩を安置する駒形堂から浅草寺へと歩き、江戸の水上交通の記憶に触れる。府中では、武蔵国の総社・大國魂神社と東京競馬場を行き来して、信仰と現在のホースカルチャーの両面を体験する。世田谷の馬事公苑では、リニューアルされた施設のもとで“馬と過ごす時間”の穏やかさを味わい、杉並の馬橋稲荷では龍の鳥居と「東京三鳥居」という通称に地域の誇りを見る。参拝作法や御朱印の心得、写真マナーを押さえておけば、午年生まれでなくても十分に楽しく、学び深い一日になります。静かに、丁寧に、感謝を胸に。一歩ずつ歩けば、馬の力強さのように、旅も人生も前へ進んでいきます。


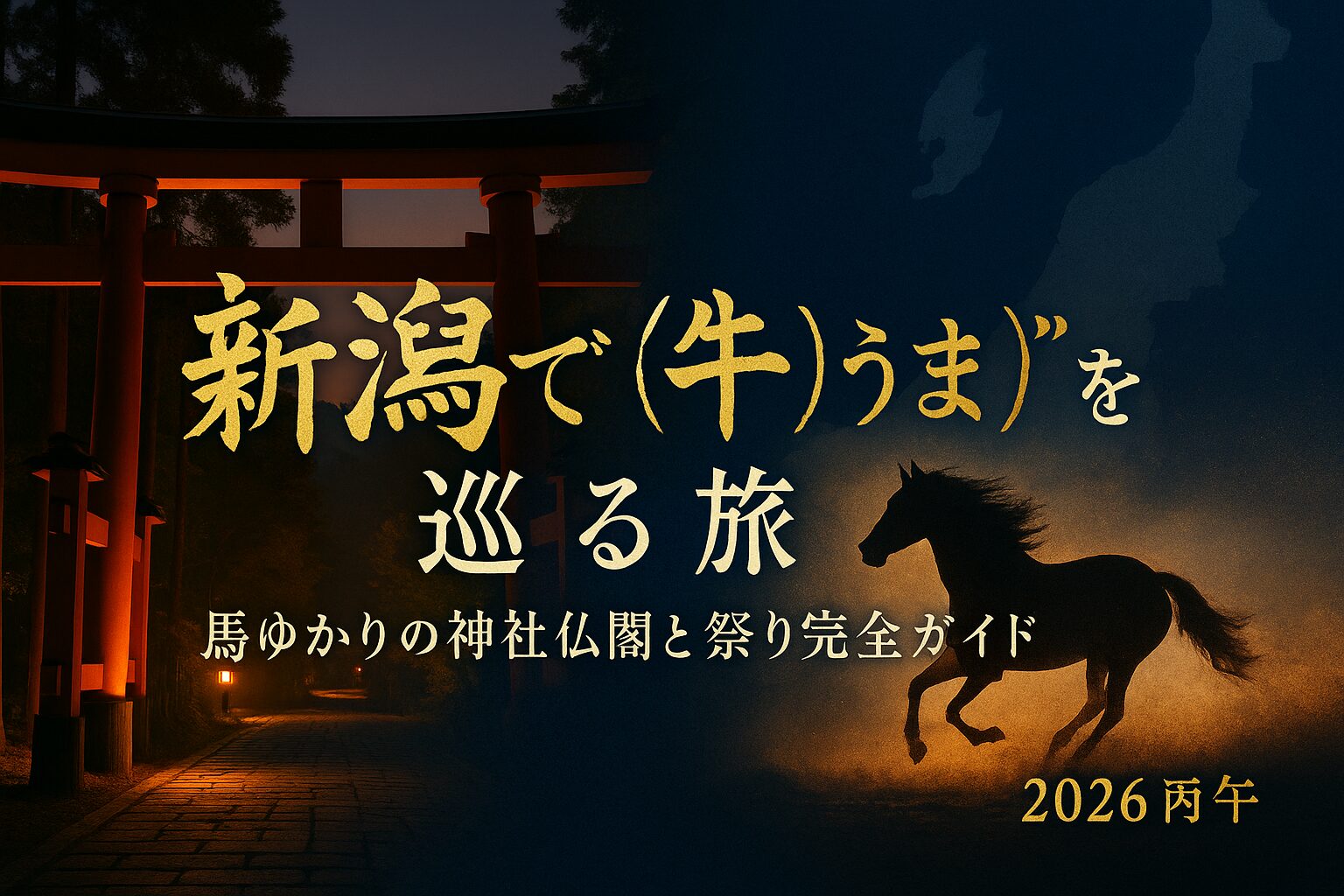

コメント