1. 甲斐(山梨)と「うま」の深い関係を知る

「午年だから」「馬が好きだから」。その気持ちだけで旅先を決めていい。山梨には、名馬伝承や武家の歴史、街道の石仏、そして今に続く流鏑馬や騎馬行列があります。富士北麓、甲府、峡南—互いに距離はあるものの、テーマを「うま」と決めれば一本の道でつながります。本記事は、伝承と資料のバランスに気を配り、事実に基づいて計画できるようにまとめました。最後にもう一度。出発前の公式確認、安全第一の観覧、そして土地への敬意。この三つがそろえば、あなたの山梨“うま旅”はきっと実りある一日になります。
甲斐の黒駒とは?古代から続く名馬伝承のキホン
山梨(旧・甲斐国)は、古くから良馬の産地として語られてきました。なかでも「甲斐の黒駒」は、黒毛の名馬として広く知られる伝承です。物語では、黒駒が都や富士山と関わる場面が多く、聖徳太子の説話や富士山信仰と結びつく話型も見られます。もちろん民間伝承なので史実と同一視はできませんが、古代から甲斐が牧(まき)=放牧・育成の場を持っていたこと、物流や交通の要地だったことを示す象徴的な“記憶の器”と考えると理解しやすいでしょう。旅の途中で「駒」「黒駒」「牧」といった地名に出会ったら、近くに古道や水場、峠があるか地図を確認してみてください。地名は当時の暮らしの痕跡です。地域の資料館や図書館の郷土史コーナーをのぞくと、黒駒に限らず、馬に関わる行事や社寺の由緒が見つかり、土地の物語が立体的に見えてきます。
武田家と弓馬の文化:戦国の武と馬のつながり
戦国期の甲斐といえば武田氏。軍事・交通・地形の視点で見ると、甲州は峠越えや河川の渡渉が多く、機動力の高い兵が求められました。記録や伝承の中で、武家の教養としての弓術・乗馬が重んじられていたことは確かで、合戦図屏風や社寺の由緒にもその空気が残ります。武田八幡宮(韮崎)は武田氏発祥とされる古社で、のちに武田晴信(信玄)が社殿再建に関わった旨が棟札に記されています。こうした史料は、武田氏が単に戦に強かっただけでなく、祈りと武、そして馬をめぐる文化を大切にしていたことを示します。甲府から韮崎にかけては、神社・古跡・資料館が密に点在し、徒歩とバスでも回れるスケールです。弓馬に触れられる場所を線でつなげば、戦国の甲斐の姿が自然に見えてきます。
甲州街道に残る馬頭観音の石造物を読み解く
旧街道沿いで見かける「馬頭観音(ばとうかんのん)」は、運搬や旅で働いた馬の守護、また亡くなった馬への供養を意味する石仏です。甲州道中は坂や峠が多く、荷駄を曳く馬には厳しい区間もありました。そのため難所や分岐、橋のたもとなどに馬頭観音が祀られ、行き交う人々が手を合わせてきました。石塔の形や刻字、年号をよく見ると、その土地の事故や工事、講中の名前がわかることもあります。写真に収める場合は、石仏に直接触れず、私有地や畑地に無断で立ち入らないことが基本です。苔や風化は歴史そのものなので剥がしたりこすったりしないでください。道端の小さな祠でも、地域の方が清掃や修繕を続けて守っています。静かに礼をして、次の一歩に向かいましょう。
「午(うま)」の干支をやさしく整理:方角・相性・縁起の考え方
干支の「午」は十二支で南を司り、季節では夏、五行では「火」に配されます。これらは暦や方位の伝統的な考え方で、古来の時間感覚とも結びついています。いっぽう、相性に関する見立ては民間信仰・占術上の説明です。一般的には「寅・午・戌の三合」「午・未の六合」などの言い回しがあり、活発さや勢いの象意が語られます。ただし科学的根拠を示すものではありません。旅の計画で「午の日に参拝」「南を意識する」といった楽しみ方は、あくまで気分を上げるスパイスとして取り入れるのがよいでしょう。社寺では馬を描いた絵馬や、馬を意匠にしたお守りが手に入ることも多く、午年生まれの人には特別な記念になります。由緒や文化財の説明板と合わせて読むと、干支の記号が土地の歴史と自然につながって見えてきます。
山梨に点在する“馬”地名・伝承の見つけ方
旅先で「駒」「馬」「牧」「鞍」「飼」などの字が付く地名を見つけたら、周辺に古い牧場跡や道の分岐、河川の渡し場がないか地図と地形をチェックしてみましょう。たとえば「駒形」「黒駒」「馬場」「牧丘」などは、馬の放牧、訓練、あるいは神事・競馬の場を示すことがあります。観光案内所の郷土資料、自治体の文化財データベース、神社の由緒掲示は、情報の入口に最適です。地元の方に昔の道や祭りの話をうかがうと、地名と社寺、石塔の位置関係が一気につながります。フィールドノートを作り、見つけた石仏の位置や刻字をメモしておくと、あとで調べ直すときに役立ちます。伝承は地域ごとに少しずつ違うため、複数の資料を読み合わせ、「今語られている形」を尊重する姿勢が旅を豊かにします。
2. 祭りで体感!山梨の“馬神事”カレンダー
富士吉田・小室浅間神社の流鏑馬祭りを楽しむ
富士吉田市の冨士山下宮小室浅間神社では、例年9月18・19日に「流鏑馬祭り例祭」が行われます。一般的な流鏑馬は馬上から的を射る競射に注目が集まりますが、ここでは、馬が走り去った後の蹄跡で吉凶を占う「馬蹄占い」が大きな特色です。神社前の通りを疾走するため、迫力を間近で体感できます。この神事は市の無形民俗文化財にも位置づけられており、地域が世代を超えて継承してきた宝といえるでしょう。見学の際は、誘導員や氏子さんの案内に従い、フラッシュ撮影や大きな音を避けるのが基本です。沿道では馬の進路をふさがない立ち位置を選び、子ども連れは手を離さないよう注意しましょう。日程や交通規制は年により変わることがあるため、出発直前に神社や市の最新情報を確認しておくと安心です。
富士河口湖・甲斐の勝山やぶさめ祭りの見どころ
河口湖畔で行われる「甲斐の勝山やぶさめ祭り」は、冨士御室浅間神社の神事として伝わる行いで、由来は900年以上前にさかのぼるとされています。武者装束の射手が疾走する馬上から矢を放ち、次々と的を射抜く姿は、春の湖畔の風景と相まって独特の臨場感を生みます。主会場となるのはシッコゴ公園周辺で、見通しがよく撮影にも適していますが、観覧エリアと馬の走路はロープで明確に区切られます。安全のためロープ内に入らない、フラッシュを使わない、ペット同伴は会場ルールに従うなど、観覧マナーを守りましょう。開催日や運営方式は年によって見直しが入ることがあるため、町や神社の公式発表で最新の案内を必ず確認してください。駐車場は混雑しやすいので、公共交通と徒歩の組み合わせも検討すると動きやすくなります。
甲府・武田二十四将騎馬行列の迫力を味わう
甲府市では、武田信玄の命日である4月12日前後に、武田神社の祭礼とあわせて「武田二十四将騎馬行列」が行われます。甲冑姿の隊列が市内を練り歩き、馬上の武者と旗指物が春の街を彩ります。コースや開始時刻、交通規制は年ごとに更新され、駅周辺や舞鶴城公園前など、観覧のしやすいポイントが設定されます。見学のコツは、直線コースの先端や交差点の曲がり角など、動きが生まれる場所を早めに確保すること。人出が多い年は最前列が埋まりやすいので、開始の1時間前には現地入りしたいところです。馬は音や光に敏感ですから、笛や拍子木、フラッシュは控えましょう。最新のコース図や当日の運行状況は市や観光協会の公式情報で直前に確認し、誘導員の指示に従って安全に楽しんでください。
祭り見学のマナーと安全ポイント:馬と人の距離感ガイド
どの神事でも、馬と人の安全を守る基本は同じです。まず、ロープや柵の内側に入らないこと。撮影は観覧エリアから行い、三脚や自撮り棒は通行の妨げにならない位置に限定します。フラッシュや突然の大声、鳴り物は避けましょう。子どもは抱き上げるか手をつなぎ、ベビーカーは走路から離して待機します。ペットを連れて行く場合は会場ルールを必ず確認し、鳴き声や臭いに配慮します。飲食物を馬に近づけたり、無断で触れたりすることも厳禁です。誘導員や氏子の案内に従えば、危険を避けられるだけでなく、進行のリズムも理解でき、神事への敬意が自然に身につきます。イベントは天候や安全の都合で内容が変更されることがあるため、プランには時間と移動の余裕を持たせると安心です。
ベスト撮影スポット&時間帯のコツ
流鏑馬は、射手が弓を引き切る「的の先」を狙うと決定的瞬間を捉えやすくなります。午前の順光はシャープに、午後の斜光は立体感が出るので、天候と太陽の位置を事前に確認しましょう。シャッタースピードは速め(目安1/1000秒程度)から試し、連写で歩留まりを上げます。スマホの場合はバースト撮影と軽い露出補正が有効です。騎馬行列は、直線通りの終端や交差点での曲がり角が狙い目で、旗指物や槍先が画面にリズムをつくります。背景に山並みや城跡、鳥居が入る位置を早めに見つけておくと、土地らしさのある写真になります。いずれも安全柵を越えない、周囲の視界を妨げない位置取りを守ることが最優先です。祭りは人が主役であり、記録はその次。現地のルールに沿って、心地よい撮影を心がけてください。
3. 馬の神さまを祀る社寺をめぐる
南巨摩郡・駒形神社:地名に刻まれた“駒”の信仰
南巨摩郡南部町の駒形神社は、その名からもわかるように「駒(馬)」との縁を感じさせる小社です。里山の斜面に寄り添うように鎮座し、境内は凛と静か。旅の安全や五穀豊穣を祈るのにふさわしい雰囲気が漂います。周辺には古道や小さな石仏が点在し、散策がてら道端の祠や刻字をたどると、地域の人々が馬とともに暮らしてきた気配が伝わってきます。参拝では、鳥居で一礼、手水、拝殿で二拝二拍手一拝の作法を丁寧に。撮影は他の参拝者へ配慮し、社殿や石碑に触れないのが基本です。駐車や通行は地域の生活道路にあたることが多いため、路上駐車は避け、指定場所を確認しましょう。大きな社ではありませんが、地名と祈りが直に結びつく好例として、旅程に静かな深みを与えてくれるはずです。
馬頭観音に手を合わせる:交通安全・旅の守り
馬頭観音は、観音菩薩が馬の守護の姿で現れたとされる信仰で、運搬や耕作、旅で働いた馬への感謝と供養の象徴です。山梨の旧街道や峠道には、石塔や小祠の形で各所に祀られています。現地では、まず足元に注意し、苔むした石段や側溝を踏み外さないように進みましょう。参拝は静かに一礼し、線香やろうそくは地域の管理方法に従い、むやみに使用しないのが礼儀です。写真撮影では、石仏に寄りかかったり、苔をこすったりしないこと。刻まれた年号や寄進者名を読むと、その場所の歴史が具体的に立ち上がってきます。ドライブ旅の途中でも、旧道の分岐や峠の手前に小さな祠を見つけることがあります。交通安全を祈り、無理のない計画で次の目的地へ向かいましょう。
武田ゆかりの社で弓馬の気配にふれる(石和八幡宮・武田八幡宮)
笛吹市の石和八幡宮は、中世に石和五郎信光が鎌倉の鶴岡八幡宮を勧請・合祀したと伝えられ、甲斐源氏の氏神として崇敬されてきました。いっぽう、韮崎の武田八幡宮は武田氏発祥の社とされ、保延6年に龍光丸(のちの武田信義)が元服したと伝わります。戦国期には武田晴信(信玄)が大檀主となって社殿を再建したことが棟札に記録され、甲斐の武と祈りの結びつきを今に伝えます。両社を合わせて巡ると、甲斐源氏から武田氏へ続く時間の流れが見えてきます。参拝では、境内の由緒書きや文化財解説を丁寧に読み、史実と伝承のどちらも大切に扱う視点を持つと、土地の歴史が穏やかに体に入ってきます。周辺には資料館や古跡もあるため、徒歩と公共交通を組み合わせれば、無理のない半日コースを組めます。
浅間の神と馬:小室浅間・冨士御室浅間の“馬”縁を知る
富士北麓に鎮座する浅間の神々は、火山と水の恵みを司るとされ、古来より人々はその力に感謝し、畏れを抱いてきました。小室浅間神社の流鏑馬祭りは、その信仰が馬の神事と重なって伝わってきた代表例です。河口湖の冨士御室浅間神社は、富士山中最古と伝わる古い歴史を持ち、世界文化遺産の構成資産にも含まれます。春の「甲斐の勝山やぶさめ祭り」は、同社の神事として長く継承されてきました。どちらも、富士山を仰ぎつつ、人と馬と神が出会う場所です。境内では社殿の彫刻や摂末社、古い石碑に目を向けてみてください。馬にちなんだ意匠や、奉納者の名前、年号が残ることがあります。参拝の最後に、旅の無事とともに、日々の安全や学業、仕事の成就を静かに祈れば、短い滞在でも満足感の高い時間になります。
絵馬の由来と奉納の作法:願いを“馬”に託す
「絵馬」は、もともと神に馬(神馬)を奉納して祈願した古い風習が、木や土で作られた馬の像へ、さらに板に馬の絵を描いた札へと変化していったものと説明されます。のちに祈願の対象は馬に限られず、多様な図柄が生まれましたが、語源は今も「馬」に残っています。奉納の作法はシンプルです。授与所で絵馬を受け、願い事やお礼を丁寧な言葉で書き、紐を結んで所定の掛所へ。人の個人情報が映らない配慮をして写真を撮るなら、全体を引き気味に収めるとよいでしょう。馬に関わる神社では、馬を描いた絵馬や馬蹄をかたどったお守りが置かれていることもあります。午年生まれの人や、乗馬・競馬が好きな人には、旅のしるしとして心に残る授与品になります。帰宅後は、叶った願いを覚えておき、次の参拝でお礼を伝える心持ちを大切にしましょう。
4. 午年・午の日に巡るおすすめモデルコース
【富士吉田】流鏑馬と下吉田さんぽコース(小室浅間神社中心)
下吉田駅を起点に、商店街の昭和レトロな通りを抜けて小室浅間神社へ向かいます。参拝のあと、社前の通りと馬場の位置関係を歩いて確認しておくと、祭礼日に再訪したときの見学がスムーズです。境内の由緒や文化財の掲示を読み、馬蹄占いの流れも頭に入れておきましょう。昼は地元のうどん店で腹ごしらえ。午後は富士山の見え方がよい路地や高台を歩き、夕方の斜光で社殿や鳥居を撮ると陰影が美しく出ます。流鏑馬祭り当日は、人出が多く沿道に規制がかかることがあるため、開始1時間以上前の現地入りが安心です。帰路は駅前で土産を揃え、混雑のピークを避けて移動する計画を。最新の開催可否、交通規制は神社・市の公式発表で確認してください。徒歩中心でも無理のない距離感で、ゆっくり町の空気を味わえるコースです。
【河口湖】勝山やぶさめ×冨士御室浅間神社で神話と馬を感じる
午前は冨士御室浅間神社の里宮を参拝。社殿の彫刻や石鳥居、由緒の掲示を丁寧に読み、富士信仰の歴史を体に入れます。その後、湖畔へ出て「甲斐の勝山やぶさめ祭り」の会場となるシッコゴ公園周辺を下見。走路の位置、観覧エリア、背景となる富士山や湖面の見え方を確認しておくと、当日の立ち位置が迷いません。開催日には、馬の進路をふさがないように余裕ある到着を心がけ、フラッシュや大声を避ける基本マナーを徹底します。観覧後は、河口湖周辺で地元の食堂や道の駅に立ち寄り、山梨の果実や加工品を味わってください。時間に余裕があれば、世界遺産の構成資産に関する展示も見学を。帰路は渋滞を避けるため、バスや鉄道の時刻表を事前に確認し、混雑のピークを外す計画が有効です。
【甲府】武田神社と市内パレードで“騎馬の都”を歩く
朝は武田神社へ。宝物殿で武田氏に関する展示を見学し、境内の案内板で由緒を確認します。昼前に市街地へ移動し、武田二十四将騎馬行列のコース上で観覧ポイントを確保。直線通りの終端や曲がり角は、隊列のリズムが出るためおすすめです。昼食は甲府駅周辺で、郷土のほうとうや甲州ワインビーフの定食を。午後の行列では、馬の進路や誘導員の案内を最優先に守り、撮影は観覧エリアから短時間で行います。終了後は舞鶴城公園で桜や石垣を楽しみ、温泉施設に寄って足を伸ばすと疲れがやわらぎます。最新のルート・交通規制は市の公式発表を参照し、時間に余裕を持った計画を。夜は甲府駅前で土産の手配をして、混雑を避けて帰路へ。徒歩と公共交通で完結できる、初めての人にも安心の一日です。
【南部〜身延】駒形神社と身延エリアで静かな祈り旅
甲府盆地のにぎわいから離れ、峡南エリアへ。南部町の駒形神社を参拝し、里山の静けさの中で旅の無事を祈ります。車の場合は事前に駐車場所を確認し、徒歩の場合はバスの本数を調べて無理のない行程を組みましょう。参拝後は、身延方面へ向かい、道端の小さな祠や石仏を訪ねます。馬頭観音や道標など、生活に根づいた石造物を丁寧に見て回ると、土地の記憶が少しずつほどけていきます。昼食は川魚や山の幸を出す食堂で、午後は日帰り温泉でひと休み。帰りの交通手段と時刻に余裕を持たせ、日没前に移動を始めると安心です。華やかな祭礼とは別の、静かな祈りの旅。地名と景観、祈りが自然に結びつく体験は、翌日以降も心に残るはずです。
御朱印・御守の集め方:馬モチーフを見つけるコツ
馬にゆかりのある社寺では、御朱印やお守り、絵馬に馬や矢、蹄鉄などの意匠が見られます。授与所では「馬にちなんだ授与品はありますか」と一言そえて尋ねると、季節限定や祭礼限定の品を案内してもらえることがあります。御朱印は参拝前に帳面を預け、混雑時は待ち時間を見込んで行動を。書置き対応の日もあるので、クリアファイルを携帯すると折れや汚れを防げます。保管はビニールカバーや専用袋に入れ、直射日光や湿気を避けましょう。写真を撮る際は、他の参拝者の個人情報が写り込まないよう配慮を。旅のテーマに合わせ、富士山や武田菱と組み合わせた馬デザインの御朱印帳を選べば、山梨ならではの一冊になります。最新の頒布情報は公式の案内で確認するのが確実です。
5. 旅の準備と実用メモ(アクセス・季節・持ち物)
交通アクセス早見:甲府・富士五湖エリアの拠点選び
山梨を効率よく回るなら、拠点は大きく「甲府」と「富士吉田・河口湖」に分けると組みやすくなります。公共交通では、甲府方面はJR中央本線、富士北麓は富士急行線が基幹です。車の場合は中央自動車道と東富士五湖道路が主な動脈で、休日は渋滞が発生しやすいので、往路・復路の時間帯をずらすと快適です。祭礼日は臨時駐車場や交通規制が敷かれることがあり、会場に近いエリアは早い時間に満車になります。駅前駐車場+徒歩、または離れた駐車場+シャトルバスを前提にすると、計画がぶれません。小室浅間の流鏑馬、勝山やぶさめ、甲府の騎馬行列はいずれも毎年運営が見直されるため、直前の公式告知が最も確実です。
| エリア | 主要拠点駅 | 主な見どころ | 移動のコツ |
|---|---|---|---|
| 甲府 | 甲府駅 | 武田神社、舞鶴城公園、騎馬行列 | 駅前ベースで徒歩+バス |
| 富士吉田 | 下吉田・富士山駅 | 小室浅間神社、流鏑馬祭り | 早着で沿道確保、徒歩回遊 |
| 河口湖 | 河口湖駅 | 冨士御室浅間神社、やぶさめ | 湖畔渋滞に注意、時刻表確認 |
祭り当日の混雑・駐車対策と服装のポイント
祭り当日は、開始の1時間以上前に現地着が理想です。最前列は想像以上に早く埋まります。服装は歩きやすい靴と両手が空くリュック。春先と秋口は寒暖差が大きいので、薄手のウインドブレーカーを重ね着に。日差しが強い日は帽子と日焼け止めを。小雨や砂埃への備えとして、スマホやカメラを入れる簡易防水袋があると安心です。車の場合は、会場から距離のある駐車場に停める前提で動くと、帰りの混雑を避けやすくなります。公共交通派は、復路の最終便を事前にメモ。トイレの場所、待ち合わせの目印、万一のはぐれ対策も決めておくと安心です。天候急変や運営判断で内容が短縮・変更されることもあるため、柔軟なプランを心がけましょう。
馬にやさしい見学マナー:フラッシュ・音・距離の基礎知識
馬は音と光に敏感です。フラッシュ撮影や突然の大声、笛や拍子のような鋭い音は避けます。観覧エリアの最前列では、可能ならしゃがんで後列の視界を確保し、子どもは抱き上げるか手をつなぎましょう。ロープや柵の内側に手や三脚を出さない、食べ物を近づけない、無断で触れないことも基本です。ペット同伴は会場のルールに従い、吠えやすい場合は距離を取りましょう。誘導員や氏子の指示は安全確保のためのものですから、必ず従ってください。撮影のために無理な場所取りをせず、人と馬の動線を尊重する姿勢が、祭り全体の心地よさをつくります。行事は地域の方々の努力で成り立っています。感謝の気持ちで場を共有することが、何よりのマナーです。
写真・動画の撮り方講座:流鏑馬をブレずに撮るコツ
流鏑馬はスピードが速いため、シャッタースピードは1/1000秒程度から試し、被写体ブレを抑えます。AFは追従設定、手ブレ補正はオン。スマホはバースト撮影を活用し、白飛びを避けるために露出をやや下げましょう。狙う位置は、馬と射手の動きが揃う「的の少し先」。フレーミングに余白を取り、背景に鳥居や山並みが入る角度を選ぶと、土地の記憶が写真に宿ります。騎馬行列は、交差点での方向転換や道幅が広がる地点で、旗や槍先に動きが出る瞬間が狙い目です。動画は横位置、肘を体に付けて固定し、短いクリップを重ねると編集しやすくなります。三脚は通行の邪魔にならない場所で短時間のみ使用。いずれも安全が最優先で、会場ルールに従ってください。
ほうとう・郷土グルメ&温泉を“馬旅”にプラス
見学の合間や帰路には、地域の食と湯を組み合わせましょう。甲府盆地では、かぼちゃや根菜を煮込んだ「ほうとう」が体を温め、富士北麓ではコシの強い「吉田のうどん」がエネルギー補給に最適です。デザートには信玄餅のソフトクリームや季節の果実を使ったスイーツもおすすめ。温泉は、富士山の眺望を楽しめる施設から、町の共同浴場まで種類が豊富です。祭りの後に湯で汗を流すと、移動の疲れがすっと抜け、旅の満足度が一段上がります。営業時間や定休日は季節で変わるため、公式情報で事前に確認しましょう。土産は馬や蹄鉄をモチーフにした小物、甲州ワインや甲斐の地酒など、テーマに沿って選ぶと記憶に残ります。食・湯・土産の三点をうまく配すると、旅は最後まで気持ちよく締まります。
まとめ
山梨には、名馬伝承「甲斐の黒駒」、武田氏の歴史、甲州街道に残る馬頭観音、そして今に続く流鏑馬や騎馬行列まで、馬にまつわる要素が濃く息づいています。本記事では、伝承と史料の境目を大切にしながら、確かな事実を基礎に旅のヒントを整理しました。ポイントは三つ。第一に、祭礼や交通は毎年見直しが入るため「直前の公式情報確認」を欠かさないこと。第二に、馬と人の安全を守る「観覧マナー」。第三に、地名・石造物・由緒など“小さな手がかり”を拾う観察眼です。午年に合わせて巡るもよし、季節の行事に合わせて再訪するもよし。神社仏閣と馬の物語を心地よい歩幅でたどれば、山梨の風景はより深く、やさしく立ち上がってきます。


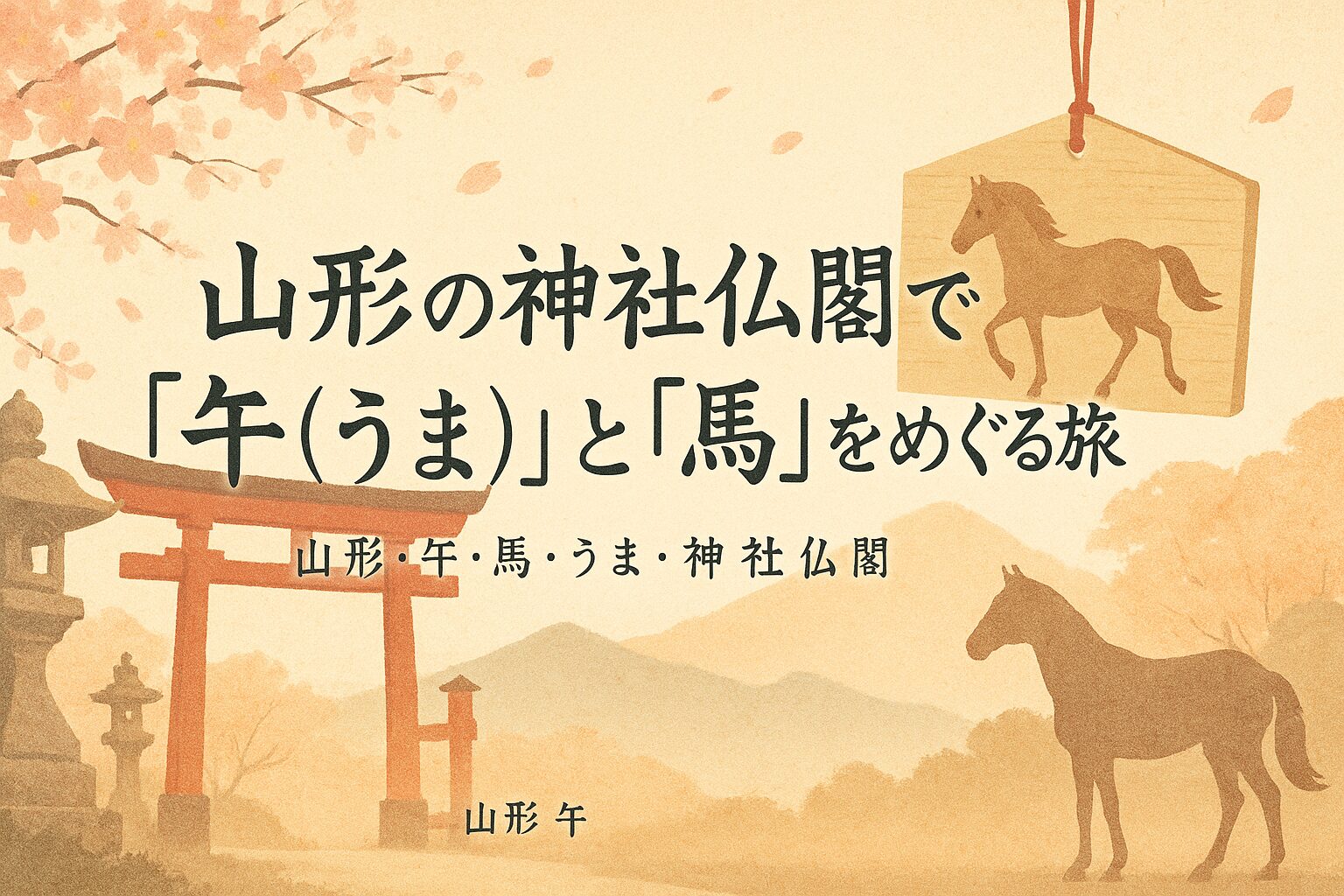

コメント