三重県と「馬」のつながりをやさしく解説

「三重で馬に出会う旅」は、派手な観光とは少し違う静かな豊かさがあります。多度の勇壮な上げ馬、伊勢の凛とした神馬、旧街道にひっそり立つ馬頭観音。どれも声高に語らないのに、心の奥で長く響きます。本記事は、初めての方でも迷わず楽しめるよう、見どころ・回り方・実用情報を丁寧にまとめました。安全とマナーを大切に、歴史に寄り添いながら、馬の気配をたどる旅へ出かけましょう。
上げ馬神事ってなに?
三重県桑名市の多度大社で毎年5月初旬に行われる多度祭では、若者と馬が一体となって斜面を駆け上がる「上げ馬神事」が大きな見どころです。開始は例年午後2時ごろで、本祭(5月5日)は年や当日の構成により5回または6回という運用が続いています(公式ページ内でも年度により5回表記と6回表記が並存するため、直前の公式告知で要確認)。また前日(5月4日)は午後1時ごろから10回行われるのが通例です。2024年には安全対策として従来の急な土壁を撤去し、勾配を抑えたコースへと大きく変更されました。2025年もこの方式を継続し、ムチ不使用、路面への砂の敷設、胴綱の使用廃止など、馬と人の安全を重視する運営が明確になっています。見学者にはロープ内立ち入り禁止、フラッシュ自粛、指示への協力が呼びかけられます。上げ馬は単独イベントではなく、神輿渡御や御旅所の神事、流鏑馬などがつながる祭礼全体の一部であることも覚えておきたいポイントです。出かける前にその年の回数・進行・観覧エリアを公式で確認し、当日は早めの到着・暑さ寒さ対策・水分の携行を心がけましょう。
伊勢神宮と神馬のこと
伊勢神宮には神に奉仕する神馬(しんめ)が奉納されており、内宮・外宮どちらにも御厩(みうまや)が設けられています。特に注目されるのが、毎月1日・11日・21日の朝8時ごろに神馬が正宮へ向かう日が設けられている点です(天候・神馬の体調・行事の都合で中止や時間変更あり)。この時間帯に宇治橋付近や内宮参道で静かに待てば、厳かな空気のなかを進む神馬に出会えることがあります。神馬は観賞用ではなく、神さまにお仕えする尊い存在。手を伸ばしたり、フラッシュを焚いて驚かせたりするのは厳禁です。境内マップで御厩や動線を事前に確認しておくと、当日迷いません。伊勢参りは外宮→内宮の順がならわし。早朝の清浄な時間に参拝すれば、一日の心が自然と整います。
馬頭観音を知ろう
「馬頭観音(ばとうかんのん)」は、馬や旅人、運搬に関わる人びとの安全を守ると信じられてきた仏さまです。江戸時代に街道整備と物流が発展すると、往来の要衝や集落の入口、峠道の要所に石仏や小祠が数多く建てられました。三重県でも旧東海道や伊勢参宮街道、熊野古道に接する地域を中心に広く分布します。たとえば紀北町・前村の和歌山別街道沿いには小祠内に馬頭観音が祀られており、かつて馬子や駕籠かき、荷継ぎの拠点があった歴史の痕跡を今に伝えています。観光パンフレットに載らない素朴な祠も多く、旅の途中でそっと手を合わせると土地の暮らしに触れられる感覚が残ります。撮影の際は民家や私有地に配慮し、扉が閉まっている場合は無理に開けないこと。地域の信仰に敬意を払う姿勢が、心地よい旅の鍵になります。
旧街道と馬の歴史(鈴鹿峠など)
東海道最大級の難所として知られる鈴鹿峠と、その西麓に広がる関宿は、江戸時代に人と物が絶えず行き交った交通の動脈でした。険しい峠越えでは馬の力が不可欠で、荷継ぎや休憩のための馬屋・問屋場が発達。関宿では今も約1.8kmにわたり江戸期の町並みが連続して残り、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。軒の連なりや格子戸の陰影、道端の道標や石仏に目を凝らすと、往時の旅人や馬の息づかいが浮かび上がってくるはず。鈴鹿峠へ伸びる旧道では、石畳や一里塚、路傍の祠に出会えるハイキングも人気です。坂道が多いので、滑りにくい靴と飲料、雨具は必携。歴史のレイヤーが重なる景観は歩く速度でこそ味わい深く、馬に守られた旅の記憶を丁寧にたどらせてくれます。
参拝の基本マナーと豆知識
初めてでも迷わないよう、基本の流れを覚えておきましょう。鳥居の前で一礼し、参道は中央を避けて端を歩きます。手水舎では左手・右手・口を清め、柄杓は戻す前に柄を流す所作が美しいとされています。拝礼は神社なら二拝二拍手一拝、寺院では静かに合掌が一般的。御朱印は参拝後にお願いするのが礼儀で、混雑時は時間にゆとりを。馬や神事を見学するときはフラッシュ禁止・ロープ内立ち入り禁止・誘導への協力が必須です。路上駐車や私有地への無断立ち入りは厳禁。伊勢や多度は混雑しやすいため、早朝・平日を選ぶと快適に過ごせます。季節に応じた服装と水分補給、歩きやすい靴を忘れずに。
絶対行きたい名所ベスト5
多度大社(桑名市):上げ馬神事の舞台
北勢を代表する古社・多度大社は、別名「北伊勢大神宮」とも称される崇敬の篤い神社です。上げ馬神事は午後2時ごろ開始、5月5日は年や当日の構成により5回または6回の実施で進み、5月4日は午後1時ごろから10回が目安です。2024年以降は安全対策として急斜面を廃し、緩やかなスロープで斎行。2025年もこの方式で、ムチ不使用・砂の敷設・胴綱廃止などの運用が周知されています。アクセスは養老鉄道「多度」駅から約1.5km(徒歩15〜20分)。車なら東名阪自動車道・桑名東ICから約10分。駐車は境内横に無料枠(台数限りあり)、階段下や周辺に有料を含む複数の駐車場が案内されています。参拝は原則24時間可能、授与所の対応は9:00〜17:00が目安。祭礼日程や交通規制は毎年変わる可能性があるため、直前に公式のお知らせを必ず確認しましょう。
伊勢神宮(伊勢市):神馬に会えるかも?
伊勢神宮は外宮→内宮の順で参るのがならわし。内宮・外宮ともに御厩があり、毎月1・11・21日の朝8時ごろに神馬が正宮へ向かう日があります(中止・変更あり)。この時間帯の内宮は、宇治橋から神楽殿周辺までの動線が静けさに包まれ、神馬の蹄の音が境内に響く特別なひととき。撮影はフラッシュ禁止、道をふさがない、神職の指示に従うのが最低限のマナーです。車で訪れるなら内宮周辺の伊勢市営駐車場が便利。昼間入庫は最初の1時間無料、1〜2時間500円、以後30分ごと100円という分かりやすい料金体系です。名古屋方面からは近鉄特急で最短約1時間20分。朝の奉仕を狙うなら前泊が安心です。
椿大神社(鈴鹿市):道ひらきと交通安全の神さま
猿田彦大神の総本宮として知られる椿大神社は、「みちひらき」の御神徳で信仰を集めます。人生の岐路やドライブ旅の安全を願う人に向き、交通安全・旅行安全・方位除けなどのご祈祷を受けられます(受付時間・初穂料は公式の案内に従ってください。交通安全は一般に5,000円以上が目安)。はじめてでも社務所で流れを丁寧に教えてもらえるので安心です。馬に直結する祭礼はありませんが、無事に行って無事に帰るという旅の根本を守る拠点として、多度や伊勢と組み合わせると行程が安定します。鈴鹿山麓の清らかな空気の中で深呼吸し、気持ちを整えてから出発しましょう。
関宿〜鈴鹿峠:旧東海道で馬頭観音さがし
関宿は江戸期の町家が立ち並ぶ景観が約1.8kmにわたり連続する国内有数の宿場町。JR関駅から徒歩圏で、観光駐車場は無料です。町並みを歩きながら屋号の看板や虫籠窓に目を向けると、往時のにぎわいが想像できます。宿場の端から鈴鹿峠へと続く旧道をたどれば、路傍の石仏や馬頭観音の小祠、道標、一里塚に出会えることも。石畳や坂があるので、滑りにくい靴と水分補給は必須。歴史を感じるには歩く速度が最良の教科書です。帰路は関の和菓子や志ら玉など地元の味で一息。半日あれば町歩きとミニハイキングをセットで楽しめます。
地元の「馬頭観音の祠」を見つけるコツ
路傍の祠は観光マップに載らないことが多く、探し方にコツがあります。まず、地域の観光協会サイトや自治体の文化財ページ、街道ウォーキングの公式資料をチェック。検索では「馬頭観音」「◯◯観音」「地蔵」「祠」など表記揺れを試し、地名と組み合わせるのが有効です。地図アプリの航空写真モードで道端の小さな屋根や社を探すのも手。三重の例では紀北町・前村の和歌山別街道沿いに小祠と馬頭観音が確認できます。現地では私有地や農地に配慮し、路肩への無理な駐車は避けて公的な駐車場を利用しましょう。扉が閉じられていれば開けず、合掌して一礼、静かに立ち去る。小さな礼節が、次の旅人まで景観と信仰をつないでくれます。
ご利益別の回り方
交通安全・旅行安全を願うなら
出発前に椿大神社で車両清祓や旅行安全の祈願を受けると、ハンドルを握る姿勢が自然と引き締まります。祈願は受付で願意を明確に伝えるのがコツ。「家族で伊勢参りの無事故」「◯月◯日の長距離ドライブの安全」など、具体的な言葉にすると旅程のリスクにも意識が向きます。参拝後は休憩計画を2〜3時間ごとに設定し、渋滞や悪天候の回避策もあらかじめ用意。上げ馬や神馬の見学では、馬の進路を塞がない、フラッシュ禁止、子どもの手を離さないの三点を徹底しましょう。帰路は関宿に立ち寄って気分転換をし、最後に最寄りの馬頭観音へお礼参り。安全は神頼みだけでなく、情報収集と行動の積み重ねで成り立ちます。祈りと準備の両輪がそろうと、旅は格段に安心で豊かになります。
勝負運アップをねらうなら
挑戦の気持ちを奮い立たせたいなら、多度大社で上げ馬の舞台に心を重ねる巡り方が向いています。若者と馬が斜面を駆け上がる姿は、努力と集中、そしてチームワークの象徴。観覧当日は午後2時ごろ開始の目安に合わせて早めに到着し、安全な視界が確保できる場所を選びます。人馬に向けて声を張り上げたり、進行を妨げたりするのは厳禁。静かに息を合わせて見守る姿勢こそが、勝負前の心構えを整えてくれます。参拝では「いつ・どこで・何に挑むのか」を短い言葉で心の中に刻み、帰宅後の行動計画を紙に落とし込みましょう。運は偶然任せではなく、日々の行動で呼び込むもの。多度の空気は、その覚悟にそっと背中を押してくれます。
仕事運・学業運を伸ばしたいなら
方向性を確かめたい時は「みちひらき」の椿大神社が頼もしい味方。合格祈願や商売繁昌、方位除けなど願意が豊富なので、自分の状況に合うものを選びましょう。おすすめは、参拝前に手帳へ三つの実行項目を書き出すこと。「一週間毎日30分の勉強」「上司に提案を一件伝える」「移動時間は読書に充てる」など、具体的で測れる行動に落とすと効果的です。参拝後は関宿のカフェで小休止し、集中できる場所でスケジュール化。紙へ書く行為が、曖昧な不安を見える形に変えてくれます。次の休日に多度や伊勢を組み合わせ、節目ごとに心を整えるルーティンを作ると、長期的な成長の支えになります。
健脚・足腰の守護を祈るなら
歩く旅は足腰が命。関宿〜鈴鹿峠の旧道をゆっくり歩き、道端の祠や道標に手を合わせながら体を慣らしていきましょう。出発前にアキレス腱と股関節を中心に5分間のストレッチ、靴擦れ防止の靴下、かかとが安定する靴が基本装備です。水分はこまめに、休憩は30〜60分に一度が目安。登坂で息が上がったら、景色を眺めながら呼吸を整えると同時に、旅ができる体への感謝も忘れずに。下山後は温泉や地元グルメで糖質・タンパク質・塩分を補給すると回復が早まります。大きな無理をせず継続することが、結局は最短距離。健脚の祈りは、丁寧な歩き方という日々の実践に宿ります。
乗馬・馬術の安全祈願をするなら
乗馬に親しむ人は、神社での祈りを「馬の健康」「自分の無事」「仲間・指導者への感謝」の三点に分けて言葉にするのがおすすめです。多度大社は人馬一体の精神に触れられる場所で、上げ馬の歴史を知るだけでも心が引き締まります。旅程に伊勢神宮を組み合わせ、朝の清浄な時間に参拝すれば、競技や外乗前のメンタルケアにも効果的。祈願は社務所で相談でき、願意に応じた案内を受けられます。帰宅後は馬具の点検、蹄のケア、基礎練習の反復といったルーティンを整え、祈りを日常の安全行動へつなげましょう。伝統への敬意と具体的な準備がそろえば、安心して上達に集中できます。
旅のモデルコースと実用情報
日帰り:名古屋→多度大社→桑名グルメ
朝、近鉄で名古屋→桑名が約16〜21分(特急は15〜17分前後の例あり)。桑名で養老鉄道に乗り換え桑名→多度は約13〜16分、多度駅からは約1.5km(徒歩15〜20分)で多度大社に到着します。乗換・徒歩を含めると体感で最短約50分前後。午前は境内参拝と資料の閲覧、上げ馬期以外は静かな空気を味わえます。昼は桑名名物のはまぐり料理で塩分とたんぱく質を補給。午後は多度の古い町並みを散歩するか、長島温泉・なばなの里へ足を延ばすのも良策です。車なら東名阪・桑名東ICから約10分、繁忙期は駐車場が満車になりやすいので早着を。帰路は近鉄で名古屋へ戻り、駅ナカで手土産を整えれば、一日でも満足度の高い“馬ゆかり”日帰り旅が完成します。
1泊:伊勢神宮と周辺をゆっくり
初日は外宮→内宮の順で参拝し、午後はおはらい町・おかげ横丁をのんびり散策。夕食を早めに済ませ、翌朝に備えて早寝します。もし滞在日が1・11・21日に当たるなら、内宮の朝8時ごろの神馬奉仕に合わせて動き、清らかな時間帯に正宮へ参るプランが至福です。車の場合、内宮周辺の伊勢市営駐車場は昼間最初の1時間無料→1〜2時間500円→以後30分ごと100円。表示に従って利用しましょう。2日目は二見興玉神社や賓日館へ足をのばし、海風でリフレッシュ。名古屋方面へは近鉄特急で最短約1時間20分。早朝参拝を重視するなら、内宮寄りの宿が動線の短縮に有利です。
2日:北勢から伊勢へドライブ
1日目は椿大神社で車両清祓→関宿で町歩き→多度大社で参拝という北勢パートを凝縮。2日目は伊勢へ南下して外宮・内宮を参拝し、時間が許せば二見へ。走行距離が長くなるため2〜3時間ごとの休憩を計画に組み込むと安全です。伊勢市営駐車場の混雑や障がい者向けスペースの場所は事前に把握しておくと当日の迷いが減ります。帰路の渋滞を見越して早めに出発し、サービスエリアでストレッチを。北の峠の歴史、中央の馬の神事、南の海の清涼感を一筆書きで味わえる、満足度の高い横断ルートです。
季節のポイント:上げ馬神事の時期と混雑対策
多度祭は5月初旬(例年ゴールデンウィーク期)に行われます。5月5日(本祭)は午後2時ごろ開始で5回または6回、5月4日は午後1時ごろから10回という進行が目安。2024年以降は安全性を高めるためコース形状の変更が行われ、2025年もこの方式を継続。祭のある日は境内と周辺道路が大変混雑し、交通規制が敷かれることもあります。公共交通の利用、早着・こまめな水分補給・帽子やレインウエア携行が鉄則。子ども連れは耳栓や冷感タオルを用意すると体力の消耗を抑えられます。観覧時は係員の誘導に従い、撮影は周囲をよく確認してから。開始回数や観覧エリアは年度で変わるため、直前に公式の告知で再確認しましょう。
行き方・駐車場・服装チェックリスト
-
名古屋→多度(電車):近鉄で名古屋→桑名約16〜21分(特急は15〜17分前後の例あり)。養老鉄道で桑名→多度約13〜16分。多度駅から多度大社まで約1.5km(徒歩15〜20分)。
-
名古屋→伊勢(電車):近鉄特急で最短約1時間20分(ダイヤにより変動)。
-
多度大社の駐車:境内横無料少数、階段下や周辺に有料含む複数(繁忙期満車注意)。
-
伊勢(内宮周辺)の駐車:最初の1時間無料→1〜2時間500円→以後30分毎100円。
-
服装:一年を通じて歩きやすい靴・天候対応の上着・雨具が基本。夏は帽子と飲料、冬は防寒と滑り止め。
-
マナー:祠や旧跡は生活道路に面する場合が多い。路上駐車禁止・静かな行動を徹底。
主なスポットの実用メモ(クイック参照)
場所 最寄り/アクセス 駐車 ポイント 多度大社 養老鉄道「多度」から約1.5km(徒歩15〜20分)/東名阪・桑名東IC約10分 境内横無料少数、周辺に有料含め複数 5月5日は午後2時ごろ開始で5〜6回/5月4日は午後1時ごろから10回。授与所は9:00〜17:00目安 伊勢神宮(内宮・外宮) 近鉄(伊勢市・宇治山田・五十鈴川) 伊勢市営P:昼間最初1時間無料→1〜2時間500円→以後30分毎100円 御厩あり。毎月1・11・21日の朝8時ごろ神馬の参向日(中止・変更あり)。参拝は外宮→内宮がならわし 関宿 JR関駅徒歩圏 観光駐車場無料 約1.8kmに江戸の町並み。旧道で祠探しが楽しい 椿大神社 鈴鹿市、車アクセス良好 境内駐車場あり みちひらき・交通安全の総本宮。ご祈祷(交通安全は5,000円以上が目安)
もっと楽しむための豆知識
御朱印のいただき方とマナー
まず参拝、その後に御朱印という順序を守りましょう。御朱印帳は表紙を開き、日付スペースを示してお渡しするとスムーズ。多忙時は書き置き対応になることもあるので、時間に余裕を。お願いする時は「お願いします」、受け取る時は「ありがとうございます」とひと言添えると気持ちの良い交流になります。祠や路傍の石仏では御朱印は基本的にありません。地域の方に出会ったらあいさつを交わし、撮影は生活の邪魔にならない距離から。御朱印はコレクションではなく参拝の証という意識を持つと、旅の記録がより大切なものになります。
写真撮影の注意(馬や神事を守るルール)
馬は光と音に敏感で、予期せぬ刺激は事故のもとです。フラッシュや連続シャッター音、至近距離からの正面撮影は避けましょう。上げ馬・神馬奉仕ともに、進行路の横断やロープ内侵入は厳禁。三脚や自撮り棒は観覧の妨げになりやすく、使用可否の掲示を必ず確認します。SNSに投稿する場合は個人の顔が特定されないよう配慮し、位置情報の扱いにも注意を。子ども連れは肩車を控え、視界を遮らない配慮を心がけます。伝統と安全を最優先にする姿勢が、行事を未来へつなぐ力になります。
地元グルメ&お土産(伊勢うどん・はまぐりなど)
旅の記憶は味とも結びつきます。桑名でははまぐりを使った吸い物や焼き物、伊勢では伊勢うどんの柔らかい麺と濃いタレの組み合わせを。おかげ横丁の食べ歩きは、混雑時に歩き食べを控えるなどマナーも忘れずに。帰りの車内で楽しめるよう日持ちするお菓子や真空パックを選ぶと荷物が軽くなります。関宿では昔菓子や地元の餅菓子が人気。志摩まで足を延ばせば海の幸も豊富で、干物や海藻類は家庭での再現度が高いお土産です。店の方に「今日のおすすめ」を尋ねると旬の味に出会える確率が上がります。
エシカル参拝:動物と環境への配慮
持ち帰るのは思い出だけ、を合言葉に。ゴミは必ず持ち帰り、植栽や苔を踏み荒らさない、野生動物や地域の猫に食べ物を与えないなど、自然と生き物に配慮した行動を心がけましょう。上げ馬や奉仕の見学では、主催者が打ち出す安全方針に従うことが参加者の最低限の責任です。小さな祠や旧跡は住民の手で守られている場所。賽銭箱や維持協力の募金があれば、感謝の気持ちで少しだけ置いていくのも良い支援になります。静けさと清潔を保つ意識が、次の旅人まで美しい景観をつないでくれます。
用語ミニ辞典:神馬・馬頭観音・上げ馬
神馬:神に奉仕する馬。伊勢神宮では内宮・外宮に御厩があり、毎月1・11・21日の朝8時ごろに正宮へ向かう日が設けられている(天候・体調等で中止・変更あり)。
馬頭観音:馬や旅人、運搬に従事する人びとの守護とされる観音。旧街道沿いの小祠や石仏として広く分布し、地域の暮らしの記憶を伝える。
上げ馬:多度祭で行われる神事の一部。2024年から安全対策として急斜面を廃し緩やかなコースへ変更。5月5日は午後2時ごろ開始で5〜6回、5月4日は午後1時ごろから10回が目安。
まとめ
三重県を「馬」という一本の軸で歩くと、祭礼の迫力、朝の清浄な祈り、街道の静かな記憶、そして人びとの暮らしが有機的につながって見えてきます。多度大社の上げ馬は地域の祈りが結晶したハイライトであり、伊勢の神馬奉仕は心を鎮める厳粛な時間。関宿や鈴鹿峠の道端に佇む祠は、何世代もの旅人と馬が残した“ありがとう”の痕跡です。安全と礼節を第一に、公式の最新情報で計画を整え、無理のない行程で一歩ずつ。あなたの旅路が、きっとやさしく開けていくはずです。


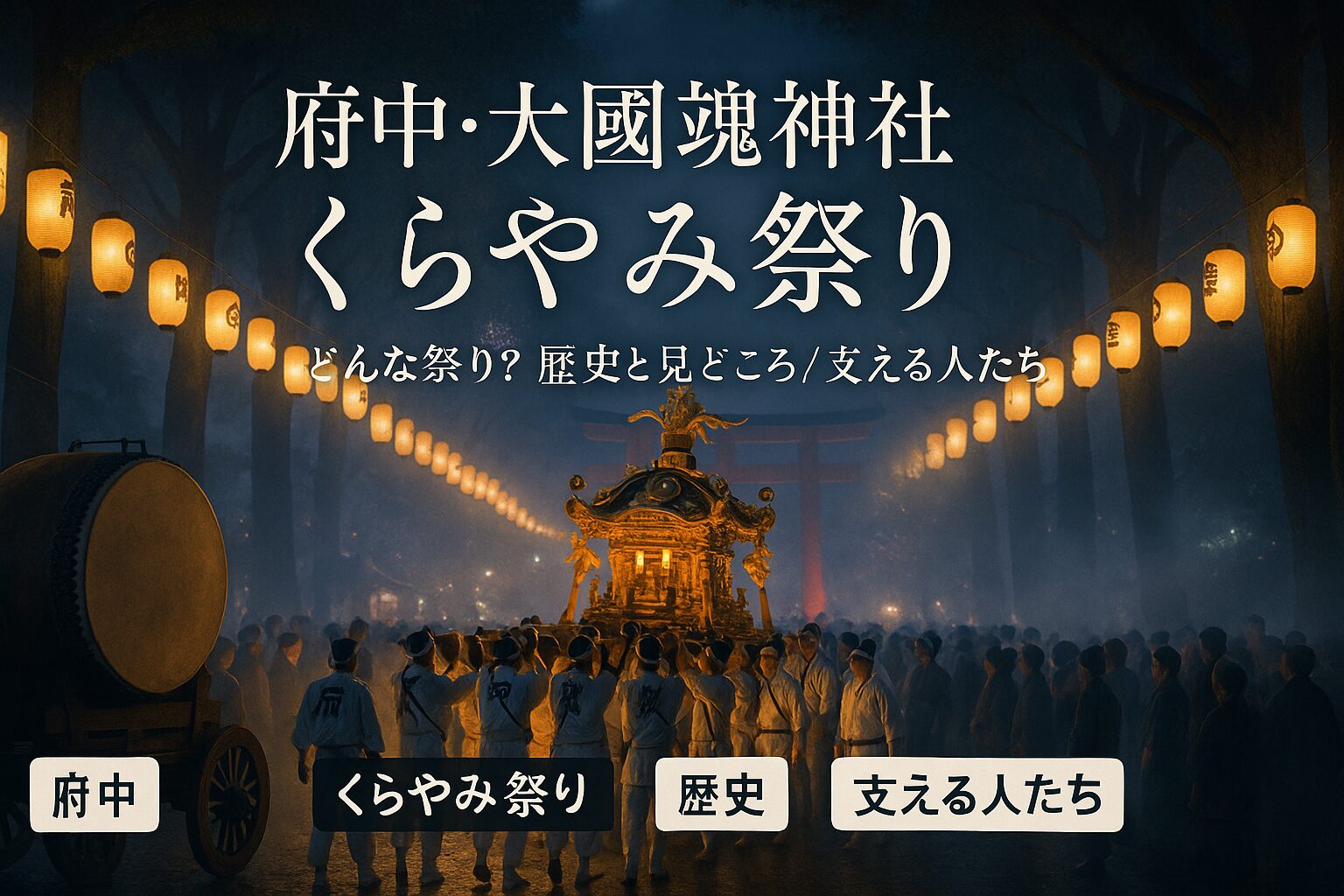

コメント