長岡「金峯神社」の流鏑馬と佐渡の伝統を知る(開催情報・見どころ・アクセス)

「午」という字を見ただけで胸が高鳴る人へ。新潟には、馬とともに生きた人々の記憶が、神社仏閣の神事や道端の石仏、競馬場の静かな碑まで、さまざまな姿で息づいています。長岡・金峯神社の矢が放たれる瞬間、胎内の坂を駆け上がる蹄、川のほとりで手を合わせる小さな祈り、越後一宮の神馬が放つ気配。2026年・丙午に向けて、今年は“馬ゆかり”をめぐる旅支度を始めませんか。ここにまとめたのは観光名所の寄せ集めではなく、土地の暮らしと祈りに根ざした“馬の記憶”のガイドです。
金峯神社の流鏑馬とは?歴史と開催日・基本情報
長岡市の金峯神社では、毎年7月15日の大祭で流鏑馬が奉納されます。開始時刻は例年17時前後で、夕刻の光に包まれた境内を馬が駆け抜け、射手が馬上から的を射抜く勇壮な神事です。長岡市の文化財解説では、この流鏑馬は市指定無形民俗文化財に位置づけられ、県内に残る流鏑馬は「金峯神社と佐渡のみ」と明記されています。起源については、源義家が奥州の戦へ向かう道中に勝利祈願として奉納したと伝わる“社伝”があり、地域の信仰と歴史を語る核になっています。所在地は「新潟県長岡市西蔵王2-6-19」。一部の観光情報で旧い「蔵王1-8-7」表記が残ることがあるため、地図検索の際は公式住所を優先してください。年により導線や開始時刻がわずかに変わるため、出発前に自治体・神社・観光協会の最新告知で確認してから向かいましょう。
初めてでも楽しめる観覧&撮影のコツ
初見で失敗しがちなのは“立ち位置”と“露出設定”です。安全ロープの外側で、射場のやや後方・外側を基点にすると、馬の進入→射抜き→通過の一連が視界に収まります。被写体ブレを抑えるなら1/1000秒前後を目安にし、曇天や夕刻はISOをためらわず上げると安定します。望遠一辺倒だと背景が単調になりがちなので、広角で社殿や提灯、見物客を入れて“祭りの空気”も撮るのがコツ。耳栓や帽子は子ども連れに有効で、蹄音や歓声に驚いても過ごしやすくなります。フラッシュは馬の集中を乱すため使用しないのが基本。神事の撮影可否や観覧エリアは年で変更されることがあるため、現地のアナウンスと掲示を最優先に行動しましょう。
佐渡にも残る流鏑馬文化の概要(新潟ならではの比較)
新潟県内で流鏑馬が現在まで伝わるのは金峯神社と佐渡島側です。佐渡では羽黒神社(羽吉)のやぶさめが県指定無形民俗文化財として知られますが、現在は休止中の年が続いています。久知八幡宮では市指定の祭礼神事の中に流鏑馬が位置づけられ、芸能と一体で受け継がれてきました。泉集落の荒木神社では子ども射手が中心の形で行われるなど、地域によって所作・衣装・進行に違いが見られます。かつては馬の供出や地域の担い手次第で形が柔軟に変化してきた歴史があり、現在も“安全第一でできる範囲”へ運用を見直しながら継承されています。いずれも年ごとの実施状況が変わりやすいため、訪問前に島内の自治体・氏子総代の告知や観光情報で最新の開催可否と内容を確認してください。
子ども連れのタイムテーブル攻略と混雑回避
子ども連れの基本戦略は「早着・早飯・早退」です。開始45分前の到着で場所取り、開始前にトイレと給水を済ませ、射場正面の密集地帯を避けて外側から観覧すると安全度が上がります。見どころは矢放ちの瞬間ですが、音量や躍動で驚く子もいるため、耳栓や帽子、軽食で機嫌を整えてあげると安心。抱っこ紐は石段や玉砂利で動きやすく、ベビーカーは場面によっては不向きです。混雑のピークはクライマックス直前と終了直後に集中するため、観覧を一回で切り上げる“一点集中”方式や、終盤少し前に移動を開始する“時間差撤収”を検討しましょう。帰路は交通規制の解除を待ちつつ、係員の指示に従って安全に移動するのが鉄則です。
長岡周辺の温泉&ご当地グルメで〆る
祭りの余韻を保ったまま身体をいたわるなら「温浴→遅めの夕食」の順が快適です。長岡駅前では生姜醤油ラーメンの人気店が複数あり、体を温めつつ塩分補給にもなります。車移動なら与板や出雲崎方面の日帰り温泉で汗を流し、寺泊エリアの鮮魚店・食堂で新鮮な海の幸を楽しむのも王道コース。祝祭日は夕刻に幹線道路が混みやすいため、17時前の早め夕食か、いったん温浴でピークを外してから動く“時間差”が有効です。夏場は特に脱水に注意し、撮影で集中しすぎたと感じたら電解質の飲料でこまめに補給を。店舗の定休日・営業時間は季節変動があるため、当日の公式案内で最新情報を確認しておきましょう。
胎内「シャングシャング馬」を追う:鳥坂神社と馬頭観音の物語
300年続くと言われる祭礼の由来と“2015年の復活”
胎内市・下赤谷の春の行事「シャングシャング馬」は、鈴の音(シャングシャング)を響かせながら装束の馬が集落を練り歩き、鳥坂神社(旧称・馬頭観音)前の急坂を一気に駆け上がることで知られます。長い途絶期を経て、2015年に地元住民と養老牧場の協力で三頭の馬から現代的な形で復活し、年を追うごとに運営と安全面の工夫が重ねられてきました。復活の年を2016年と誤解する記述を見かけますが、正しくは2015年です。装束の赤や房、鈴の音、土を蹴る蹄の勢いは写真・動画映えも抜群で、しかし本質は五穀豊穣や牛馬安全を祈る素朴な信仰にあります。地域の記憶をつなぎ直す営みとして、手づくりの温度を保ちながら続けられている点にこの祭りの価値が宿っています。
馬が坂を一気に駆け上がる!ベスト観覧ポイントと所要時間
行事の核心は“駆け上がり”です。坂下からの視点は迫力満点ですが人出が集中するため、初めての人や子ども連れは坂のやや上手・外側から斜めに構え、馬の進入・加速・駆け上がり・通過が見える角度を選ぶと安全と視界が両立します。所要は挨拶・練り歩き・駆け上がり・参拝・休憩・再演・下山までで概ね半日。写真はシャッタースピード1/1000秒前後、連写ドライブ、AF-C、手ぶれ補正オンが基本。流し撮りで速度感を強調するなら1/30~1/60秒も狙い目です。観客の密度が高い年は導線や仕切りが変更されるため、立入禁止ロープを越えないこと、フラッシュや大声での呼びかけを控えること、馬の進路に背を向けての撮影を避けることが重要です。
馬頭観音堂の参拝ポイント(ご利益・作法の基本)
馬頭観音は観音菩薩の変化身で、忿怒の相で煩悩・災厄を打ち砕き、畜生道を救済すると説かれます。日本では家畜や運搬の要だった“馬”と重なり、動物供養・交通安全・旅の無事などの祈りと結びつきました。参拝の作法は難しく考えず、鳥居・山門前で一礼、手水で清め、堂前で静かに合掌。供花やお線香は火気・片付け・周囲への配慮を徹底し、祭礼当日は進行の妨げにならないタイミングを選びます。馬を驚かせないようフラッシュや接近を控え、写真は短時間で切り上げるのが礼儀。願い事は具体的に一つか二つに絞り、“感謝”の言葉を添えると心が整います。由緒やご真言が掲示されている場合は、まず一読してから参ると理解が深まります。
アクセス&交通規制・駐車の注意点(当日運営の目安)
集合は道の駅「胎内」河川公園が基本。例年、午前に練り歩きが出発し、鳥坂神社前の坂で複数回の“駆け上がり”が行われます。道路は一部区間で通行止めが敷かれ、直近の年では8:30~12:00といった時間帯の規制例が公表されています。2025年は10:15頃出発・14時台下山のスケジュールが告知されましたが、天候や馬の体調で柔軟に変更される可能性があります。駐車は指定場所のみ、坂下周辺は歩行者優先で徐行が徹底されます。トイレ・自販機は河川公園で早めに利用し、斜面や玉砂利では滑りにくい靴を推奨。ドローン飛行やペット同伴の可否は年度で方針が異なるため、必ず最新の公式案内をご確認ください。
近年のトピック(参加者の広がり・来場の傾向)
復活当初は三頭での練り歩きからの再出発でしたが、その後は地元の学校や馬事関係者、近隣地区の協力が広がり、装束や鈴の意匠も年ごとに磨かれていきました。コロナ禍の中止・縮小を乗り越え、2022年には色鮮やかな装束の馬が10頭規模で集う年もあり、地域メディアでも“にぎわいの復活”が報じられました。SNSでは坂を駆け上がる連写や、鈴の音が風景に溶け込む動画の人気が高く、撮影者の増加に合わせて安全運用の周知も強化されています。来場者層は家族連れと写真愛好家が二本柱で、午前の練り歩きから最後まで追う“通し組”と、駆け上がりだけを狙う“時短組”に分かれる傾向があります。前者は日焼け・補給、後者は到着直後の導線把握が要点になります。
馬頭観音を巡礼:十日町・新潟市・競馬場で“馬の仏さま”に会う
十日町・松苧神社に伝わる木造馬頭観音坐像(市指定文化財)
十日町に伝わる木造馬頭観音坐像は、高さ36.3センチと小ぶりながら三面八臂の威容を湛え、台座に「応永十年(1403)八月二十四日作之 作者讃岐丸 大江ゑ門入道」との墨書が残ります。制作地は京と推定され、地方にありながら都の美意識を伝える貴重作です。かつて中院(白馬観音堂)が雪害で倒壊する前に、像を犬伏の庵堂へ避難させて難を逃れたという逸話が伝わり、地域が文化財を守ってきた具体的な行動の記録としても重要です。現在は市の文化財として整理・公開情報が整備され、写真・寸法・来歴が明快に示されています。規模の大小に関わらず信仰の対象に“人格”を見いだしてきた新潟の姿が、この小像の迫力に凝縮されています。
新潟市秋葉区・小須戸の川辺に立つ馬頭観音のエピソード
信濃川の渡し場で栄えた小須戸には、天保の頃に増水した川を無理に渡ろうとして多くの馬が溺れ亡くなったことを悼み、馬宿・尾崎屋円助らが建立したと伝わる馬頭観音が残ります。位置は小須戸橋のたもとが目安で、舟運と馬市で栄えた町の歴史を静かに語り続けています。周辺整備に伴い位置が移ったという話は地域記事・現地レポートによるもので、公的資料では明確な記述が乏しいため、その点は出典の性質を意識して受け止めるのが適切です。いずれにせよ、川と馬と人の暮らしが交差した場所で、いのちを悼む祈りが今も可視化されていることに価値があります。参拝は交通の妨げにならない時間帯に、短時間・静粛を心がけましょう。
新潟競馬場の馬頭観世音にご挨拶(場所の目安・授与品の話題)
新潟競馬場のパドック付近には、馬頭観世音の碑があると複数の現地レポートや来場記録で紹介されています。場内アナウンスやマップは時期により掲載項目が変わるため、具体的な位置把握は当日のスタッフに確認するのが確実です。開催時には“御駿印”と呼ばれる来場記念の印が限定で販売されることがあり、ターフィーショップ等の公式アカウントで発売告知が出る年も見られます。ただし授与・販売の有無やデザイン、販売場所は開催回ごとに変更されるため、「販売がある場合は当日の案内に従う」という但し書きを常に添えておくのが公平です。参拝・撮影はレース進行の妨げにならない短時間で、動線や馬の安全を最優先に配慮しましょう。
そもそも“馬頭観音”とは?起源とご利益の基礎知識
馬頭観音は観音菩薩の変化身の一尊で、六観音に数えられる存在です。怒りの相(忿怒)で描かれるのは、煩悩や障碍を打ち砕く救済力を象徴するためで、インド的背景にハヤグリーヴァ(馬頭の神)への連想を重ねる解説もあります。日本では古くから馬が運搬・耕作・移動の相棒であったため、動物供養・交通安全・旅の無事を願う祈りと結びついて全国に石仏や堂宇が広がりました。新潟でも川湊・街道・峠・競馬場など“馬が働いた場所”を中心に碑や石仏が点在します。参拝は特別な作法を要さず、静かに手を合わせ、供花や清掃で“手向け”の気持ちを形にすることが要点です。宗派の違いはありますが、根底にあるのは“いのちを思いやる”姿勢です。
参拝・撮影時のマナーと安全配慮チェックリスト
第一に、神事・レース・参拝者の動線を妨げないこと。社寺では合掌一礼、手水で清め、石段や玉砂利では滑りにくい靴を。三脚は人の流れが滞る場所や混雑時間帯では使わず、短時間で譲り合いを徹底します。馬や動物に対してはフラッシュ禁止・不用意な接近禁止・大声禁止が原則。供花や線香は風向き・火気・片付けに留意し、持ち込み可否の掲示に従います。競馬場では“馬の動線優先・観客動線順守”を徹底し、パドック柵に身体を乗り出さない、レース前後の緊張時間帯は撮影を控えるなど細心の配慮を。写真やSNS投稿は個人情報や他参拝者の写り込みに注意し、位置情報の公開範囲も事前に検討しておくと安心です。
越後一宮・彌彦神社の“神馬”文化を深掘り&「駒形」の社を訪ねる
彌彦神社の神馬舎とは(木像の作者:山本瑞雲/高村光雲の高弟)
越後一宮・彌彦神社の神馬舎には、高村光雲の高弟である彫刻家・山本瑞雲による木彫の神馬が奉安されています。神馬は神の御乗物として神威を象徴し、実馬の奉納に代わって木像や銅像で祀られる例も少なくありません。彌彦の神馬は端正な面相と量感ある体躯で、参道の静けさの中に凛とした存在感を放ちます。まず拝殿で日々の感謝を伝え、神馬舎で“馬への敬意”を新たにし、最後に御神域全体を静かに巡ると、境内の流れが自然に体へ染み込みます。公式案内に作者名が明記されている点も含め、文化史と信仰の交差点として訪ねる価値の高いスポットです。
絵馬に残る“馬”信仰の歴史を読み解く(境内の歩き方)
絵馬の起源は、かつて本物の馬を奉納する代わりに“馬の絵”を奉納したことにあるとされます。彌彦でも交通安全、勝負運、家内安全など、馬にちなむ願いが今も息づいており、拝殿脇の絵馬掛には多様な祈りが重なります。境内の歩き方は、参道右側通行を基本に、撮影は他者の参拝の邪魔にならない角度と距離をキープ。御守・御札・御朱印は季節で授与体制が変わることがあるため、訪問前に最新情報を確認すると滞りがありません。見過ごされがちなのが、境内の小さな意匠や文様。馬と稲、山と海を結ぶ越後の暮らしが、細部のモチーフにさりげなく表現されています。
県内の「駒形神社」をチェック(例:糸魚川市 下倉の駒形神社)
社号に“駒形”を冠する社は、馬との関わりを色濃く伝える存在です。新潟県内にも点在し、糸魚川市下倉の駒形神社はその一例。大規模な観光地ではないため、静謐な空気の中で地域の日常と向き合う参拝ができます。境内整備や駐車の可否は地域事情に左右されるため、長居は避け近隣への配慮を最優先に。神社庁のデータベースや地図情報で所在地とアクセスを確認し、天候や路面の状況に応じて安全第一で訪れましょう。参拝後は地域の史跡や古道を合わせて歩くと、馬の道と人の道が重なってきた歴史が立体的に見えてきます。
1日で回す“馬ゆかり”ハイライト周遊プラン
モデルプランは、朝に彌彦神社からスタートし神馬舎と拝殿で心を整える→北陸道経由で長岡の金峯神社へ移動(流鏑馬の日は早着で場所確保)→夕刻は新潟市・小須戸の馬頭観音へ→開催と時間が合えば新潟競馬場で馬頭観世音の碑に一礼、という“越後平野右回りルート”です。総移動はおよそ200km弱、各区間は60~90分が目安。祭礼や授与は年で運用が変わるため、当日の公式情報を確認して柔軟に順序を入れ替えましょう。レンタカーなら小回りの利くクラスが便利で、鉄道+タクシーでも十分に成立します。昼食は彌彦の門前や長岡駅前で早めに済ませ、夕方の渋滞を避ける時間設計が快適です。
御朱印・授与品の楽しみ方と保管のコツ
社寺ごとに授与体制・初穂料は異なり、期間限定や会期限定の授与品もあります。新潟競馬場の“御駿印”のように開催回ごとに販売の有無や場所が変わる記念品は、必ず当日の案内で確認しましょう。いただいた御守や紙印はジップ袋で防湿・防汚し、帰宅後は高温多湿と直射日光を避けて保管。御朱印帳は手の油で波打ちやすいので、ページの乾燥を待ってから閉じると長持ちします。撮影・投稿は社務所や他参拝者の写り込みに配慮し、個人情報が映る場合は加工や非公開設定を。大切なのは“ありがたく丁寧に扱う”姿勢で、数よりも一つ一つのご縁を深める意識が満足度を高めます。
“午(うま)年”の準備:2026年・丙午に合わせて回る新潟参拝計画
2026年は“丙午(ひのえうま)”:干支の基礎をサクッと確認
干支は十干と十二支の組み合わせで60年周期。2026年(令和8年)は“丙午(ひのえうま)”に当たります。干支は暦法上の符号で、十二支の“午”は本来、南の方位や正午の時刻を指す記号でしたが、動物の“馬”と結びつけられて親しまれてきました。年回りそのものに吉凶が宿るというより、暦を旅の背中押しに使うと前向きになれます。馬ゆかりの地を巡るには雪解けから新緑の5~6月、実りの9~10月が動きやすく、天候の急変が少ない点でも計画が立てやすい季節です。祝祭日と重なる祭礼は混雑するため、平日または開始前の到着を心がけると体験の質が上がります。
午と馬の違いは?十二支の読み方・意味
“午”は十二支の第七で、本来は時刻・方位を表す記号です。一方の“馬”は動物そのもので、記憶しやすいよう十二支に動物を対応させた慣習が広がった結果、「午=馬」と認識されるようになりました。干支は十干(甲乙丙丁…)と十二支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)の組み合わせで、例えば2026年は“丙(火の陽)”と“午(南・正午)”が重なる年。旅先で“午”の字や馬の意匠に出会ったら、暦と信仰と生活感覚が重なって生まれた日本らしい感性に触れているのだと意識してみましょう。言葉の理解が深まるほど、授与品や社頭掲示にある短い文言も立体的に読み解けます。
願意別のおすすめ参拝先(勝負運/交通安全/五穀豊穣 など)
勝負運や仕事運を意識するなら、越後一宮・彌彦神社で神馬と縁を結び、金峯神社の流鏑馬奉納に“的中”の象徴を重ねる流れが分かりやすいでしょう。交通安全・旅の無事・動物供養に心を寄せるなら、小須戸の馬頭観音や新潟競馬場の馬頭観世音で静かに合掌を。豊穣や家内安全は、佐渡に受け継がれてきた流鏑馬神事の意味を心に留め、収穫の季節に感謝を重ねる巡礼が似合います。いずれも“願いは一つに絞る”のが基本で、複数ある場合は参拝を日程で分けると心が澄みます。授与品は身につけるか、清潔で高い場所に安置し、感謝が薄れたと感じたら社寺に納め直す選択も丁寧です。
ベストシーズンと気候・服装の目安
日本海側の新潟は、冬の降雪・季節風と夏の強い日差しがはっきりしています。歩行・撮影が主体の巡礼には、雪解け~初夏と秋が適季。平野部は晴れると紫外線が強く、帽子・日焼け止め・薄手の羽織が役立ちます。参道は玉砂利や段差が多く、撥水性とグリップのある靴が安全。山間部や海沿いは体感温度が下がりやすいので、軽量のレインジャケットを一年中バッグに忍ばせると安心です。祭礼日や連休は駐車場が不足しがち。公共交通+タクシーやシェアサイクルを組み合わせると時間の読める行程になります。気温・風・降水の実測は前日と当朝に二度チェックし、服装と持ち物を微調整しましょう。
旅の持ち物チェックリスト(御朱印帳・交通系IC・双眼鏡ほか)
御朱印帳と小銭、身軽なカードケース、モバイルバッテリー、飲料と塩分タブレット、ウェットティッシュ、日焼け止め、絆創膏とテーピング、薄手のレインジャケット、滑りにくい靴、折りたたみ座布団、双眼鏡(流鏑馬の観覧に有効)、カメラ(連写設定推奨)を基本装備に。紙の授与品やチケットはジップ袋で防湿・防汚し、帰宅後は直射日光と高温多湿を避けて保管します。新潟競馬場の“御駿印”のような限定品は当日の案内が最優先です。ごみは必ず持ち帰り、地域の方への一言の挨拶を忘れずに。撮影データは帰路のうちに簡易バックアップを取り、紛失や破損に備えましょう。
行程設計に役立つ早見表
| 名称 | 主な場所 | 実施時期・時刻の例 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 金峯神社の流鏑馬 | 長岡市 西蔵王2-6-19 | 毎年7/15、例年17時頃開始 | 市指定無形民俗文化財。新潟で現在伝わる流鏑馬は金峯と佐渡のみと市が解説。住所は公式の「西蔵王2-6-19」を優先。 |
| シャングシャング馬 | 胎内市 下赤谷(鳥坂神社) | 2025年例:10:15開始~14時台下山、8:30~12:00通行止 | 2015年に三頭の練り歩きから復活。坂の“駆け上がり”が核心。集合は道の駅「胎内」河川公園。 |
| 羽黒神社のやぶさめ | 佐渡市 羽吉 | 毎年6/12夕刻(現在は休止の年が続く) | 県指定無形民俗文化財。実施の有無は必ず最新情報で確認。 |
| 久知八幡宮の祭礼神事 | 佐渡市 下久知 | 9/15に近い日曜に本祭 | 市指定の祭礼の中に流鏑馬が位置づけられる。芸能と一体の継承。 |
| 彌彦神社・神馬舎 | 弥彦村 彌彦神社境内 | 通年参拝 | 山本瑞雲作の木彫神馬。拝殿と合わせて静かに巡拝。 |
| 小須戸の馬頭観音 | 新潟市 秋葉区 | 通年(道路状況に留意) | 天保期の馬供養由来。位置は小須戸橋たもとが目安。移設の話は地域記事由来である旨を意識。 |
| 新潟競馬場・馬頭観世音 | 新潟市 北区 | 競馬開催日中心 | 碑はパドック付近と現地レポートに記載。“御駿印”は開催回によって販売の有無・場所が変動。 |
まとめ
新潟で“午(うま)”を辿る旅は、長岡の金峯神社に脈々と受け継がれてきた流鏑馬、三頭から現代に息を吹き返した胎内のシャングシャング馬、川湊の記憶を刻む小須戸の馬頭観音、越後一宮・彌彦の神馬、そして新潟競馬場の馬頭観世音まで、祈りと暮らしが一本の線でつながる体験です。2026年・丙午という節目は、暦を旅の背中押しに変える好機。まずは一社一像を丁寧に訪ね、次の旅で点を線に、線を面に広げていきましょう。開催可否・導線・授与・販売は年ごとに変わるため、最終的には各公式情報と現地スタッフの指示を最優先に。安全第一と地域への敬意を忘れなければ、旅は必ず温かい記憶として心に残ります。
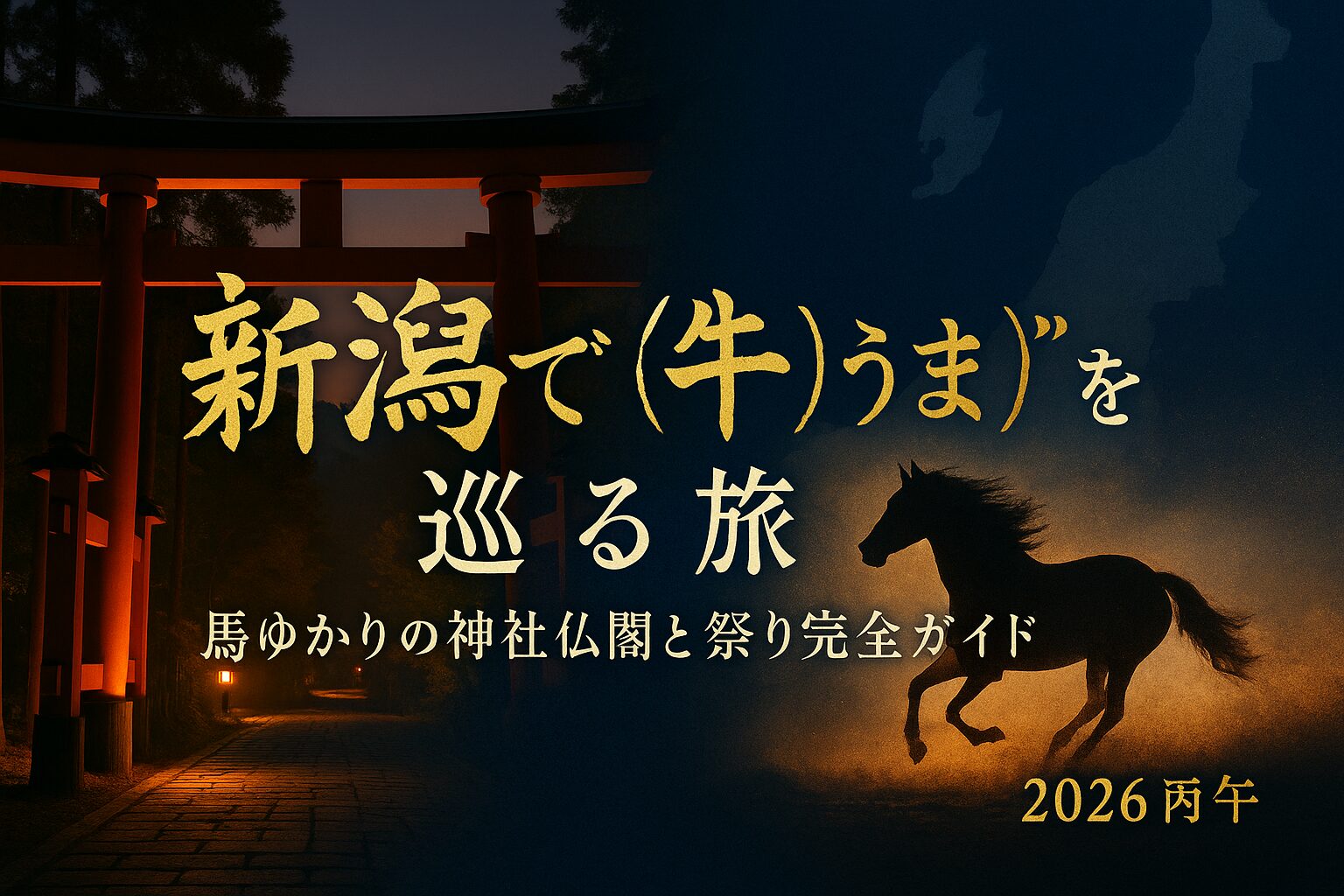

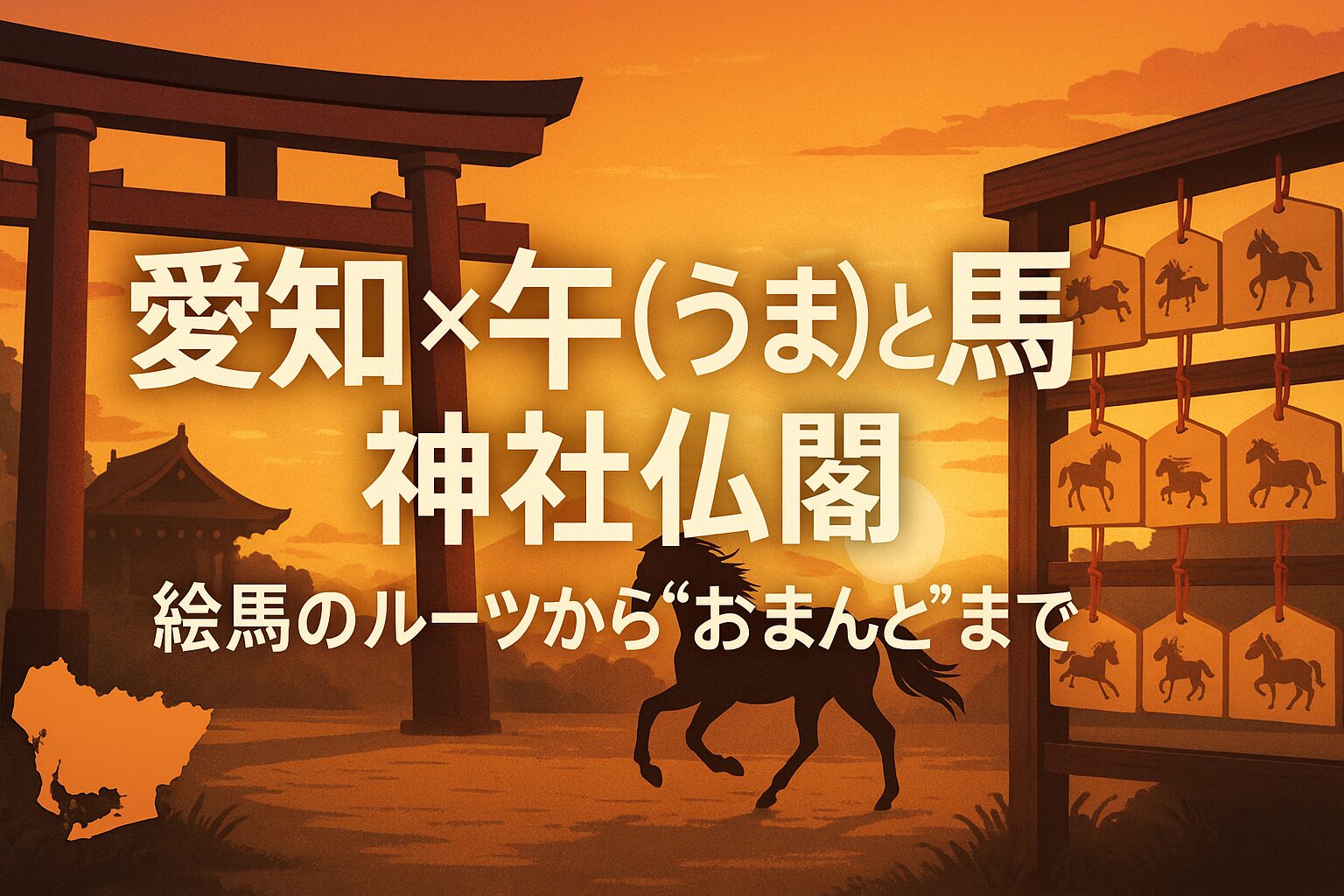

コメント