根津神社は「何の神様?」由緒と呼ばれ方をやさしく解説

「根津神社って“怖い”の?」――検索結果の言葉にドキッとした人へ。答えは「怖くない、けれど背筋が伸びる」。江戸の色彩が残る社殿群、朱が続く千本鳥居、白蛇の伝承を宿す榧の木。そこにあるのは畏れではなく、凛とした静けさです。
かつて「根津権現社」と呼ばれるようになった背景
根津神社は、伝承では日本武尊(やまとたける)が須佐之男命の御神徳を仰いで創祀したとされる古社です。神仏習合の時代には「根津権現社」と呼ばれ、素盞烏尊(十一面観音を本地)を主に、山王大権現(薬師如来)と八幡大菩薩(阿弥陀如来)を相殿に祀ったため「根津三社大権現」とも称されました。明治維新の神仏分離で社号を「根津神社」と改め、いまに至ります。社号碑に刻まれた「元准勅祭」の文字は、近代初頭に国家の安寧を祈る特別な社格(准勅祭社)だった歴史を静かに物語ります。呼び名の変遷は、江戸から明治へと移る宗教文化の流れを映す“生きた資料”。「権現」という言葉にとまどう人も、当時は“神の権化(ご本地の仏)”として敬われたこと――つまり神と仏が溶け合って信仰された時代背景を知れば、ぐっと理解が深まります。
御祭神の顔ぶれと役割(須佐之男命・大山咋命・誉田別命・大国主命・菅原道真公)
根津神社では、主祭神に須佐之男命・大山咋命・誉田別命を、相殿に大国主命・菅原道真公を祀ります。ご神徳として掲げられるのは、厄除け・除災招福・家内安全・病気平癒・延命長寿・五穀豊穣・安産・学業成就・縁結び・商売繁盛・殖産興業など幅広い内容。特定の一柱だけに“お願い”をするより、まず拝殿で五柱へ日々の感謝とこれからの誓いを伝えるのが基本です。そのうえで目的に応じ、絵馬に「達成したい内容+期限」を具体的に記すと、参拝後の行動につながりやすくなります。大切なのは「祈りと実践の両輪」。神社が背中を押してくれるのは、あなたが踏み出す一歩の方向を定めた時です。
徳川家と深い関わりがある理由
現在の豪壮な社殿群は五代将軍・徳川綱吉の命による「天下普請(てんかぶしん)」で再整備され、宝永3年(1706)に完成しました。のちの六代将軍・徳川家宣(綱豊)の産土神として手厚く造営されたため、境内には家宣の胞衣塚など徳川ゆかりの痕跡が残ります。兄・綱重の山手屋敷地が献納されたことにより、旧社地の千駄木から現在地へ遷座が実現。政治と信仰の中心が重なり合う“江戸の縮図”ともいえる場所で、漆の艶や極彩色の装飾からは、国家的事業としての威信と美意識が感じられます。
東京十社に数えられる意味
明治元年(1868)、新政府は「東京の鎮護と万民の平安」を祈るため、選ばれた神社を准勅祭社に定めました。根津神社もその一つです。戦後しばらくして、これらの社を巡る文化的な巡拝企画として「東京十社めぐり」が1975年(昭和50年)に発足。観光だけではなく、首都圏の守護を祈る“現代に生きる巡拝”として親しまれています。御朱印帳を片手に十社をめぐると、地理・歴史・都市計画の視点でも東京が立体的に見えてきます。
「権現造り」ってなに?初心者向けに簡単解説
根津神社の社殿は、拝殿・幣殿・本殿が一体となる「権現造り」。さらに楼門・唐門・西門・透塀を含む七棟がすべて現存し、いずれも国の重要文化財に指定されています。指定年次を添えると、保存の歩みが見えてきます。主だった指定は昭和6年(1931年)、一部の建造物は昭和31年(1956年)に追加指定。300年以上の風雪に耐えてきた本漆塗りの艶と装飾文様は、江戸の色彩文化が“今も息づく”ことを教えてくれます。建物の縁に腰掛けたり塀にもたれたりせず、そっと離れて鑑賞するのが礼儀です。
ご利益まとめ:厄除けから学業・縁結びまで
厄除け・除災招福が強いと言われるワケ
主祭神の須佐之男命は、古くから“災いを祓う力”の象徴的存在として崇められてきました。公式のご神徳でも厄除け・除災招福が最初期に掲げられ、節目の年の不安や生活再建の願いを託す参拝者が絶えません。厄年の人は、個人祈祷(予約不要・随時受付/所要約20分)でしっかり心を整えるのも選択肢。受付時間は季節や社務の都合で変わるため、直前に公式のお知らせを確認しましょう。祈祷後は「何を手放し、何を始めるか」をノートに落とし込み、小さな実践を積み重ねる――この地道さこそ最大の厄除けです。
学業成就と菅原道真公のご縁
相殿の菅原道真公は言わずと知れた学問の神。合格祈願や資格取得の成功体験が口コミで広がっています。参拝のコツは、まず拝殿で五柱全員に感謝と誓いを述べ、具体的な行動計画と締切を絵馬に記すこと。例えば「毎朝30分の過去問×60日」「10月15日に模試A判定」など、測れる目標に変えると祈りが“日課”に変わります。合格後は必ずお礼参りを。努力のプロセスを言語化して奉告すると、次の挑戦に向けた自信が自然と宿ります。
縁結びはどこで祈る?大国主命と乙女稲荷のポイント
良縁は相殿の大国主命が得意分野。まずは拝殿での正式参拝が基本です。そのうえで、境内西側の乙女稲荷神社へ足を延ばすのもおすすめ。倉稲魂命を祀り、奉納鳥居がずらりと並ぶ“朱のトンネル”は、公式案内でも「千本鳥居」と紹介される象徴的スポット。非日常の集中が生まれるので、「どんな関係を育て、どんな関係を手放すか」を心の中で整理するのに最適です。撮影時は鳥居の柱に刻まれた奉納者名への配慮を忘れずに。
商売繁盛・殖産興業の祈り方Q&A
根津神社のご神徳には商売繁盛・殖産興業も掲げられています。まず拝殿で事業の安全と社会への貢献を誓い、必要に応じて乙女稲荷で日々の商いの充実を祈りましょう。おすすめは「PDCA絵馬」。今月の売上目標や提供価値、改善点を短く書き、達成したら“感謝→次の課題”へ更新します。財布に小さなメモを入れて毎週見直すのも効果的。祈りは“業務の見える化”と相性が良いのです。取引先や顧客への誠実さを神前で誓う――それがいちばんの御加護を呼び込みます。
はじめての参拝作法:間違えがちなポイントをチェック
基本は「二拝二拍手一拝」。手水舎で左手→右手→口→柄杓の柄の順に清め、賽銭は静かに。願いは“要求”ではなく感謝+誓い+行動の宣言に近い言葉で。神社によって作法に細かな違いがあるので、掲示があれば必ず従いましょう。根津神社は社殿前の参道(石畳上)での撮影が禁止。商用や放映目的の撮影は事前申請が必要です。写真は周囲の参拝者の動線を妨げない位置から、音の出るシャッターは避けるなど、祈りの空気を壊さない心配りを。
ご神徳早見表(公式の記載+代表的な連想)
| 神さま | キーワード | 祈る場所の目安 |
|---|---|---|
| 須佐之男命 | 厄除・防災・豊穣 | 拝殿 |
| 大山咋命 | 山の地主・農業・醸造 | 拝殿 |
| 誉田別命 | 文武両道 | 拝殿 |
| 大国主命 | 縁結び・国づくり | 拝殿 |
| 菅原道真公 | 学問成就 | 拝殿 |
| 倉稲魂命(乙女稲荷) | 五穀豊穣・商売繁盛 | 乙女稲荷 |
(※ご神徳は“万能薬”ではありません。祈り+実践の両輪で叶えていくのが基本です)
「怖い」と検索されるのはなぜ?神秘と不思議の体験ゾーン
乙女稲荷の千本鳥居が生む非日常感
乙女稲荷へ続く参道に立つ奉納鳥居は、まさに“朱のトンネル”。朝夕の薄明かりに包まれると、足音と風の音だけが響き、時間の感覚がゆっくりとほどけていきます。この非日常感が、人によっては“ちょっと怖いほど神秘的”に感じられる所以。鳥居の内側は参道ですから、立ち止まって長時間の撮影や横並びの通行は避け、後ろから来る人に道を譲るのがマナー。奉納者名の写り込みにも配慮すると気持ちよく楽しめます。
願掛け榧の木と白蛇の伝承にまつわる“不思議”
拝殿前の御神木「願掛け榧(かや)の木」には、神使の白蛇が住み、人々の願いを不思議と叶えたという古い伝承が残ります。伝承はあくまで伝承ですが、静かに手を合わせる人が絶えないのは、榧の前に立つと自然に心が整い、“本当に叶えたいこと”が浮かび上がるからでしょう。願いを言葉にできたら、具体的な行動へ小さく踏み出す。そうして一年後、報告と感謝を捧げるために戻ってくる――この参拝のリズムこそ、伝承が伝える“叶う”の正体なのかもしれません。
夜の境内は怖い?感じ方とマナーの両立
夕刻以降、木々の影が濃くなると境内はぐっと静かになり、初めての人には心細く感じられることがあります。とはいえ神社は「祈りの場」。境内では静粛を保つ、立ち入り禁止や撮影禁止の掲示に従う、社殿や透塀に触れない――などの基本を守れば、怖さよりも“凛とした静けさ”が勝ってくるはず。少しでも不安を覚えたら、無理せず明るい参道に戻ること。安全第一で楽しむのが、神さまにも周囲にも優しい参拝です。
楼門・唐門など権現の意匠が与える“圧”
根津神社の楼門は「江戸内の神社で唯一残る楼門」と言われています。随身像のうち、向かって右が“水戸黄門”と伝えられています。唐門や透塀を含む七棟重文の意匠は、極彩色と本漆の艶、幾何学的な連なりが生む荘厳さで、見る者の背筋を思わず伸ばします。圧倒される感覚を“怖い”と表現する声もありますが、実際には畏敬(いけい)の感情に近いはず。足を止め、細部の彫りや彩色のリズムをじっくり味わってみてください。
口コミの「怖いくらい当たる?」をどう見分けるか
“当たる・当たらない”という二択より、根津神社の公式がていねいに示す広い御神徳と、参拝者側の姿勢に目を向けたいところ。お願いを“丸投げ”にせず、宣言→実行→振り返り→感謝のサイクルを自分の生活に落とし込むと、結果は自然についてきます。SNSや口コミは体験談として参考にする程度に留め、撮影ルールや境内マナーなど公式のお願いを優先――これが、良縁やチャンスを呼ぶ最短ルートです。
お守りガイド:選び方・持ち方・よくある疑問
願い別の選び方(厄除け・病気平癒・安産・学業ほか)
授与所には、厄除け・病気平癒・安産・学業成就・交通安全・商売繁盛など、暮らしの節目を支える授与品が揃っています。まずは願いを一つに絞るのがコツ。1年間「感謝→実践→報告」を回す前提で、日常の行動と結び付けて持ち歩きましょう。季節や行事に合わせた授与が登場することもあるため、欲しいものがある人は最新の案内を事前にチェック。持ち歩きにくい場合は、自宅の清潔な高い場所におまつりし、毎朝のルーティンに“ひと礼”を加えるだけでも心の姿勢が変わります。
複数持ちはOK?色で意味は変わる?公式Q&Aで整理
「複数の神社のお守りを一緒に持っていいの?」「袋にまとめて入れても大丈夫?」「色の違いに意味はある?」――根津神社のQ&Aは明快です。複数所持は問題なし、色は好みで選んでOK。干支の身代わり守は自分の干支を持つのが基本。古い授与品は授与所で返納が可能(ただし、お寺の授与品・正月飾り・人形などは対象外)。迷ったら“気持ちが素直に整うか”で選ぶと失敗しません。
返納タイミングと正しい納め方
お守りやお札は一年を目安に、守っていただいた感謝を伝えて返納します。参拝時に授与所へ申し出れば預かってもらえます。年末年始には返納用の専用箱が設置される期間があり、混雑を避けて納められて便利です(設置時期は年度により変動するため、事前に公式のお知らせを確認)。遠方の方は次の参拝まで清潔な場所に保管し、心を込めてお礼を述べてから納めれば大丈夫。焦らず、丁寧に向き合いましょう。
郵送で授与を受けたいときの注意点
根津神社では郵送授与に対応しています。流れは申込用紙をメール/FAXで送付→神社から「納入依頼書」到着→期限内に振込→入金確認後に発送。申込用紙に記載のある授与品が対象で、期限内未入金はキャンセル扱いになる点も明記されています。社務の都合で受付状況や内容は更新されるため、申込前に最新ページと注意書きを必ずチェック。繁忙期は到着まで日数がかかることもあるので、余裕を持って申し込みましょう。
御朱印の基礎知識とマナー入門
御朱印は「参拝の証」。列が伸びているときはゆずり合い、授与所の指示に従いましょう。つつじまつり期間は限定御朱印の頒布や終了などがその年の状況に応じて告知されます(例:2025年は4月下旬に頒布終了の案内あり)。書き置き対応の時期もあります。御朱印帳の表紙や墨が雨に濡れないよう、クリアファイルやビニール袋を用意しておくと安心。いただいたら境内の隅で軽く一礼し、今回の参拝の学びを一言メモしておくと、御朱印が“旅の記録”としても活きてきます。
参拝前に知っておきたい見どころ&ベストシーズン 📷
重要文化財がずらり:社殿・楼門・透塀の歩き方
根津神社の圧巻は、本殿・幣殿・拝殿・唐門・西門・透塀・楼門という七棟がそろって国の重要文化財に指定され、昭和6年(1931年)を中心に指定が行われ、昭和31年(1956年)に追加指定もあるという保存の厚み。透塀は全長約200m、地中約8mに達する基礎で支えられ、社殿群をぐるりと囲んで“聖域”のリズムを生み出します。鑑賞のコツは、まず全体の配置を把握してから、彫刻・金具・漆の艶といった細部の層に目を移すこと。火気厳禁・建物に触れないなどの掲示を守り、ていねいに歩きましょう。
文豪ゆかりのスポット(森鴎外・夏目漱石)
境内には、森鴎外が日露戦争の戦利砲弾の台座を転用した「森鴎外碑銘水飲場」や、地域の文化を象徴する「文豪の石」など、文学ファンにはたまらないポイントが点在します。鴎外も漱石も氏子としてこの地域に関わり、作品の舞台や登場人物の背景に“谷根千の気配”を残しました。社殿の色彩や鳥居の朱は、彼らが歩いた当時の東京とも通じる時間の層。静かな読書会のような気持ちで、言葉と景色を往復しながら歩くと、参拝体験がより豊かになります。
つつじまつりで楽しむ季節の根津神社
境内西側の丘「つつじヶ岡」には、約100種・3,000株のつつじが植えられ、例年4月ごろに文京つつじまつりが開催されます。期間中のみ入苑できるつつじ苑からは、権現造りの屋根と色とりどりの花の海が一望に。開苑時間や入苑券、限定御朱印や社宝の公開などの企画は年によって変動します。2025年シーズンは4月下旬に限定御朱印頒布終了の告知が出るなど、情報は随時更新されました。訪れる際は直近の公式お知らせをチェックしてから向かいましょう。
アクセスと混雑回避のコツ
最寄り駅は、東京メトロ千代田線「根津」「千駄木」、南北線「東大前」、都営三田線「白山」。いずれも徒歩5〜10分圏内です。境内(北参道側)には有料駐車場、参拝・祈祷・婚礼参列者向けの無料駐車場の案内もありますが、花の季節や休日は満車になりがち。平日午前の参拝と公共交通の併用が快適です。駅から歩く際は、谷根千らしい古い街並みと坂のリズムを楽しみつつ、ゴミは必ず持ち帰る――そんな小さな配慮が町歩きを心地よくしてくれます。
写真OK・NGの境界線と撮影エチケット
個人の参拝・観光の記念撮影は基本OK。ただし社殿前の参道(石畳上)は撮影禁止で、婚礼衣装のロケ撮影、企業主催の撮影会、素材配布・販売目的、露出の高い衣装・コスプレなどは不可。商用・放映目的は申請が必要です。千本鳥居の奉納者名が写り込む場合は角度を工夫するか、公開時にぼかす配慮を。シャッター音やフラッシュは控えめにして、祈りの時間を最優先。このマナーが守られてこそ、誰にとっても気持ちのよい神社時間になります。
まとめ
根津神社は「怖い」場所ではありません。背筋がすっと伸びる厳かな静けさと、日常から心を切り替える集中のスイッチがある場所です。乙女稲荷の千本鳥居や、願掛け榧の白蛇伝承がほんの少しのミステリアスさを添え、徳川ゆかりの七棟重文が江戸の美意識を今に伝えます。明治元年の准勅祭社、そして*975年発足の「東京十社めぐり」という文脈を知れば、単なる観光地ではない“東京の守護”としての顔も見えてきます。参拝作法と撮影ルールを守り、あなたの願いに合った授与品を一つ選び、祈り+実践+感謝のサイクルを1年続ける――それが、根津神社の“不思議”と仲よくなる最短ルートです。
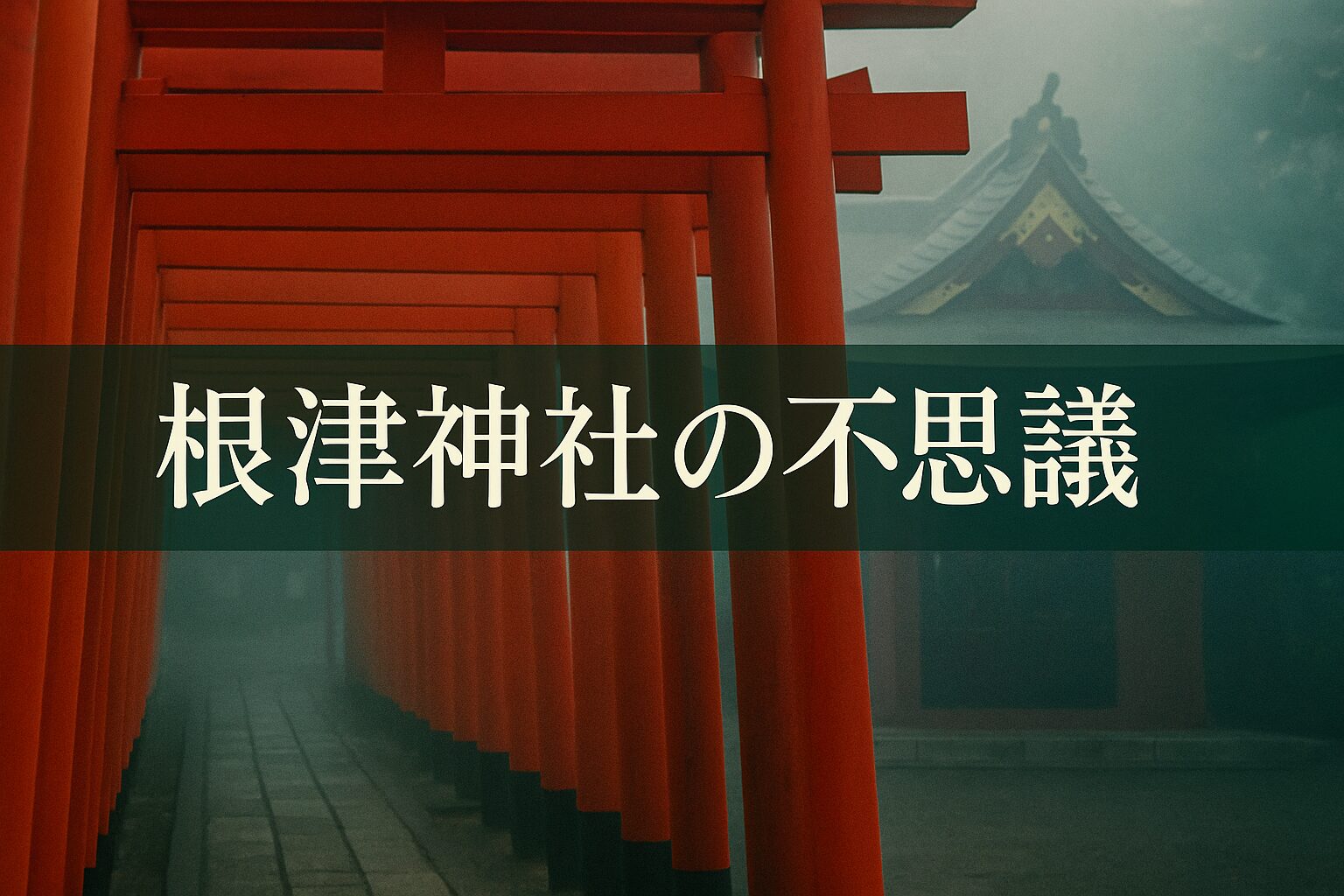

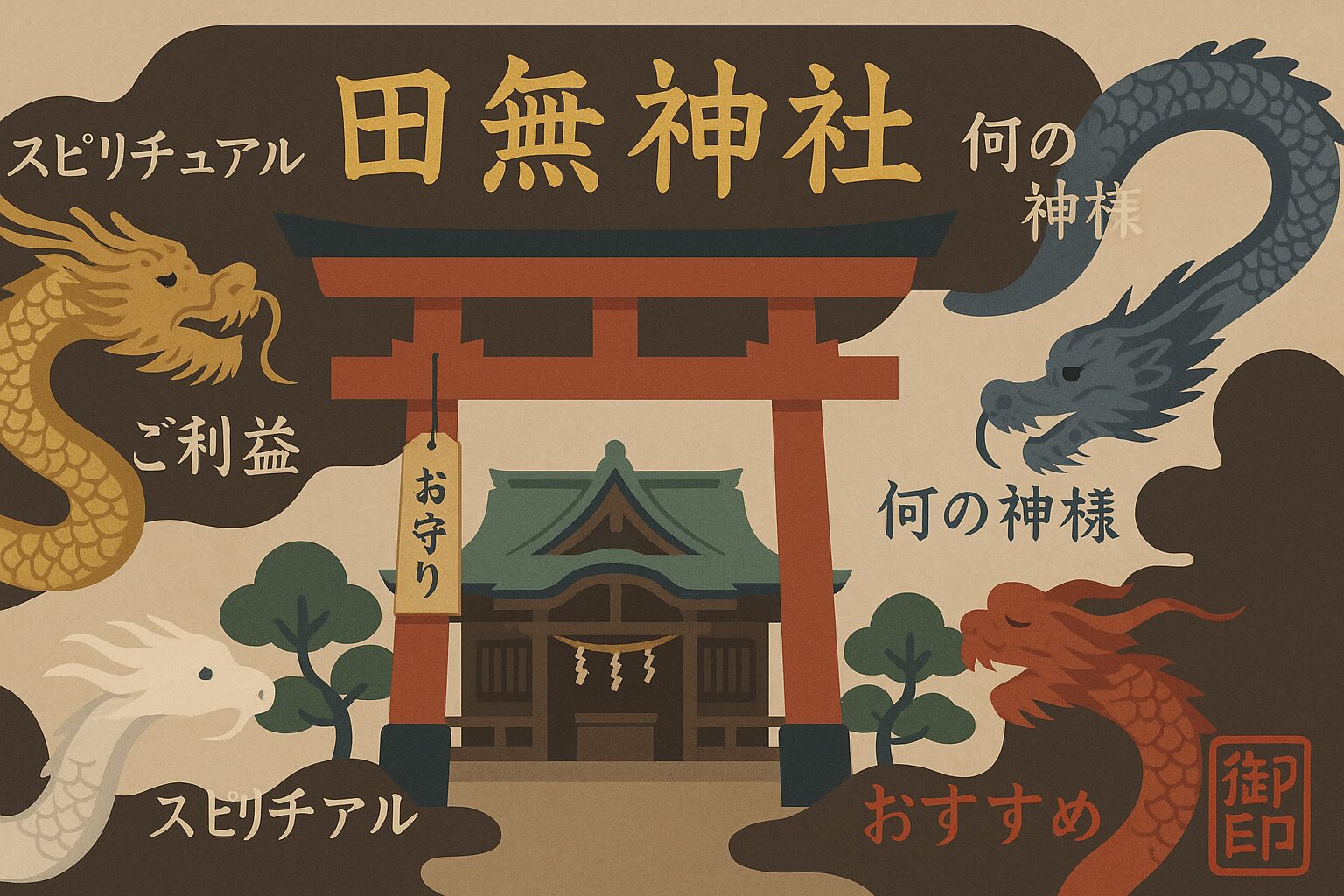

コメント